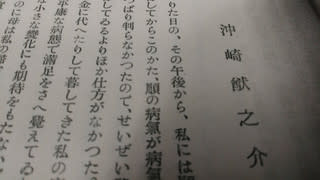親王は昔男と話をしながら夜更かしをする。昔男は早く帰りたい。しかし、親王はあるとき出家してしまった。
睦月に、をがみ奉らむとて、小野にまうでたるに、比叡の山のふもとなれば、雪いと高し。しひて御室にまうでてをがみ奉るに、つれづれといとものがなしくて、おはしましければ、やや久しくさぶらひて、いにしへのことなど思ひ出で聞こえけり。さてもさぶらひてしがなと思へど、おほやけごとどもありければ、えさぶらはで、夕暮れに帰るとて、
忘れては 夢かとぞ思ふ 思ひきや 雪ふみわけて 君を見むとは
伊勢物語のなかで一番好きなのはこの八三段である。まさに中年の昔男のエピソードなわけだが、とても良く出来た文章だと思う。この段より少し前にある、世の中に絶えて桜のなかりせば、という歌はいやだ。桜なぞなくなってもいっこうにかまわない。オリンピックも中止になるかもしれないし、最近なにか生きる希望が湧いてくるかんじがしないではない。とはいえ、桜やオリンピックはどうでもいいとしても、話し相手がいないと大変なことになりそうなのが人間であるので、――少しは話し相手がいて欲しいと思うこの頃である。
思うに、突然出家してしまった親王は、皇位の望みがなくなったからなのか知らないが、結局のところ、昔男と話がしたかっただけ、そういう人だったのかもしれないわけである。わたくしは、いまでも、さまざまな雑音を逃れてふたりで気楽なお話をしたいがために出家のようなことをする人がいると確信する。
ただ、わたくしは、こういう話が美しく感じるのを逃避だとも思う。だいたい、親王と昔男のような身分差の関係に憧れること自体がねじくれている(「アシガール」なんかがその少女趣味バージョンだ)。そういえば、「ブレードランナー」の新しい映画の最後でも雪が降っていた(妄想かも知れない)。アンドロイド?の孤独が染みるしんみりした場面だが、彼の孤独な状態が長すぎるせいか、わたくしはあんまり何かを感じなかった。しかし、八三段があまりにも理想的なものだとすればわれわれの状態は、この映画に近い。虚無ではないのだが、虚無以上にやる気を失わせる状態である。