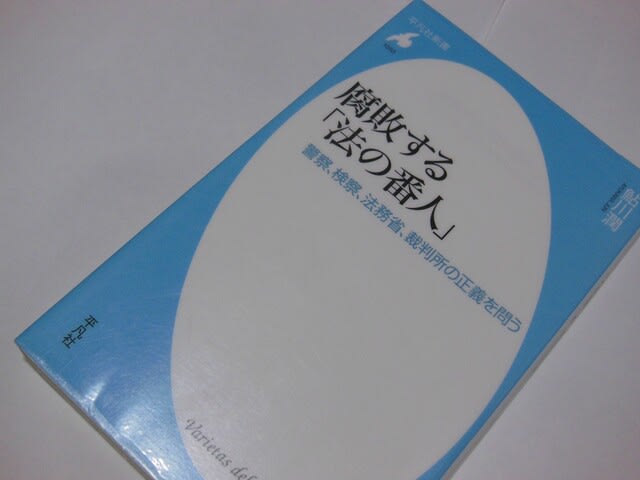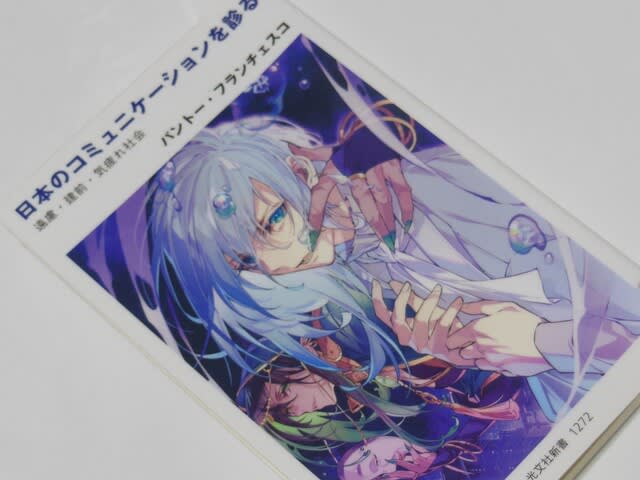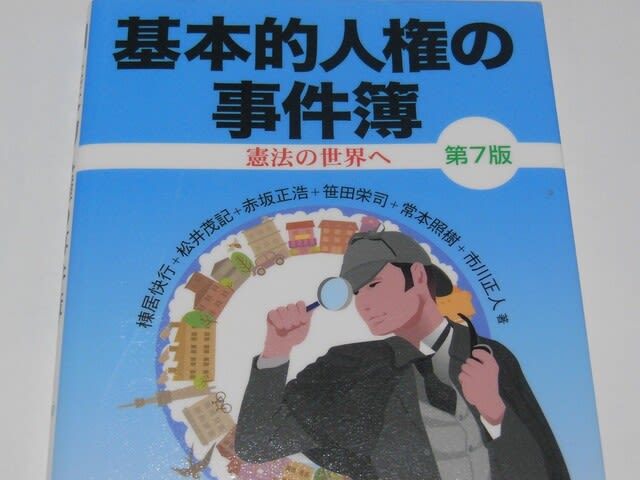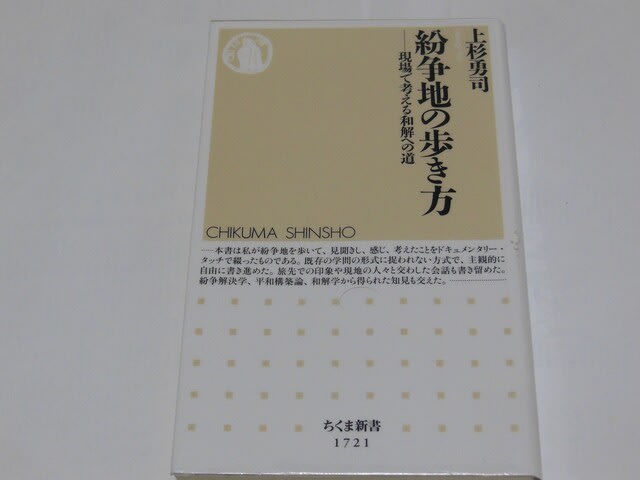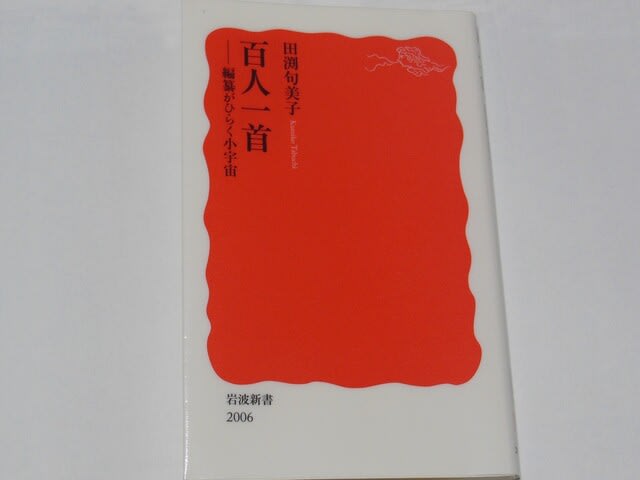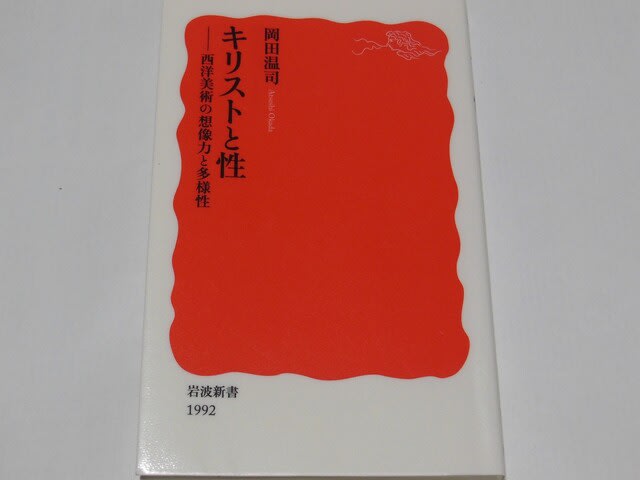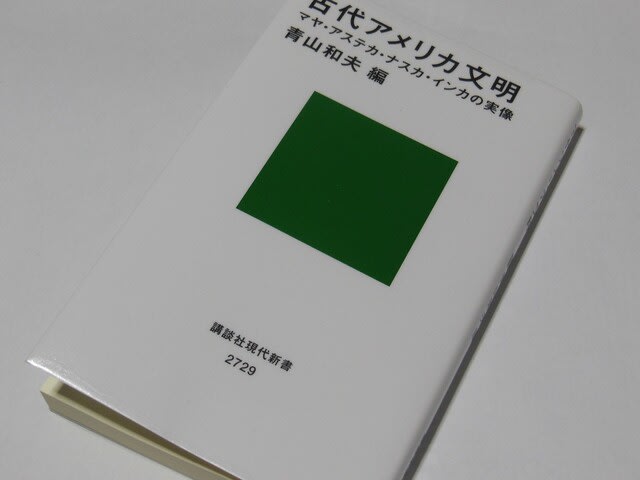警察の利権、警察の利害に乗せられたあるいは翼賛するマスコミ、検察の奢りと組織の論理、矯正の実情、最高裁の行政との癒着、お上の意に沿わぬ判決を書く裁判官に対する処遇差別等を論じた本。
権力組織の問題点を弾劾・断罪する論調は、私のような権力者嫌いの者には心地よく読めます。もっとも、裁判所批判の中で書記官・事務官・調査官らの労働条件が恵まれ、産休・育休等が充実していることを、利用者のことを第一に考えていないなどと批判しているくだり(187~192ページ)は、労働者の権利をやっかみ引きずり下ろそうとする、著者自身が使用者側に味方しているようなもので不快に思えました。
学者さんが書いたものにしてはなのか、学者さんが書いたものだからなのか、書かれていることの多くが他人が書いたものからの引用で、業界人にとっては既にどこかで聞いたようなことが大半で、まぁ取りまとめてはいますがあまり新味は感じません。
またどうしてだか報道で有名な固有名詞があえてイニシャルにしてあって、それが貫かれているならまだそういうポリシーかと思いますが、実名記載のものもありその基準もテキトーな気がして、ちょっと残念です(村木局長:なぜかこの本では村木局長は一貫して匿名、が逮捕・起訴された冤罪事件で証拠のフロッピーの作成日付を改ざんして実刑判決を受けた主任検事について、118ページでは「元主任検事は刑務所を出所後、社会で発生している事件の解説をインターネットで行い、閲覧者の関心を集めている」と匿名で書きながら、213ページにはその実名が書かれてるとか、著者の考えは私には理解できません)。

鮎川潤 平凡社新書 2024年2月15日発行
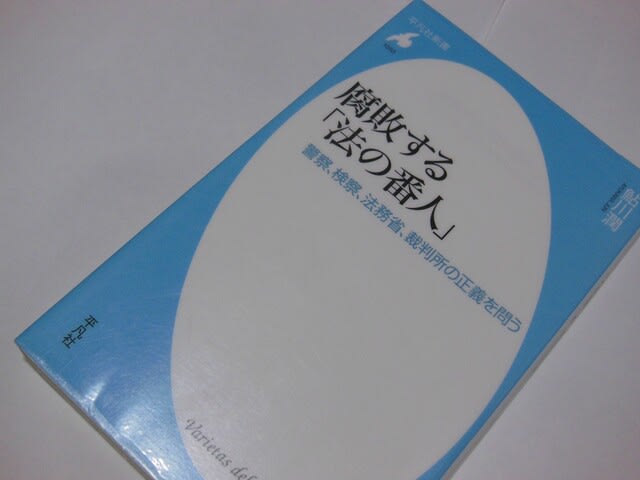
権力組織の問題点を弾劾・断罪する論調は、私のような権力者嫌いの者には心地よく読めます。もっとも、裁判所批判の中で書記官・事務官・調査官らの労働条件が恵まれ、産休・育休等が充実していることを、利用者のことを第一に考えていないなどと批判しているくだり(187~192ページ)は、労働者の権利をやっかみ引きずり下ろそうとする、著者自身が使用者側に味方しているようなもので不快に思えました。
学者さんが書いたものにしてはなのか、学者さんが書いたものだからなのか、書かれていることの多くが他人が書いたものからの引用で、業界人にとっては既にどこかで聞いたようなことが大半で、まぁ取りまとめてはいますがあまり新味は感じません。
またどうしてだか報道で有名な固有名詞があえてイニシャルにしてあって、それが貫かれているならまだそういうポリシーかと思いますが、実名記載のものもありその基準もテキトーな気がして、ちょっと残念です(村木局長:なぜかこの本では村木局長は一貫して匿名、が逮捕・起訴された冤罪事件で証拠のフロッピーの作成日付を改ざんして実刑判決を受けた主任検事について、118ページでは「元主任検事は刑務所を出所後、社会で発生している事件の解説をインターネットで行い、閲覧者の関心を集めている」と匿名で書きながら、213ページにはその実名が書かれてるとか、著者の考えは私には理解できません)。

鮎川潤 平凡社新書 2024年2月15日発行