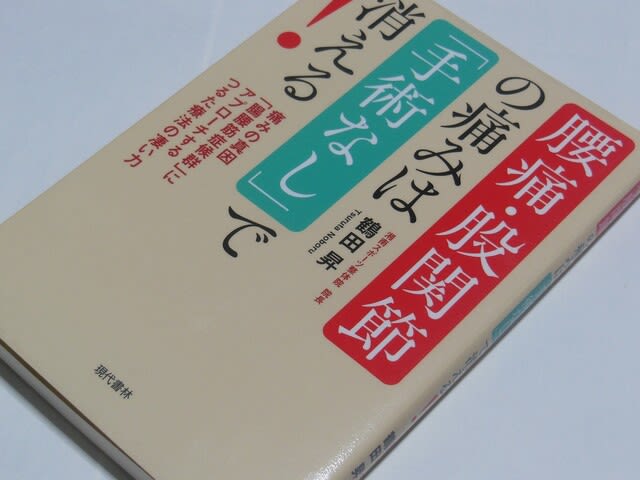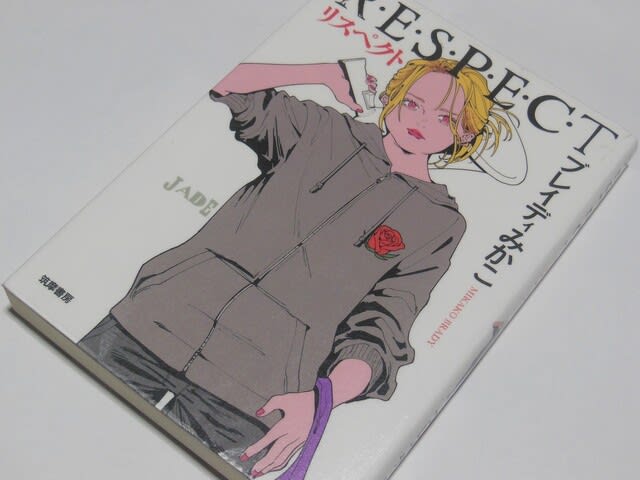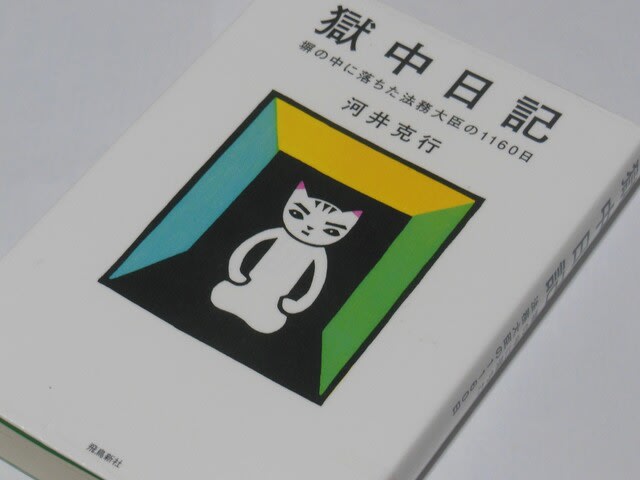東京の18のエリア(佃・月島・晴海、八重洲、有楽町、新富町、神田三崎町、神田神保町、千駄木、目黒、池袋、白金、春日、大久保、市谷柳町、四谷、原宿、大崎、一ツ橋、六本木)の地名の由来や町の成り立ちなどについて江戸時代(あるいはそれ以前)から明治、戦後にかけての通史や資料に基づいて、各地域見開き2ページの紹介と3つのテーマ合計8ページで蘊蓄を語る本。
興味深い話題が多く語られていますが、見開き2ページで左ページは一面絵という構成へのこだわりで、埋め草的なイラストも散見されるのと、高低差を示す地形図で高いところほど緑が濃い図(25ページ、33ページ、49ページ上図、81ページ、89ページ、109ページ、141ページ)と逆に高いところほど緑が薄く白っぽくなる図(49ページ下図、65ページ、99ページ、113ページ、121ページ、129ページ、153ページ)が混在していて直感的に混乱するのが残念に思えました。

岡本哲志 エクスナレッジ 2024年7月2日発行

興味深い話題が多く語られていますが、見開き2ページで左ページは一面絵という構成へのこだわりで、埋め草的なイラストも散見されるのと、高低差を示す地形図で高いところほど緑が濃い図(25ページ、33ページ、49ページ上図、81ページ、89ページ、109ページ、141ページ)と逆に高いところほど緑が薄く白っぽくなる図(49ページ下図、65ページ、99ページ、113ページ、121ページ、129ページ、153ページ)が混在していて直感的に混乱するのが残念に思えました。

岡本哲志 エクスナレッジ 2024年7月2日発行