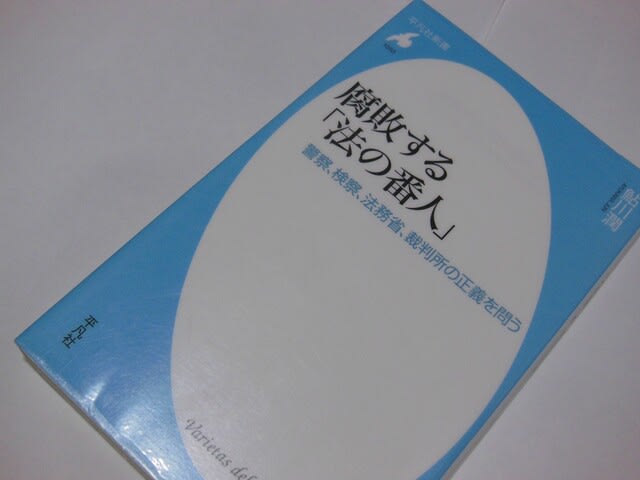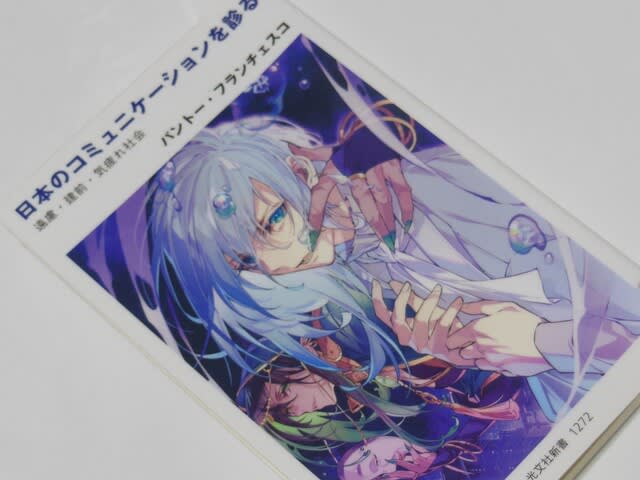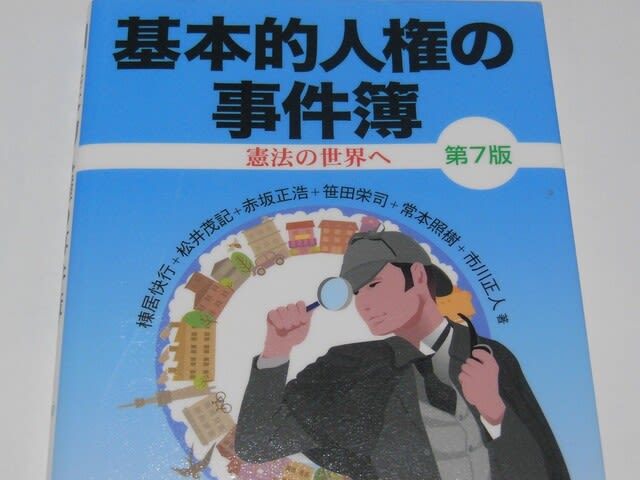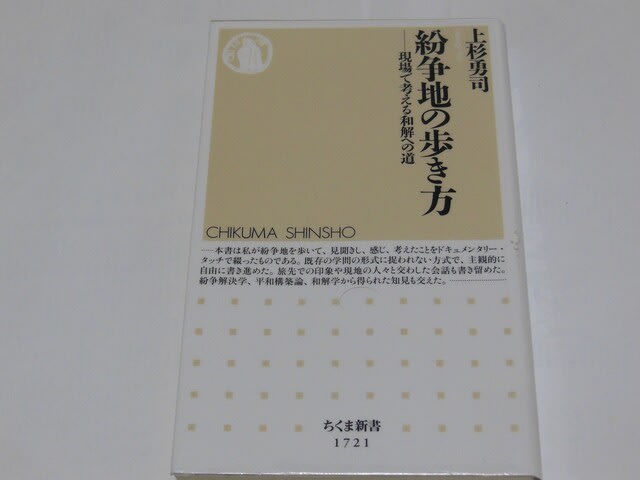哲学者である著者が、小学校高学年の娘と寝る前の10分間ベッドに寝転んですることにした哲学対話を紹介し、哲学対話を実践する意義と手法について述べた本。
紹介されている対話の例を読むと、小学生が飾らない言葉で本質を突いた発言をしているのが微笑ましく、他方父親の方はそれを小難しくまとめようとしているのが苦々しく思えました。自分もまた子どもにこういう感じで対応していた(しかし自分自身は子どもによくわかるようにかみ砕いたつもりでいた)のかもと。
対象が哲学でなくても、子どもと語り合う親密な時間というのは、著者もしみじみというように「宝物のような時間」(183ページなど)だと思います。私も、娘が小学生だった頃、寝る前の約1時間(10分では足りなくて)物語の読み聞かせ(寝かしつけ)をしていましたが、その頃の思いと考えが私のサイトの「女の子が楽しく読める読書ガイド」になって残っています(近年は更新していませんが)。著者の立場からは哲学を広め浸透させるための実践かも知れませんが、親子の大切な時間と関係を作る手段の1つとして読んでおいたらいいなと思います。

苫野一徳 大和書房 2024年5月30日発行
「教職研修」連載

紹介されている対話の例を読むと、小学生が飾らない言葉で本質を突いた発言をしているのが微笑ましく、他方父親の方はそれを小難しくまとめようとしているのが苦々しく思えました。自分もまた子どもにこういう感じで対応していた(しかし自分自身は子どもによくわかるようにかみ砕いたつもりでいた)のかもと。
対象が哲学でなくても、子どもと語り合う親密な時間というのは、著者もしみじみというように「宝物のような時間」(183ページなど)だと思います。私も、娘が小学生だった頃、寝る前の約1時間(10分では足りなくて)物語の読み聞かせ(寝かしつけ)をしていましたが、その頃の思いと考えが私のサイトの「女の子が楽しく読める読書ガイド」になって残っています(近年は更新していませんが)。著者の立場からは哲学を広め浸透させるための実践かも知れませんが、親子の大切な時間と関係を作る手段の1つとして読んでおいたらいいなと思います。

苫野一徳 大和書房 2024年5月30日発行
「教職研修」連載