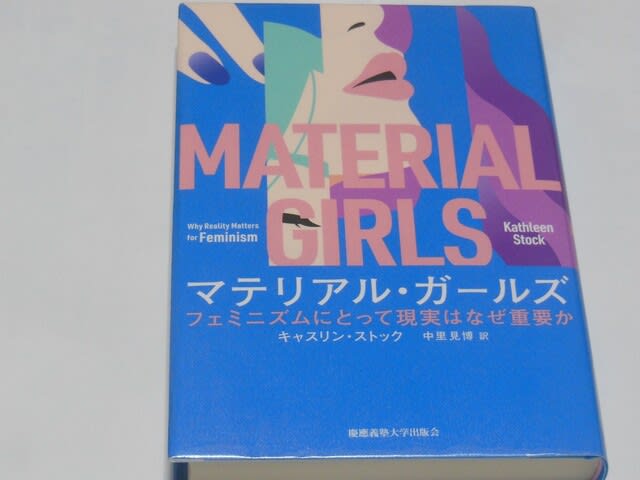トランプの出現やイギリスのEU脱退(ブレグジット)を受け止められず困惑するリベラリストに対して、リベラルエリートがいかに大衆に嫌われたかを指摘し、リベラルが残虐さへの恐怖の低減を訴えたジュディス・シュクラーの「恐怖のリベラリズム」に基礎を置くべきことなどを論じた本。
著者が右翼ポピュリズムを嫌悪しており、この本がリベラルを貶めることを目的としているのでないことは理解できますが、ではどうすべきかに関しては、虐げられた者の話をよく聞けということ以外は、私には今ひとつよくわかりませんでした。ヨーロッパの社会と政治をめぐる歴史と情勢を私がよく知らないためか、専門用語のためかあるいは訳文のためか、流し読んで頭に入ってこないというか、言っていることがなかなかストンと胸に落ちませんでした。
私が理解できた、虐げられた者の話をよく聞けということについても、著者がフランス政府のムスリムのブルカ着用に関する姿勢を非難している(101ページ)のは、ムスリムの女性は自分が好んで着用しているのだからこれを容認しないのはおかしいというのでしょうか。著者が依拠するシュクラーの「恐怖のリベラリズム」は、インドのカースト制や毛沢東の支配体制を挙げて、「危害と屈辱を受けた、世界中の革命政府と伝統的な政府の犠牲者たちに、彼らの現状に変わる真の実現可能な別の選択肢を提供することができない限り、私たちには彼らが自らを拘束する鎖を本当に受け入れているのかどうかを知る術はない。そして彼らがそれを受け入れているという証拠はほとんどない」と批判しています(159ページ)。社会内の力関係上声を上げにくい人々に対する抑圧を外部から批判することは、私には必要で正当なことに思えます(私には、この本に掲載されているジュディス・シュクラーの「恐怖のリベラリズム」の159~160ページで言われていることはそういうことだと思えるのですが)。私の意見は、著者の言うリベラルエリートの感覚なのでしょうけれども。

原題:Furcht und Freiheit
ヤン=ヴェルナー・ミュラー 訳:古川高子
みすず書房 2024年11月1日発行(原書は2019年)

著者が右翼ポピュリズムを嫌悪しており、この本がリベラルを貶めることを目的としているのでないことは理解できますが、ではどうすべきかに関しては、虐げられた者の話をよく聞けということ以外は、私には今ひとつよくわかりませんでした。ヨーロッパの社会と政治をめぐる歴史と情勢を私がよく知らないためか、専門用語のためかあるいは訳文のためか、流し読んで頭に入ってこないというか、言っていることがなかなかストンと胸に落ちませんでした。
私が理解できた、虐げられた者の話をよく聞けということについても、著者がフランス政府のムスリムのブルカ着用に関する姿勢を非難している(101ページ)のは、ムスリムの女性は自分が好んで着用しているのだからこれを容認しないのはおかしいというのでしょうか。著者が依拠するシュクラーの「恐怖のリベラリズム」は、インドのカースト制や毛沢東の支配体制を挙げて、「危害と屈辱を受けた、世界中の革命政府と伝統的な政府の犠牲者たちに、彼らの現状に変わる真の実現可能な別の選択肢を提供することができない限り、私たちには彼らが自らを拘束する鎖を本当に受け入れているのかどうかを知る術はない。そして彼らがそれを受け入れているという証拠はほとんどない」と批判しています(159ページ)。社会内の力関係上声を上げにくい人々に対する抑圧を外部から批判することは、私には必要で正当なことに思えます(私には、この本に掲載されているジュディス・シュクラーの「恐怖のリベラリズム」の159~160ページで言われていることはそういうことだと思えるのですが)。私の意見は、著者の言うリベラルエリートの感覚なのでしょうけれども。

原題:Furcht und Freiheit
ヤン=ヴェルナー・ミュラー 訳:古川高子
みすず書房 2024年11月1日発行(原書は2019年)