焼失「かんだやぶそば」再開へ…かえしも再現
昨年2月に火災で焼失した東京の老舗そば店「かんだやぶそば」(千代田区神田淡路町)は15日、今月20日から1年8か月ぶりに営業を再開すると発表した。(読売新聞)
暖簾と伝統の味を守り抜いて、これからしつかり頑張ってください。昨年2月に火災で焼失した東京の老舗そば店「かんだやぶそば」(千代田区神田淡路町)は15日、今月20日から1年8か月ぶりに営業を再開すると発表した。(読売新聞)
暖簾と伝統の味を守り抜いて、これからしつかり頑張ってください。>2014年10月15日 06時49分10秒 | 政治
◆ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ国境付近で軍事演習を展開していた軍部隊に対し、所属基地への撤収を命じ、「ウクライナ問題は終結した」という。
プーチン大統領のロシア軍撤収命令は、ウクライナのポロシェンコ大統領(米国CIAのスパイ説あり)が、ゲレテイ国防相から提出された辞職願を受け入れ
たのを評価した結果であった。ポロシェンコ大統領は10月13日、最高会議(議会)で新国防相の候補者を提案したという。
ロシアの声(ラジオ)は10月13日午前11時5分、「ポロシェンコ大統領 恥さらしのウクライナ国防相を解任」というニュースのなかで、ゲレテイ国防相について、こう伝えている。
「ゲレテイ氏は、知識不足と挑発的な発言で知られていた。例えば、ロシアからウクライナに最新の徹甲弾が供給されていると主張し、その証拠として、口径
7.62ミリのソ連製ライフル用カートリッジを提示したほか、ロシアがウクライナに対して戦術核兵器を使用したなどという不条理な発言を行ったりしてい
た。ウクライナ議会では、このような発言が、ウクライナ軍司令部の信用を失墜させるとの意見も出た。ゲレテイ氏は、ウクライナ東部における軍事作戦中に、
クリミアのセヴァストポリで勝利パレードを実施するとも約束した」
◆しかし、ロシアのプーチン大統領が、「ゲレテイ国防相の首を取った」のは、あくまでも表向きの「体面と辻褄合わせ」にすぎない。本当は、「ゴールデン・
ファミリーズ・グループ」(300人の個人委員会)の中心的存在である欧州最大財閥ロスチャイルド総帥ジェイコブ・ロスチャイルドの強い指示に従ったので
ある。
その指示とは「ロイヤル・ファンド」(いわゆる「天皇家の金塊」)が生む富から巨額資金が分配されるので、欧州諸国は、値上げされて高くなったロシアの
「天然ガス」を言い値通りで買うことができる。いい加減手を引けというものだった。プーチン大統領が、ウクライナ問題を終結しなければ、「冬将軍に襲われ
て、欧州諸国で多数の凍死者が出る」ことになる。ジェイコブ・ロスチャイルドは、こうした事態が現実化するのを憂慮し、欧州諸国に対しては、「高くても
買ってやれ」と指示した。ギリギリのところで、直前に手を打ってきたのである。
◆米国オバマ大統領はじめ、バイデン副大統領、ケリー国務長官、ヘーゲル国防相らは、いまのところ、ロシアのプーチン大統領が、ウクライナ国境付近で軍事
演習を展開していた軍部隊に対し、所属基地への撤収を命じたことについて、何もコメントしていない。背後でジェイコブ・ロスチャイルドが手を回したことを
知っているからである。
しかし、仮にイチャモンをつけられても、プーチン大統領は、「米国が何を言ってこようが、関係ない」と屁の河童である。それは、ジェイコブ・ロスチャイルドが、自分の強い後ろ盾であることを誇りに思っているからだ。
要するに、いま欧州とロシアは、ジェイコブ・ロスチャイルドを強い後ろ盾としたプーチン大統領が動かしているということだ。オバマ大統領は、「イスラム国」に小突き回されて、欧州やロシアどころではないのである。
【参考引用】ロイターが10月13日午後1時46分、「ロシア大統領、ウクライナ国境付近からの軍撤収を命令」という見出しをつけて、以下のように配信した。
「[モスクワ 12日 ロイター]
ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ国境付近で軍事演習を展開していた軍部隊に対し、所属基地への撤収を命じた。大統領報道官が明らかにした。
16─17日にイタリアのミラノで開催されるアジア欧州会議(ASEM)首脳会議では、ロシアとウクライナの首脳会談が予定されており、これをにらんだ動
きとみられる。ロシア大統領府ウェブサイトによると、ショイグ国防相から現地での軍事演習終了の報告を受け、大統領が所属基地への撤収を命じた。国境付近
では合計で1万7600人の部隊が演習を行っていた。ロシア通信(RIA)は国防省の発表として、部隊はすでに撤収を開始したと伝えている。
本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
鳩山由紀夫元首相が小沢一郎代表の代理で訪ロ、ナルイシキン下院議長と会談、舞台裏で何が起きている?
◆〔特別情報①〕
ロシアのプーチン大統領が、ウクライナ国境付近で軍事演習を展開していた軍部隊に対し、所属基地への撤収を命じたという。ロイターが10月12日報じ
た。これに即応するかのように、モスクワを訪問中の鳩山由紀夫元首相が13日、プーチン大統領の側近であるナルイシキン下院議長と会談し、このなかで
「2015年に東京で開催される第10回ロシア文化フェスティバルに合わせてのプーチン大統領訪日」を提案したという。日ロ外交に詳しい専門家によると、
「鳩山由紀夫元首相は、小沢一郎代表の代理として訪ロし、ナルイシキン下院議長と会談した」という。一体、日本外交の舞台裏で何が起きているのか?
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
携帯電話からのアクセスはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
携帯電話から有料ブログへのご登録
「板垣英憲情報局」はメルマガ(有料)での配信もしております。
お申し込みはこちら↓

板垣英憲マスコミ事務所からも配信しております。
お申し込みフォーム
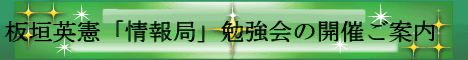
第35回 板垣英憲「情報局」勉強会のご案内
平成26年11月9日 (日)
「黒田官兵衛と孫子の兵法」
~秦ファミリーの秘密がいま明らかになる
◆新刊のご案内◆
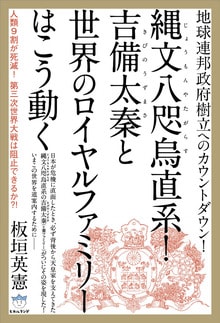
「地球連邦政府樹立へのカウントダウン!
縄文八咫烏直系!
吉備太秦と世界の
ロイヤルファミリーはこう動く」
著者:板垣 英憲
超★はらはらシリーズ044
☆2014年9月下旬発売予定☆
◎ 日本が危機に直面した時、かならず背後から天皇家を支えてきた縄文八咫烏(じょうもんやたがらす)直系の吉備太秦(きびのうずまさ)(=秦ファミリー)がついにその姿を現した!今この世界を道案内するためにー...
詳細はこちら→ヒカルランド
中国4分割と韓国消滅
ロスチャイルドによる衝撃の地球大改造プラン
金塊大国日本が《NEW大東亜共栄圏》の核になる
著者:板垣 英憲
超★はらはらシリーズ040
☆絶賛発売中☆
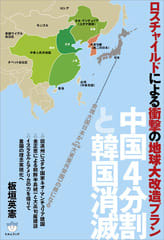
詳細はこちら→ヒカルランド
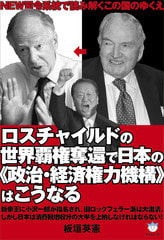
こちらも好評発売中 「ロスチャイルドの世界派遣奪還で日本の《政治・経済権力機構》はこうなる」(ヒカルランド刊)
■NEW司令系統で読み解くこの国のゆくえ―新帝王に小沢一郎が指名され、旧ロックフェラー派は大粛清、しかし日本は消費増税分の大半を上納しなければならない
詳細はこちら→ヒカルランド
**********板垣英憲『勉強会』の講演録DVD販売********
板垣英憲・講演録DVD 全国マスコミ研究会
 9月開催の勉強会がDVDになりました。
9月開催の勉強会がDVDになりました。
「マッキンダーの『地政学』がいま蘇る~プーチン大統領は『ハートランド』を支配し、世界を支配するのか」
その他過去の勉強会もご用意しております。遠方でなかなか参加できない方など、ぜひご利用下さい。
板垣英憲・講演録DVD 全国マスコミ研究会
【板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作集】
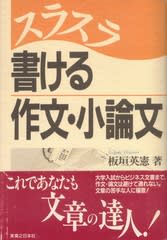
『スラスラ書ける作文・小論文』(1996年4月20日刊)
目次
第1章 自分探しの技法
7「十のテーマ」を定点観測する
【定点観測5=為替動向、一ドル=七○円時代へ突入、一転して、一〇〇円台へ】
円高問題は、輸出産業を深刻な状況に陥れた。日本経済の本当の実力を見定めるにはいい機会と思われた。いまや国内の経済だけを考えてはいられない。国際的な規模で見る時代だ。
引用元http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/1bab706c46a700b594f50efaff297716
きょうの産経新聞が小さく報じていた。
米国ニューヨーク・タイムズ(電子版)が13日までに日本の教育戦略は分裂に陥っていると書いていたことがわかったと。
すなわち、一方において教育の国際化を掲げながら、他方において愛国的な教育を推進して近隣諸国の反発を招いている、これは精神分裂だというわけだ。
そう思っていたら、今度はきょうの各紙が書いていた。
安倍首相は伊原外務省アジア局長を13日までの連休中に中国に極秘派遣して日中首脳会談の地ならしをしていたことがわかったと(読売)。
その一方で、すなわち高市早苗総務相は14日の閣議後の記者会見で17日から行われる靖国神社の秋季例大祭にあわせ靖国参拝を行う意向を示し、 政府は14日の閣議で、客観的事実にもとづく正しい歴史認識が形成され、日本の立場が正当な評価を受けるように、慰安婦問題に関する対外発信力をこれからも強化していくとする答弁書を決定したという(朝日)
これこそ分裂の極みだ。
教育戦略の分裂だけでなく外交戦略の分裂だ。
いったい安倍首相は何をしたいというのか。
お願いだから、安倍首相はこれ以上歴史認識問題で世界に恥をさらさないでくれ。
日本国民が皆、そうだと思われてはたまったものじゃない(了)
外交評論家
2003年、当時の小泉首相に「米国のイラク攻撃を支持してはいけない」と進言して外務省を解雇された反骨の元外交官。以来インターネットを中心に評論活動をはじめ、反権力、平和外交、脱官僚支配、判官びいきの立場に立って、メディアが書かない真実を発信しています。主な著書に「さらば外務省!」(講談社)、「さらば日米同盟!」(講談社)、「アメリカの不正義」(展望社)、「マンデラの南アフリカ」(展望社)。
岡雄一郎
朝日新聞デジタル2014年10月15日05時33分
地域によって広がる大学進学率の差は、能力があるのに進学できないという状況を生んでいる。大学の少ない地域から、大都市圏の大学をめざす高校生を持つ家庭には下宿代などの経済負担がのしかかる。
「本当は大学に行きたいんだけど、親から言われたんだよね」。青森県立 の高校で進路指導を担当する50代の男性教諭は今春、3年生の女子生徒が冗談めかした言葉に、切なくなった。提出された進路調査の第1志望欄には「公務 員」。国立大も狙える学力だが、重い費用負担が理由だ。大学生の兄がおり、「妹の学費まで賄えないのだろう」と推し量った。 例年、約300人の3年生全員が進学を志望するが、今年は就職希望者が約20人。同僚と「経済的な理由だろう」と話した。かつて成績上位の生徒に東北大(仙台市)を勧めたら、生徒の親から「金がかかる。余計なこと言わないで」と怒られたこともあった。 隣の秋田県。小中学生の全国学力調査で上位の常連だが、高校生の大学進学率は42%で全国平均(54%)を下回る。「経済状況もあり、単純に『学力調査=進学率』とはいかない」と県教育委員会の担当者は言う。 「進学の機運を高めて、頑張る高校生を応援しよう」と県教委は2010年、東大など難関大学の現役合格者数を数値目標に掲げた県高校総合整備計画を策定。希望する高校生向けに予備校講師による「ハイレベル講座」を開くなどの支援に取り組んでいる。』
日本経済のバブル崩壊後、失われた三十年で都市圏でも家庭の所得格差が、拡大している今日、都市圏と地方圏との所得格差は是正されず拡大しているの現実と思います。株高になっても実体経済の景気回復がしてていない現状では、経済的に豊かな受験生でないと下宿して大学に進学するのは困難と言えますし、受験生の地元゛大学志向は当分続くのでは有りませんか。受験生を持つ家庭の台所が豊かにならない限り、地方の大学進学率は改善されないと思います。先立つものはお金です。日本の受験生に見る教育に及ぼしている経済状況、景気動向の実態結果とも言えます。