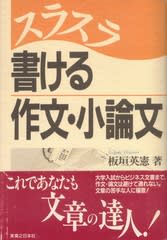先般「アジアでトップクラスの英語力」という
目標設定がいかに無意味かを説明しました。
今日は「世界大学ランキングトップ100に
10校以上」という目標設定の問題について
ご説明したいと思います。
この目標は「日本再興戦略」のひとつであり、
閣議決定済みの文章に出てくる表現です。
それなりに練り上げられた政策と思ったら、
それは大きな間違いでした。驚きます。
安倍政権・自民党の教育政策の目標設定が、
いかにいい加減かがよくわかるでしょう。
まず「どのランキングを使うのか」という点。
もっとも基本的かつ重要な点だと思います。
文科省の担当者に直接電話して聞いてみたら、
驚くことに「決まっていない」との回答。
いろんな大学評価のランキングがある中で、
どのランキングを使うか未定だそうです。
世界の大学ランキングに関して有名なのは、
英国の出版社「Times Higher Education」、
英国の評価機関「Quacquarelli Symonds」、
上海交通大学といったものでしょうか。
複数の大学ランキングが存在するなかで、
どの大学ランキングを用いるかによって、
トップ100に何校入るかは変わります。
政策を評価するには指標が必要です。
政策の実施前に指標を決めておかないと、
後出しジャンケンになってしまいます。
しかし、最も基本的な指標が未定です。
こんなものは政策目標とは言えません。
さらにそもそも世界大学ランキングが、
大学教育の質を計る基準として有効か、
という別の問題も存在します。
2014年のTimes Higher Education の
World University Rankings100位以内
の大学を国別に分けるとこんな感じです。
・米国: 46
・英国: 11
・ドイツ: 6
・オランダ: 6
・オーストラリア: 4
・カナダ: 4
・スイス: 3
・スウェーデン: 3
・韓国: 3
・日本: 2
・中国: 2
・香港: 2
・シンガポール: 2
・ベルギー: 2
・フランス: 2
・トルコ: 1
・イタリア: 1
日本のメディアや有識者が言及するのは、
多くの場合、この大学ランキングでしょう。
社説にも「日本の大学は世界ランキングの
100位以内に2校しか入らない」と書かれ、
多くの日本人はこのランキングを基準にし、
日本の大学のレベルの低さを嘆きます。
大学の教育環境、研究の影響力、引用数等、
具体的な指標を基にランク付けされます。
英語で書かれた情報をもとに評価するため、
非英語圏はかなり不利な競争条件です。
ノーベル賞受賞者数で上位のフランス、
ロシアといった国が評価されません。
フランスが2校しか入っていないし、
ロシアは1校も入っていません。
ロシアやフランスは、日本と同様に、
母国語で大学教育を受けられます。
英語の論文数等の指標で不利です。
フランスで最高のランキングの大学が、
61位で、ボストン大学より下です。
フランスの大学はもっと上位に来ても
全然おかしくないと思います。
ロシアやフランス、日本といった国は、
共通のハンディキャップを持っており、
この手のランキングでは低評価です。
英語圏の大学や旧英領の国が有利です。
また欧州の小国も英語教育に熱心だし、
英語が準公用語なので有利です。
一方、同じTimes Higher Educationが、
別の大学ランキングをやっています。
そのランキングは印象が異なります。
そっちは World Reputation Rankingsで、
各国の大学教員のアンケート調査により、
専門家による評価を重視したものです。
そっちのランキングの100位以内の
大学を国別に分けるとこんな感じです。
・米国: 46
・英国: 10
・ドイツ: 6
・日本: 5
・オーストラリア: 5
・オランダ: 4
・カナダ: 3
・香港: 3
・韓国: 3
・スイス: 2
・中国: 2
・シンガポール: 2
・フランス: 2
・ロシア: 1
・イスラエル: 1
・ブラジル: 1
・スウェーデン: 1
・ベルギー: 1
・トルコ: 1
・台湾: 1
こっちの方が地域的バランスがよく、
若干信頼度が増すように思います。
それでも英語圏が有利なままです。
フランスの大学の評価が異様に低いのは、
謎のまま残るのですが、もしかすると、
フランス独特のグランゼコール制度が、
理由なのかもしれません。
ロシアやイスラエル、台湾等からは、
その国のトップ校が入っているので、
ちょっと安心感があります。
なお、こっちの世界ランキングだと、
すでに日本の大学は5校入っており、
あと5校増やすだけで目標達成です。
いまは東大、京大、大阪大、東北大と
東京工業大学が100位以内につけ、
さらに北大や名古屋大等を強化すれば、
10校ランクインも夢ではありません。
なお、総合的な大学ランキングの欠点は、
大規模な大学しか評価対象にならなくて、
少人数教育の大学は対象外です。
米国に「リベラルアーツカレッジ」という
教養教育を重視する小さな大学が多数あり、
レベルの高い教育を行っています。
こういう大学は学部教育に特化していて、
大学院は設置していないケースも多くて、
ランキングの対象になりません。
蛇足ながら、わが母校の国際基督教大学も、
米国のリベラルアーツカレッジをモデルに、
少人数教育を売り物にしてきた大学なので、
大学ランキングには相手にされません。
また私が大学院修士課程を終えた大学も、
教育学だけに特化した大学院大学なので、
この手のランキングの対象外です。
もっとも「教育学」分野のランキングは存在し、
わが母校はQS社のランキングで世界一で、
ちょっと自慢でした。もっともランキングには、
信頼を置いていないので、重視しません。
以上のような理由から、安倍政権が掲げている
「世界大学ランキングトップ100に10校」
という目標設定がダメなことがわかります。
もうちょっと比較教育学の専門家とか、
高等教育の専門家の意見を取り入れて、
より有意義な目標を考えるべきです。
わかりやすさを最重視する「教育再生」は、
専門家を軽視する反知性主義の傾きがあり、
第一次安倍政権の頃から批判してきました。
安倍政権の「教育再生」に関する問題点に
ご関心のある方(いないと思いますが)は、
私が書いた以下の小論もご参照ください。
*「教育改革の改革を:教育再生会議への七つの疑問」
岩波書店『世界』2007年6月号













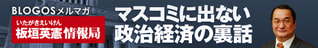
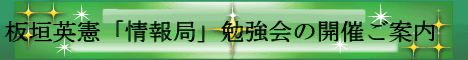
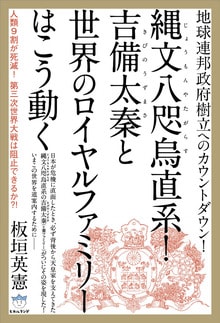
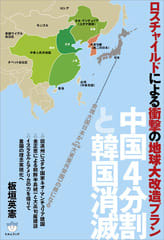
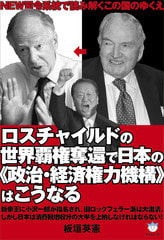
 9月開催の勉強会がDVDになりました。
9月開催の勉強会がDVDになりました。