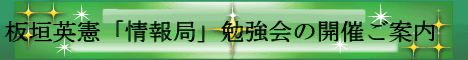「人と話す機会がめっきり減った」という人は誤嚥に要注意
「最近首がたるんできたような……」こんな異変があれば、注意が必要だ。命に関わる「誤嚥(ごえん)」の可能性がある。秋津医院の秋津壽男院長が解説する。
「誤嚥とは、食べ物や唾液が食道でなく、誤って気管に入ることを指します。加齢によって喉の筋肉が衰え、ものを飲み込んで胃に送る嚥下機能が低下することが主な原因です。
誤嚥の多くは咳やむせるなどの咳嗽(がいそう)反応(排出作用)が出ますが、怖いのは咳嗽反応のない『不顕性誤嚥』です。睡眠中に口腔内の菌が唾液などに混じって気管から肺へと到達し、誤嚥性肺炎を引き起こして、重症化するケースも少なくない。
就寝中の誤嚥性肺炎は反応が出ないので気づきにくいのですが、不顕性誤嚥の場合、首がたるんだり、細くなるなどして喉仏が下がってくるという身体的な兆候が見られることがあります。喉仏をつり上げている筋肉などが伸びてしまっているからです。
風邪でもないのにちょっとしたことで咳き込むことが多い方も、睡眠中に不顕性誤嚥をしている可能性があるので、耳鼻咽喉科にかかることが大切です」
日本人の死亡原因の3位を占める肺炎だが、65歳以上の肺炎死亡者に限れば、その大半が「誤嚥性肺炎」が直接的な死因になっている。
「不顕性誤嚥は気づくのが難しいからこそ、日頃から喉の筋肉を鍛え、嚥下機能を高めることが重要になります」(同前)
最も簡単な鍛錬法は食事の際、よく噛んで飲み込むという習慣を付けることだ。顎周辺だけでなく、喉の筋肉も使うことになるため、嚥下機能の強化に繋がる。
声を出すことも有効な対策。「発声しない時間が多くなると嚥下機能の低下を促す」(同前)とされ、リタイア後、人と話す機会がめっきり減ったという人は要注意だ。
ちょっとした嚥下機能の低下に気づくことも大切になる。飲み込む力が弱くなると、唾液の切れが悪くなり、よく痰が出るようになったり、朝起きたときに胸がむかむかする、水を一気に飲もうとするとむせ込んでしまうなどの傾向が出るようになるという。
喉でわかる“兆候”を見逃さず、命に関わる病気を防ぐ手立てにしたい。
※週刊ポスト2019年3月8日号