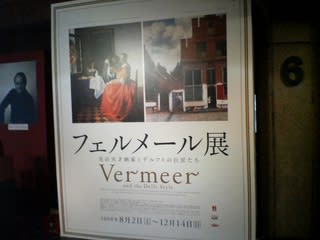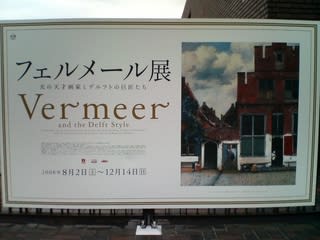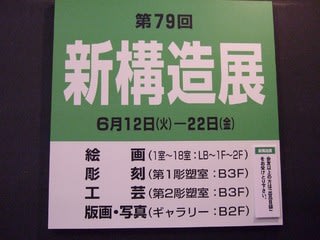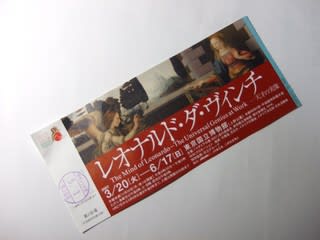昨日、八王子へ自転車で出かけた帰り、八日町にある八王子夢美術館で開催されている展覧会”魯山人の宇宙”を見てきました。私が住んでいるマンションの掲示板にパンフレットが掲示されていたので、何となく気になっていたのです。
北大路魯山人。名前は良く聞きます。最近では「料理の鉄人」というフジテレビの番組で"魯山人の愛弟子"と紹介されていた審査員(平野雅章)が印象に残っています。魯山人は今年が丁度没後50年にあたるらしく、各地で様々な催しが開催されています。夢美術館での展覧会もその一環のようです。
説明によると、魯山人は陶芸や書、絵画、漆芸など幅広い分野で伝統に学びつつ斬新で個性的な作品を生み出した芸術家で、食通としても名前が知られています。特に陶芸においては料理と食の調和を求めた魅力溢れる作品を生み出し、この展覧会ではアメリカ・サンディエゴから里帰りしたカワシマ・コレクションを中心に数多くの秘蔵の名品が展示されています。
私は陶芸の世界は素人で良く分かりませんが、繊細かと思えば斬新で大胆な作品もあり、見ていて飽きませんでした。交友関係も広く、イサム・ノグチやシャガール、ピカソとも親交があったとのこと。
展覧会の様子は、八王子夢美術館のHPを参照下さい。
http://www.yumebi.com/

帰りに、甲州街道沿いでちょっと面白い店を発見。染料や化学工業薬品を扱う「橋本要助商店」です。店内ではビーカーやリトマス紙なども販売していますが、人目を引くのは店頭に飾られているストーンアートです。テレビでも紹介されたみたいです。
北大路魯山人。名前は良く聞きます。最近では「料理の鉄人」というフジテレビの番組で"魯山人の愛弟子"と紹介されていた審査員(平野雅章)が印象に残っています。魯山人は今年が丁度没後50年にあたるらしく、各地で様々な催しが開催されています。夢美術館での展覧会もその一環のようです。
説明によると、魯山人は陶芸や書、絵画、漆芸など幅広い分野で伝統に学びつつ斬新で個性的な作品を生み出した芸術家で、食通としても名前が知られています。特に陶芸においては料理と食の調和を求めた魅力溢れる作品を生み出し、この展覧会ではアメリカ・サンディエゴから里帰りしたカワシマ・コレクションを中心に数多くの秘蔵の名品が展示されています。
私は陶芸の世界は素人で良く分かりませんが、繊細かと思えば斬新で大胆な作品もあり、見ていて飽きませんでした。交友関係も広く、イサム・ノグチやシャガール、ピカソとも親交があったとのこと。
展覧会の様子は、八王子夢美術館のHPを参照下さい。
http://www.yumebi.com/

帰りに、甲州街道沿いでちょっと面白い店を発見。染料や化学工業薬品を扱う「橋本要助商店」です。店内ではビーカーやリトマス紙なども販売していますが、人目を引くのは店頭に飾られているストーンアートです。テレビでも紹介されたみたいです。