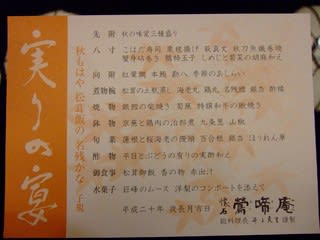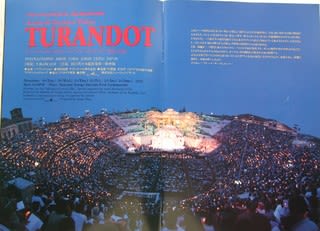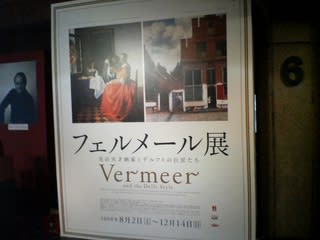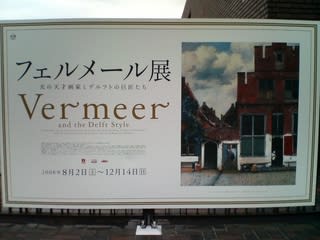10月も下旬になり朝晩の冷え込みにようやく秋の深まりを感じるようになりました。10月30日に大分へ出張に行く際、飛行機の窓から雪化粧した日本アルプスを撮影したので紹介します。

富士五湖を過ぎるあたりから雲が切れて甲府盆地が姿を現しました。

やがて南アルプスの峰々が眼下に広がります。間ノ岳や最初の写真の手前に映っている悪沢岳では山頂付近がうっすら白くなっていました。甲斐駒ケ岳では10/27に甲府から初冠雪が観測されています。

伊那盆地の西には木曽駒ケ岳を中心とする中央アルプスが広がります。山頂付近は冠雪がはっきりと確認できました。

更に進むと、御嶽山から乗鞍岳・北アルプス方面が広がります。山頂付近は雲がかかっていますが雪をかぶった姿がはっきりと分かりました。

暫くすると加賀の白山が見えてきます。白山の初冠雪は飛行機に乗った当日、金沢から観測されたそうです。

当日はかなり北よりのルートをとり、琵琶湖北岸から若狭湾、中国山地を経由し広島上空を通過しました。中国山地上空は雲に覆われていましたが、雲間から広島の街がはっきりと確認できました。

富士五湖を過ぎるあたりから雲が切れて甲府盆地が姿を現しました。

やがて南アルプスの峰々が眼下に広がります。間ノ岳や最初の写真の手前に映っている悪沢岳では山頂付近がうっすら白くなっていました。甲斐駒ケ岳では10/27に甲府から初冠雪が観測されています。

伊那盆地の西には木曽駒ケ岳を中心とする中央アルプスが広がります。山頂付近は冠雪がはっきりと確認できました。

更に進むと、御嶽山から乗鞍岳・北アルプス方面が広がります。山頂付近は雲がかかっていますが雪をかぶった姿がはっきりと分かりました。

暫くすると加賀の白山が見えてきます。白山の初冠雪は飛行機に乗った当日、金沢から観測されたそうです。

当日はかなり北よりのルートをとり、琵琶湖北岸から若狭湾、中国山地を経由し広島上空を通過しました。中国山地上空は雲に覆われていましたが、雲間から広島の街がはっきりと確認できました。