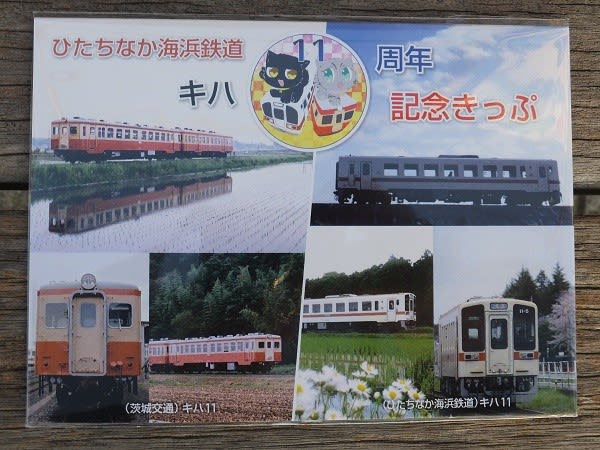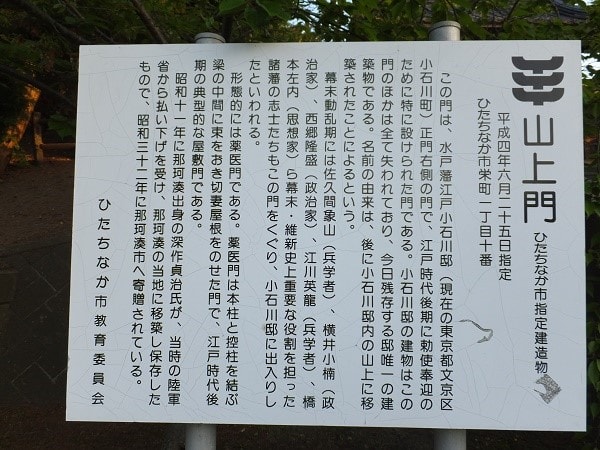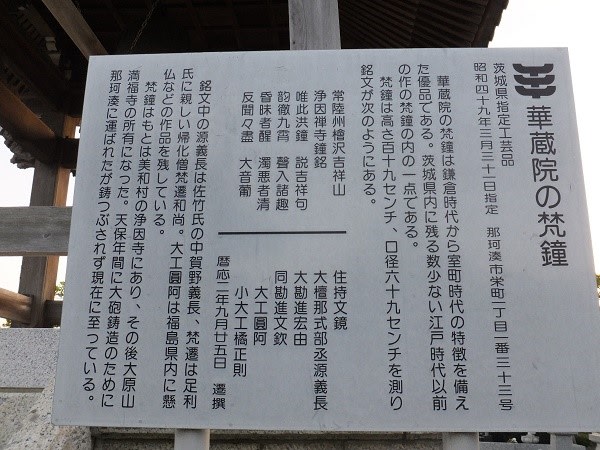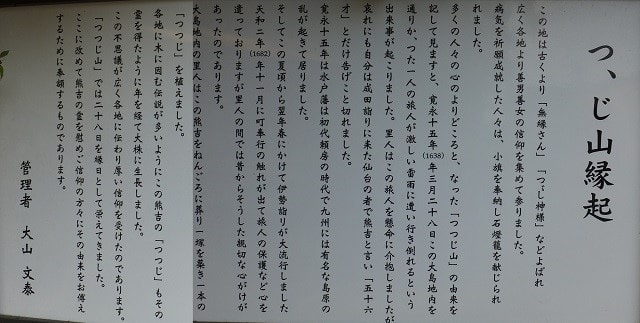昨夜は早く床に入ったためか眠りが浅く、朝4時前に目が覚めてしまいました。久しぶりの超早起きです。しかし外は明るくなっていました。今月末にちょっとした登山を計画中で、その足慣らしに筑波山にでも寄って戻ろうかと考えましたが、一日がかりになってしまい昼前に戻るのは難しそう。奥日光のアカヤシオが見頃との情報なので寄ってみようかとも思いましたが、昨年満開の時期(GW初日)に訪れているのと混雑渋滞が懸念されたので断念。あれこれ悩んだ結果、咲き始めたかもしれない八溝山のシロヤシオを見に行くことにしました。
八溝山は茨城県と福島県の県境にあります。自動車で山頂直下まで登ることができるアクセスの良さと、秋から冬には富士山や東京スカイツリー、東北の山々を見渡す眺望の良さが魅力です。しかも春には多くの種類の花々を見ることができるため年に2~3回訪れていますが、5月に咲くシロヤシオは見たことがありません。今年の春は平年並みの気温で経過しているため、見頃は5月下旬と予想されます。但し昨日の暖気でぼちぼち開花しているのではないかと予想しました。

友部から1時間40分。標高1021mの八溝山頂に到着。まずは展望塔に登り景色を見ることにします。春霞で周囲の山はほとんど見ることができません。奥久慈の男体山ですらうっすらと霞んで、筑波山や日光連山は全く見えません。唯一見えたのは高原山から那須連山にかけてと会津駒ケ岳方面です。

那須の山々です。

左から茶臼岳、剣が峰、朝日岳、三本槍岳、赤面山、旭岳と連なります。那須連山は雲がかかっていることが多くここまで全体を見渡すのは久しぶりです。今年も夏か紅葉の時期に登ってみたい山の1つです。

那須の南の日留賀岳と帝釈山の間に見える雪山は会津駒ケ岳方面です。

中央の弥太郎山の左奥に大戸沢岳から会津駒ケ岳、右奥には三岩山にかけての白銀の山々が連なります。
今日の眺望はこの方面だけ。会津磐梯山は見えそうで見えませんでした。
眺望を楽しんでから、今日の目的であるシロヤシオの花を見に行きます。

山頂下の駐車場から高笹山方面へ向かいます。気持ち良い笹の尾根道が続きます。実はこの方面を歩くのは初めて。来年の春に向けてカタクリやイワウチワの花がどのあたりに咲くのかを調べるのも目的です。
高笹山方面への分岐を過ぎて入山方面へ少し進むと分岐点があり茗荷方面へ進みます。ここから先がシロヤシオの森となります。福島の山々というHPから引用します。
山頂から東側の矢祭町の茗荷川源流部を中心とした一帯(約44ha)は ブナやミズナラ、ヤマツツジ、ゴヨウツツジ(マツハダ)などの原生林がある。 原生林は40年以上前から地元の八溝山天然林保存会の人々によって保護され「八溝山天然林」として保護林の指定を受け、2001年には ふくしま遊歩道50選に選定されている。 なお、矢祭町の茗荷地区は柚子の産地として知られ、毎年11月頃には美しい黄色い実を収穫する様子をよく見かける。以上引用終わり

高笹山分岐を少し下り茗荷川源流部を見てきたので紹介します。周囲はブナやミズナラの原生林に覆われています。

茗荷方面へ少し下るとしばらくは尾根道が続きます。ブナの大木。

ゴヨウツツジ(シロヤシオ)の大木。上のほうはまだ蕾をつけていません。

少し下るとミツバツツジが姿を現します。ほとんど咲き始めですが、一本満開でした。

新緑の遊歩道をさらに下ります。

シロヤシオの花がちらほら咲き始めています。

あと2~3日で、これらの蕾が一斉に開花するのではないでしょうか。

シロヤシオの花をズーム。
さらに下ると茗荷川に辿り着くみたいですが今日は時間がありません。途中で引き返すことにします。機会があったらシロヤシオが満開の時期にゆっくり歩いてみたいです。森全体がシロヤシオの大木に包まれているので、一斉に開花するときっと絶景ではないでしょうか。

帰りに見かけたカエルさんです。

今日見かけた花をいくつか紹介。ユキザサです。

ヒゲネワチガイソウ。
尾根道ではワチガイソウも咲いていました。それから今日のもう一つの目的であるカタクリとイワウチワの位置もばっちり確認済です。

8時を過ぎてしまったので高尾へ戻ることにしました。旧参道入口方面への林道を下ります。林道の頭上で咲いている白い花は山桜でしょうか。

八溝山を下ってからは大田原へ向かって北上。林道を走り、南方で県道321号と合流する地点で見かけた白藤。
今日は水戸から大子にかけて山藤が満開でした。大田原市でも木々に絡みつく山藤が見事でした。

あまりにも鮮やかなので、那珂川にかかる橋で途中休憩です。


新緑と藤の彩りが鮮やかでした。

少雨の影響で、那珂川の水量が少なくなっています。
帰りは西那須野塩原ICから東北自動車道に乗り、11時30過ぎに高尾の自宅に到着しました。