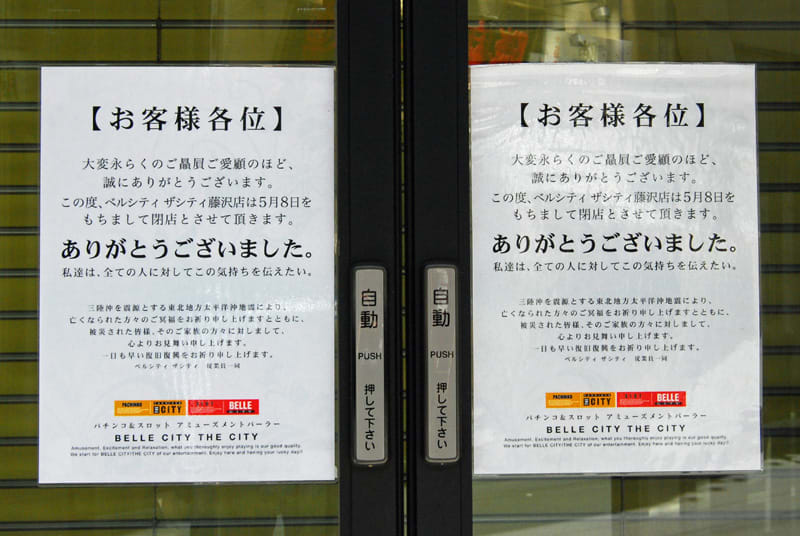庶民スーパーの前を過ぎて進むと、バス停「日ノ出町」があります。
現在の地図を眺めても、「日ノ出町」はありません。
家人が子供のころ、日ノ出町の銭湯に通った記憶があるというので、
資料を探しましたが見つかりませんでした。

バス停「日ノ出町」から少し進むと、右手に自動車整備工場があります。
この辺りから町工場のような建屋も増えてきます。

整備工場から右折して、ゆるい坂を下ると、明細地図の会社があります。
インターネットで簡単に地図検索が出来る時代ですが、
その昔はこうした明細地図がないと仕事にならない人が大勢いました。
私も古い明細地図を手に入れるためにここを訪ねたことがあります。