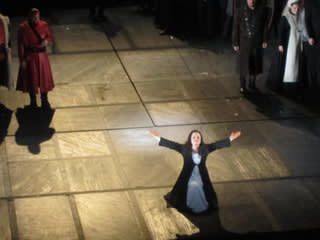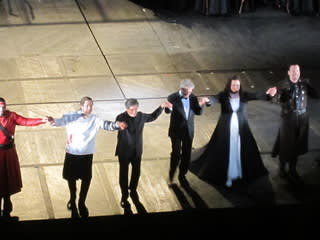2週間前の連休にドイツのベルリン、ハンブルグを駆け足で訪れたので、その備忘録を残しておきたいと思います。ベルリンは2年前にベルリンフィルを聴きに来ましたので、今回が2回目です。前回、時間の関係で廻れなかったペルガモン博物館を初めとしたいくつかの博物館・美術館にどうしても行っておきたかったのです。
【ペルガモン博物館】

スケールの大きさが想像以上で、本物の迫力が見るものを圧倒します。入場していきなり現れるペルガモンのゼウスの大祭壇(紀元前180~159)は、古代ギリシャのペルガモン(現トルコ)で発掘された遺跡がそのまま再現されています。まるごと展示してある壮大なスケールは大英博物館を凌ぐほどです。
(ゼウスの大祭壇)



この他にも「ミレトスの市場門」や古代バビロニアの「イシュタール門」などの展示は、本物ならではの無言のオーラが漂っています。私は、特に「イシュタール門」の青い色のレンガに魅かれ、しばし立ちすくんでしまいました。あまりの美しさに溜息がでます。
(ミレトスの市場門)

(イシュタール門)



【絵画館】
続いて、ベルリンフィルの本拠地フィルハーモニーの奥にある絵画館へ。


イタリア、オランダ、ドイツものの近代以前の絵画を中心に非常に充実した展示です。ボッティチェッリ、ホルバイン、レンブラントなどが充実していたのが嬉しいです。フェルメールもありました。



ペルガモン博物館の賑やかさに較べて、とても静かで空いているので、落ち着いて、ゆっくりすることができます。
2011年5月28日
【ペルガモン博物館】

スケールの大きさが想像以上で、本物の迫力が見るものを圧倒します。入場していきなり現れるペルガモンのゼウスの大祭壇(紀元前180~159)は、古代ギリシャのペルガモン(現トルコ)で発掘された遺跡がそのまま再現されています。まるごと展示してある壮大なスケールは大英博物館を凌ぐほどです。
(ゼウスの大祭壇)



この他にも「ミレトスの市場門」や古代バビロニアの「イシュタール門」などの展示は、本物ならではの無言のオーラが漂っています。私は、特に「イシュタール門」の青い色のレンガに魅かれ、しばし立ちすくんでしまいました。あまりの美しさに溜息がでます。
(ミレトスの市場門)

(イシュタール門)



【絵画館】
続いて、ベルリンフィルの本拠地フィルハーモニーの奥にある絵画館へ。


イタリア、オランダ、ドイツものの近代以前の絵画を中心に非常に充実した展示です。ボッティチェッリ、ホルバイン、レンブラントなどが充実していたのが嬉しいです。フェルメールもありました。



ペルガモン博物館の賑やかさに較べて、とても静かで空いているので、落ち着いて、ゆっくりすることができます。
2011年5月28日