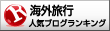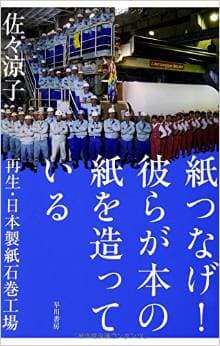映画好きな友人から勧められていたこの作品、ようやく鑑賞。
原作は1999年に出版されたベストセラー「the perks of being a wallflower」( 壁際の花であることの特典)。
原作者のスティーヴン・チョボスキーは数々の映画化のオファーに満足できず、
遂に自ら脚本・監督を手がけたといいます。
チャーリー(ローガン・ラーマン)はピッツバーグの高校の新入生。
自意識過剰で孤独な、本ばかり読んでいる冴えないタイプ。
中学の時の親友が自殺したこともあり、新しい友達を作れず、学校に馴染めないでいる。
そんな彼がひょんなことからパトリック(エズラ・ミラー)とサム(エマ・ワトソン)兄妹と
知り合い、彼らを通じて新しい世界、新しい友達と出会っていくのですが…
孤独なチャーリー、明るいパトリック、綺麗なサム、その三人が三人ともに
大きな秘密を抱えている。
チャーリーに至っては、彼自身も気づいていないという秘密もあり、
それが彼の精神疾患の原因となっている。
嫌な記憶を封鎖したいという本能によるものなのでしょうか。
その秘密が段々解かれてゆくというミステリー要素も含みながら
アメリカの高校の授業やカフェテリアやパーティなどを舞台に、話は展開してゆく。
彼らは親しくなり、ぶつかり合うことによって、その傷を暴露し、
それによって更に傷つきながらも成長していくのです。
その秘密というのが、同性愛であったり不倫であったり(高校生なのに)、性的虐待であったり
というところが、いかにもアメリカ的ではあるのですが
しかし傷つきやすく転びやすい青春期であるという点は、日本もアメリカも同じです。
若さゆえの繊細さ、痛さ、愚かさ。
初恋の甘酸っぱさ、それが壊れた時の切なさ、もどかしさ。
そういったみずみずしくもほろ苦い思いが、画面いっぱいから伝わってきます。
この作品の宣伝文句は「あの頃の自分と会える」というようなものだったような。
確かに、はるか昔の、頭でっかちであった高校生の頃の自分を思い出しました。
ただ残念なのは、自分はあの頃から、こんなに自分をさらけ出したり、
本気で友人とぶつかり合ったりはしなかったのではないかということ。
無論、この登場人物たちのような深刻な悩みはありませんでしたが
それなりに自分としては精一杯の悩みを抱えていた。
傍から見れば笑止千万なことであっても、当人にとっては世界のすべてであったりするのが
あの頃の悩みなのですから。
でも私は、この作品の中の連中のようにぶつけ合うことができただろうか。
そこまで本気の、裸の付き合いができなかったのではないか。
それは映画の話だからという言い方もできると思うし、
国民性の違いもあると思います。
ただ、やはりアメリカの青春映画である「ブレックファースト・クラブ」をかつて観た時にも
同じようなことを感じて、胸が少々痛んだことを思い出したのでした。
「ウォール・フラワー」 http://wallflower.gaga.ne.jp/