都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「生誕110年 東山魁夷展」 国立新美術館
国立新美術館
「生誕110年 東山魁夷展」
10/24~12/3

国立新美術館で開催中の「生誕110年 東山魁夷展」を見てきました。
日本各地やドイツ、北欧などを旅し、風景を描き続けた画家、東山魁夷(1908~1999)は、今年で生誕110年を迎えました。
それを期して行われているのが、「生誕110年 東山魁夷展」で、唐招提寺御影堂の障壁画を含む、全70件の作品が展示されていました。

「残照」 1947(昭和22)年 東京国立近代美術館
冒頭は、魁夷が33歳の時に描いた、「自然と形象 雪の谷間」でした。同名の「秋の山」や「早春の麦畑」などに連なる作品で、雪に覆われた渓谷を、どこか図像的に表していました。続くのが、1947年の第3回日展で特選を受けた「残照」で、千葉県の房総丘陵に位置する鹿野山から望んだ景色を俯瞰的に描いていました。彼方に太陽の沈む夕方の光景で、折り重なる九十九里谷の尾根が淡い光に包まれていました。まさにパノラマと言って良く、壮大な光景に、思わず深呼吸がしたくなるほどでした。
「たにま」は「自然の形象 雪の谷間」をより単純化した作品で、雪の谷間に流れる小川をトリミングするように描いていました。画面は継ぎ紙がなされている上、水流も加えられていて、琳派的な表現も伺うことが出来ました。
おそらく近代日本画で最も有名な道を表した「道」の舞台は、八戸の種差海岸に並走する県道でした。当初のスケッチでは馬や灯台を描いていたものの、本画の段階では省き、まさに一本の道のみを表しました。道は緩やかに登っていて、頂点で右へ曲がり、さらに奥へと連なっていました。あまりにもシンプルな光景ながらも、力強さも感じる作品で、魁夷の代表作と呼んでも良いかもしれません。
1962年、北欧へと旅立った魁夷は、同地の風景をスケッチしては、帰国後、数多くの連作を発表しました。そして「清澄な画風」(解説より)は大いに評価され、作品に青を多用したことから、「青の画家」と呼ばれるようになりました。
うち「映象」は水辺越しのシラカバの林を描いた作品で、水面に反射したシラカバは、まるで地中に根を張るように広がっていました。また「冬華」は雪に包まれ、氷に閉ざされた一本の大樹を正面から捉えていて、空には太陽が灯っていました。しかしながら実に寒々しい光景で、樹木は凍りつき、必死に耐えているようにも見えました。大自然の厳しさも感じられるかもしれません。
この一連の北欧の作品で最も惹かれたのが、フィンランドのクオピオの湖を表した「白夜光」でした。タイトルが示すように白夜を描いていて、湖は白銀の光を放っていました。先の「残照」と同様、雄大な自然をパノラマ的に示していて、無限の彼方にまで続くかのようでした。

「花明り」 1968(昭和43)年 株式会社大和証券グループ
京都も魁夷が積極的に描いたモチーフの1つでした。うち「京洛四季スケッチ」は、川端康成の勧めにより描いた連作で、京都の四季の景色を表していました。「祇園まつり」では、鉾の巡行の場面を捉えていて、祭りの華やいだ雰囲気が伝わってきました。

「晩鐘」 1971(昭和46)年 北澤美術館
魁夷は旅する画家でした。一連の京都シリーズを公表した翌年、ドイツ・オーストリアへと渡った魁夷は、現地の建物や街並みを描きました。「窓」では、窓を中心とした石造りの建物を正面から描いていて、「晩鐘」では、ドイツのフライブルクの大聖堂を表していました。雲の合間からは、さながら街を祝福するかのような淡い光が差し込んでいて、どことなく幻想的な光景が生み出されていました。
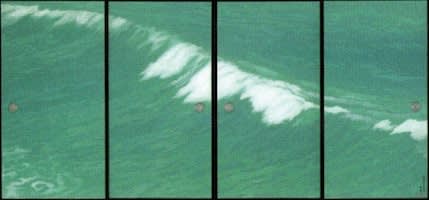
「御影堂障壁画 濤声」(部分) 1975(昭和50)年 唐招提寺
ハイライトを飾った「唐招提寺御影堂障壁画」は、全てケース無しの露出での展示でした。御影堂内部をほぼそのままに再現していて、正面から宸殿の間の「濤声」、次いで上段の間の「山雪」があり、桜の間の「黄山暁雲」、松の間の「楊州薫風」、梅の間の「桂林月宵」と続いていました。
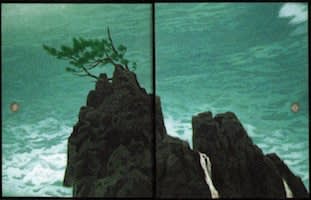
「御影堂障壁画 濤声」(部分) 1975(昭和50)年 唐招提寺
何よりも圧巻であるのは、冒頭の「濤声」で、エメラルドグリーンに染まった大海の広がる中、白波が右手上方より打ち寄せ、岩を洗い、また飛沫をあげながらも、細かに砕けては、静かに消えゆく光景を表していました。ともかく大変に美しく、臨場感のある作品で、展覧会のハイライトとしても過言ではありません。なお一連の障壁画は、2015年より始まった大修理のため、今後数年間は御影堂でも拝観することが叶いません。ほかの展示室とは異なり、暗がりの中、LEDでライトアップされた演出も効果的で、思わず見惚れてしまいました。
 「東山魁夷 青の風景/求龍堂」
「東山魁夷 青の風景/求龍堂」
ラストは1980年以降、晩年に制作した風景画の展示でした。中でも趣深いのは、最晩年、90歳の時の「有星」で、青く染まる夜の中、水辺越しに望む4本の杉を描いていました。空には星が輝くものの、水面に映り込むことはなく、物悲しいほどの静けさに満ちていました。魁夷の絶筆として知られています。
一部の作品に展示替えがあります。
「生誕110年 東山魁夷展」
前期:10月24日(水)~11月12日(月)
後期:11月14日(水)~12月3日(月)
本画の入れ替えは数点ですが、「京洛四季習作」と「京洛四季スケッチ」はかなりの数が入れ替わります。
最後に館内の状況です。今回はタイミング良く、平日の夕方前に行くことが出来ました。よって、思ったり賑わってはいたものの、特に並ぶこともなく、どの作品もスムーズに見られました。
ただし、先行した京都展(京都国立近代美術館。8/29~10/8。)は、中盤以降、かなり混み合ったと聞きました。東京でも、会期は約1ヶ月強に過ぎず、土日を中心に混みあうことも予想されます。現に11月3日には、一部の時間帯で入場規制もかかりました。夜間開館も狙い目となりそうです。

ぼんやりと魁夷の風景画を前にしていると、構図や表現云々ではなく、いつしか風景の中に吸い込まれている自分に気がつきました。見終えたあと、気持ちが晴れるような気がしたのが不思議でなりません。「国民的風景画家」と称されますが、あながち誇張とは思えませんでした。

12月3日まで開催されています。
「生誕110年 東山魁夷展」 国立新美術館(@NACT_PR)
会期:10月24日(水)~12月3日(月)
休館:火曜日。
時間:10:00~18:00
*毎週金・土曜日は20時まで開館。
*入館は閉館の30分前まで。
料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。
*11月23日(金・祝)、24日(土)、25日(日)は高校生無料観覧日。要学生証。
住所:港区六本木7-22-2
交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。
「生誕110年 東山魁夷展」
10/24~12/3

国立新美術館で開催中の「生誕110年 東山魁夷展」を見てきました。
日本各地やドイツ、北欧などを旅し、風景を描き続けた画家、東山魁夷(1908~1999)は、今年で生誕110年を迎えました。
それを期して行われているのが、「生誕110年 東山魁夷展」で、唐招提寺御影堂の障壁画を含む、全70件の作品が展示されていました。

「残照」 1947(昭和22)年 東京国立近代美術館
冒頭は、魁夷が33歳の時に描いた、「自然と形象 雪の谷間」でした。同名の「秋の山」や「早春の麦畑」などに連なる作品で、雪に覆われた渓谷を、どこか図像的に表していました。続くのが、1947年の第3回日展で特選を受けた「残照」で、千葉県の房総丘陵に位置する鹿野山から望んだ景色を俯瞰的に描いていました。彼方に太陽の沈む夕方の光景で、折り重なる九十九里谷の尾根が淡い光に包まれていました。まさにパノラマと言って良く、壮大な光景に、思わず深呼吸がしたくなるほどでした。
「たにま」は「自然の形象 雪の谷間」をより単純化した作品で、雪の谷間に流れる小川をトリミングするように描いていました。画面は継ぎ紙がなされている上、水流も加えられていて、琳派的な表現も伺うことが出来ました。
おそらく近代日本画で最も有名な道を表した「道」の舞台は、八戸の種差海岸に並走する県道でした。当初のスケッチでは馬や灯台を描いていたものの、本画の段階では省き、まさに一本の道のみを表しました。道は緩やかに登っていて、頂点で右へ曲がり、さらに奥へと連なっていました。あまりにもシンプルな光景ながらも、力強さも感じる作品で、魁夷の代表作と呼んでも良いかもしれません。
1962年、北欧へと旅立った魁夷は、同地の風景をスケッチしては、帰国後、数多くの連作を発表しました。そして「清澄な画風」(解説より)は大いに評価され、作品に青を多用したことから、「青の画家」と呼ばれるようになりました。
うち「映象」は水辺越しのシラカバの林を描いた作品で、水面に反射したシラカバは、まるで地中に根を張るように広がっていました。また「冬華」は雪に包まれ、氷に閉ざされた一本の大樹を正面から捉えていて、空には太陽が灯っていました。しかしながら実に寒々しい光景で、樹木は凍りつき、必死に耐えているようにも見えました。大自然の厳しさも感じられるかもしれません。
この一連の北欧の作品で最も惹かれたのが、フィンランドのクオピオの湖を表した「白夜光」でした。タイトルが示すように白夜を描いていて、湖は白銀の光を放っていました。先の「残照」と同様、雄大な自然をパノラマ的に示していて、無限の彼方にまで続くかのようでした。

「花明り」 1968(昭和43)年 株式会社大和証券グループ
京都も魁夷が積極的に描いたモチーフの1つでした。うち「京洛四季スケッチ」は、川端康成の勧めにより描いた連作で、京都の四季の景色を表していました。「祇園まつり」では、鉾の巡行の場面を捉えていて、祭りの華やいだ雰囲気が伝わってきました。

「晩鐘」 1971(昭和46)年 北澤美術館
魁夷は旅する画家でした。一連の京都シリーズを公表した翌年、ドイツ・オーストリアへと渡った魁夷は、現地の建物や街並みを描きました。「窓」では、窓を中心とした石造りの建物を正面から描いていて、「晩鐘」では、ドイツのフライブルクの大聖堂を表していました。雲の合間からは、さながら街を祝福するかのような淡い光が差し込んでいて、どことなく幻想的な光景が生み出されていました。
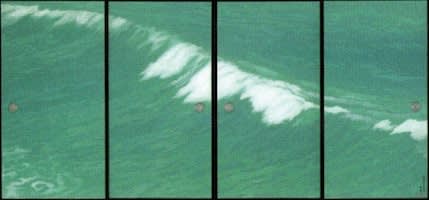
「御影堂障壁画 濤声」(部分) 1975(昭和50)年 唐招提寺
ハイライトを飾った「唐招提寺御影堂障壁画」は、全てケース無しの露出での展示でした。御影堂内部をほぼそのままに再現していて、正面から宸殿の間の「濤声」、次いで上段の間の「山雪」があり、桜の間の「黄山暁雲」、松の間の「楊州薫風」、梅の間の「桂林月宵」と続いていました。
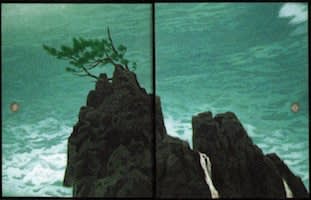
「御影堂障壁画 濤声」(部分) 1975(昭和50)年 唐招提寺
何よりも圧巻であるのは、冒頭の「濤声」で、エメラルドグリーンに染まった大海の広がる中、白波が右手上方より打ち寄せ、岩を洗い、また飛沫をあげながらも、細かに砕けては、静かに消えゆく光景を表していました。ともかく大変に美しく、臨場感のある作品で、展覧会のハイライトとしても過言ではありません。なお一連の障壁画は、2015年より始まった大修理のため、今後数年間は御影堂でも拝観することが叶いません。ほかの展示室とは異なり、暗がりの中、LEDでライトアップされた演出も効果的で、思わず見惚れてしまいました。
 「東山魁夷 青の風景/求龍堂」
「東山魁夷 青の風景/求龍堂」ラストは1980年以降、晩年に制作した風景画の展示でした。中でも趣深いのは、最晩年、90歳の時の「有星」で、青く染まる夜の中、水辺越しに望む4本の杉を描いていました。空には星が輝くものの、水面に映り込むことはなく、物悲しいほどの静けさに満ちていました。魁夷の絶筆として知られています。
一部の作品に展示替えがあります。
「生誕110年 東山魁夷展」
前期:10月24日(水)~11月12日(月)
後期:11月14日(水)~12月3日(月)
本画の入れ替えは数点ですが、「京洛四季習作」と「京洛四季スケッチ」はかなりの数が入れ替わります。
最後に館内の状況です。今回はタイミング良く、平日の夕方前に行くことが出来ました。よって、思ったり賑わってはいたものの、特に並ぶこともなく、どの作品もスムーズに見られました。
ただし、先行した京都展(京都国立近代美術館。8/29~10/8。)は、中盤以降、かなり混み合ったと聞きました。東京でも、会期は約1ヶ月強に過ぎず、土日を中心に混みあうことも予想されます。現に11月3日には、一部の時間帯で入場規制もかかりました。夜間開館も狙い目となりそうです。

ぼんやりと魁夷の風景画を前にしていると、構図や表現云々ではなく、いつしか風景の中に吸い込まれている自分に気がつきました。見終えたあと、気持ちが晴れるような気がしたのが不思議でなりません。「国民的風景画家」と称されますが、あながち誇張とは思えませんでした。

12月3日まで開催されています。
「生誕110年 東山魁夷展」 国立新美術館(@NACT_PR)
会期:10月24日(水)~12月3日(月)
休館:火曜日。
時間:10:00~18:00
*毎週金・土曜日は20時まで開館。
*入館は閉館の30分前まで。
料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。
*11月23日(金・祝)、24日(土)、25日(日)は高校生無料観覧日。要学生証。
住所:港区六本木7-22-2
交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )










