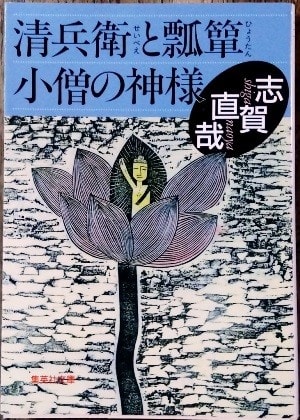
志賀直哉は「小僧の神様」なども含めて、偕成社版「少年少女現代日本文学全集」の「志賀直哉名作集」(1963年)で読んだはずだが、冒頭の写真は、息子が子どもだった頃に買い与えた志賀直哉「清兵衛と瓢箪 小僧の神様」(集英社文庫、1992年)の表紙カバーである。
2000年頃までは新潮、角川、小学館、集英社など各社が、毎年夏休み前になるとこぞって若者をターゲットに自社の文庫本から古典的な名作をピックアップした小冊子を配布するなど販売促進活動をしていたものだった。本書の表紙カバー見返しにも、「青春必読の1冊 集英社文庫ヤング・スタンダード」と称して、芥川「河童」「地獄変」から、漱石、鴎外、鏡花、宮沢賢治、川端、太宰、堀辰雄、梶井基次郎、中島敦らを経て、山川方夫「夏の葬列」、吉行淳之介「子供の領分」に至る40冊近い目録が載っている。しかし、いつの間にか若者は文庫本の販売対象ではなくなってしまったようだ。「笛吹けど踊らず」だったのだろう。
この集英社文庫も、表紙カバーのイラストが若者向けなだけでなく、本文も活字が大きく行間も広くとってあり読みやすい印象を与えている。もちろん新仮名遣い、新字体で、ルビ、語注までついている。巻頭には著者の若いころの写真などを納めた口絵ページがあり、巻末には解説の他にも著者の経歴や作品を網羅した年譜などをつけて若い読者に配慮しているのだが。
「小僧の神様」は、短編小説の名手として「小説の神様」といわれた志賀直哉中期の代表作だと解説はいう。
話の最後に作者(志賀)自身が登場して、小僧が立て替えてもらった握り寿司の代金を払いに行ったら、そこにはお稲荷さんの祠があったとかいう結末にしようと思ったが、小僧が気の毒なのでやめたと書いていたことが、中学生の頃に偕成社版で読んだときには強く印象に残った。こんな風に作者自身が小説の中に顔を出す小説を読んだのは初めての経験だったのだろう。その後柴田錬三郎「うろつき夜太」や、最近になって読んだ永井荷風「濹東綺譚」、高見順「故旧忘れ得べき」などにも作者自身が登場する場面があったから、小説作法として特別なことではなかったのだ。
集英社文庫版のもう一つの表題作である「清兵衛と瓢箪」は、かつて読んだときはあまり好い印象を残す小説ではなかった。幼い少年が骨董屋の店頭に置かれた一見何でもない瓢箪(ひょうたん)を気に入って購入するのだが、周囲の大人たちからは馬鹿にされる、しかしのちにその瓢箪に高値がつくといった内容だったと思う。そもそも瓢箪に価値があるなどという世界がぼくには当時も今も理解不能なので、そんな瓢箪に目利きかどうかなど主人公の少年の価値に何の関係もないではないか、という思いをぬぐえなかった。少年の審美眼を信じるというのも白樺派作家の「善意」なのだろうか。

今回、「網走まで」「母の死と新しい母」「正義派」「范の犯罪」「城の崎にて」などを読んだ。ついでに旺文社文庫版「網走まで 他16編」(昭和43年、手元にあったのは昭和52年13刷。上の写真)で「沓掛にて」を読んだ。
「沓掛」は現在の中軽井沢駅周辺の昭和30年ころまでの呼称である(沓掛時次郎!)。あのあたりの何が書いてあるのだろうと期待して読んだが、中身は芥川龍之介との思い出話で、彼の自殺を篠ノ井から沓掛に向かう信越線の車中で知ったという以外に「沓掛」はまったく登場しなかった。ぼくは志賀が「沓掛」で芥川と出会ったことがあり、そのときの思い出を回想するのだろうと期待したのだったが、期待外れだった。ただ、志賀の芥川に対する突き放したような見方が印象的だった。志賀が芥川を都会人、自分を田舎者と見ていたことも意外だった。
「城の崎にて」も城の崎のことはほとんど描かれていないし、「網走まで」も青森行きの列車で同席した母子が(どんな理由があってか)網走に向かっているというだけだった。小説の題名に地名をつけた志賀の真意が分からないが、「沓掛」「城の崎」「網走」に何か含意があったのだろうか。「沓掛にて」のテーマは芥川の死だが、彼の死に「沓掛」が係わりがあったと志賀は考えたのか。「城の崎にて」もテーマは「死」それ自体だが、誰かの死が城の崎に係わりでもあったのだろうか。「網走まで」は、ひょっとすると母親の夫は受刑者で母子は刑務所に面会にでも行く途中だったのだろうか。
今回読んだ志賀の小説の中で一番ぼくの印象に残ったのは「范の犯罪」である。偕成社版に入っていたかは覚えていないが、旺文社文庫には入っていた。編集者時代に、誰だったか法律家の随筆で「范の犯罪」に触れたものを読んだことがあった。
主人公は中国人の奇術師夫婦である。夫(范)が戸板の前に直立させた妻に向かってナイフを投げるという芸当を見せるのだが(ウィリアム・テル!)、ある時夫の投げたナイフが妻の喉にあたって妻は死んでしまう。裁判になり、夫に殺意があったか否かが争点になる。実は結婚直後に、妻が結婚前に交際のあった男との間の子を産んだため(死産だったが)、夫婦は結婚直後から不仲となり、夫はその事実を受け入れようとキリスト教の洗礼まで受けるが、心の安らぎを得られないでいたということを夫自身が告白する。殺意があったのかどうか、夫は自分自身でも分からないと告白する。
最後に裁判官が「無罪」と心証を得るところで話は終わるが、たとえ殺人で無罪だとしても、(重)過失致死罪の責任は免れないだろう。
その結論の当否よりも、「范の犯罪」では妻の不貞(この小説では結婚前のことだが)に対する主人公(=志賀)のこだわりが印象的である。「暗夜行路」はもっと直截に妻の不貞による出産という自分の出生の秘密(への疑惑)がテーマになっていた。
小津安二郎の映画に対する志賀直哉「暗夜行路」の影響は何人も指摘しているが(浜野保樹「小津安二郎」岩波新書ほか)、小津「風の中の牝鶏」の夫(佐野周二)の煩悶などは、「暗夜行路」というよりむしろ「范の犯罪」の影響の方が強いのではないか。最近読んだ佐古純一郎「家からの解放」(春秋社)では、そもそも「暗夜行路」の主人公時任健作が抱いた父子関係への疑念の脆弱さが厳しく批判されていたが。
集英社文庫版の最後のページには、「2002年8月27日(火)」という日付と下の息子のサインがあった。日付からして、夏休みの宿題の読書感想文を書かせるために読ませたのかもしれないが、小学校6年、12歳の息子には「范の犯罪」や「正義派」は無理だろう。「『小僧の神様』を読んでごらん」とちゃんと読書指導をしたうえで読ませただろうか。太宰治「新樹の言葉」のような感想は書いてなかった。
2025年1月23日 記









