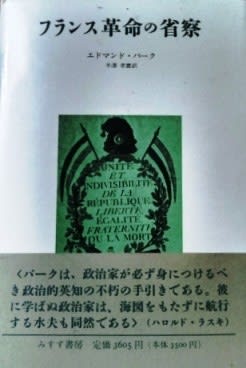昨日読み終えたバーク『フランス革命の省察』(半澤孝麿訳)の余滴を。
フランス革命によって成立した国民議会を口を極めて批判し、革命前の旧体制を支持するバークだが、何か所か、旧体制維持以外の可能性を示唆する記述もあった。
イギリスのコモン・ローによる漸進的な法的ルールの形成を肯定する記述については前に書いたが、さらに、「混合政体」の可能性および「中間項」の可能性についての記述があったことを思い出した。
バークは完全な民主政を批判する文脈で、「王政の専制と大衆の専制との中間に何物かがあるということを、この紳士連中(革命支持者たち)はかつて聞き及んだことはないのでしょうか。法によって方向づけられ、一国の偉大な世襲的財産と世襲的品位によって制御され平衡を保たれている王政――しかもこの二つながら、然るべき恒久機関を通して行動する民衆全体の理性と感情による健全な抑制を受けて再び制御されている王政――」のことを彼ら(革命支持派)は知らないのだろうか。・・・「ある国民が、そのような混合中庸の政府を手に入れる――否むしろ実際所有しているそうした政府をより堅固にする――こと」を自ら選択する人物がいないとでも言うのだろうかと述べている(半澤訳[以下同]157頁)。
ここでバークが述べている「混合政体」とは、当時のイギリスの憲法体制のことであり、「世襲的財産と・・・」は上院を、「恒久機関」は下院を意味すると訳者の注釈がついている(356頁)。
「国家をめぐる大部分の問題と同じく、ここ(※革命期のフランスにおける体制選択)にも中間項があります。・・・単純に絶対的破壊か改革無しの存続か、という選択肢以外に何か別物があるのです。・・・/立派な愛国者や真の政治家ならば、如何にすれば自らの国に現存する素材で最善が得られるかを常に考えるものです。保存しようとする気質と改善する能力とを合したものが、私にとっての真の政治家の基準です」と述べている(197頁)。
そして、諸国家の歴史の中では、特定の人々が偉大な精神的努力によって改善を行なうよう召命を受ける瞬間がある。しかしのそのような瞬間にも彼らは必ずしも適切な道具を持っているとは限らない。政治家が偉大な事業を行なうためには一つの力(職人が梃子と呼ぶもの)が必要であると述べている(同頁)。
ただし、バークがフランス革命期の「梃子」として挙げるものは(旧体制下のフランスの)修道院制度というのだから(同頁)、革命擁護派としては鼻白んでしまうのだが・・・。
本書の帯には「バークは、政治家が必ず身につけるべき政治的英知の不朽の手引きである。彼に学ばぬ政治家は、海図をもたずに航行する水夫も同然である」というハロルド・ラスキの言葉が記されている(※上の写真)。
本書を読み始めたころは、何でラスキはこんな本をこのように褒めたのだろうと訝しく思ったが、上のようなイギリス流の憲法体制、議会政治、コモン・ロー法体系についてのバークの言説に対する評価なのだろう。
2022年2月9日 追記