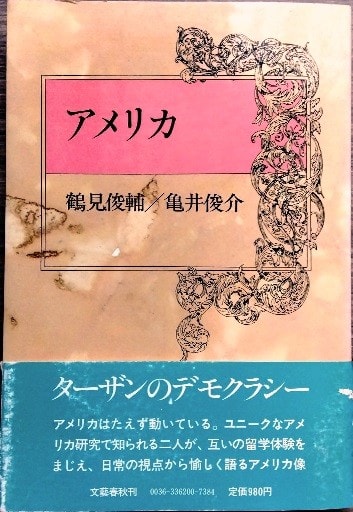鶴見俊輔・亀井俊介『アメリカ』(文芸春秋、1980年)を読んだ。980円で、発行者(社長?)は半藤一利となっている。
再読で、前回読んだのは1980年12月28日(日)、pm 2:34に読み終わったらしい。最終ページの余白にそう書いてあった。さらに「新幹線ひかり2号(下り)車中で。富士川通過から10分くらい。車窓には、年末のあわただしさも感じさせない、のどかな農村の風景。冬晴れ。」と万年筆で書き込みがある。時期からして、家内の実家への帰省の車中だろう。
裏表紙に「深みのある知米派対談」と題した朝日新聞の書評(12月8日付、無署名)が挟んであった。
対談というより、どちらかといえば亀井が聞き手となって鶴見の話を聞き出す感じで始まっているが、途中から亀井も元気になって自説を述べるようになる。
高田宏氏に対する謝辞が「あとがき」にあるところを見ると、あの懐かしい雑誌「エナジ―」(エッソかどこかが発行していた対談誌)が初出だったのかも。
植草甚一、石坂洋次郎、谷譲次(牧逸馬)らのアメリカ体験を評価し、東大を追放された(とは知らなかった!)ラフカディオ・ハーンの水脈の可能性を指摘するなど、鶴見の視点は独自である。
山本周五郎がサロイヤンの影響を受けていたこと(確かに二人とも主な舞台は周縁部=田舎である)、反軍演説で知られる斎藤隆夫がイェール大学出身で、その風貌とは裏腹に彼の中にはアメリカ魂がみられるという指摘なども(61頁)、なるほどと思わせる。
ジョン(中浜)万次郎、ジョセフ(浜田)彦蔵らの漂流民に日本のデモクラシーの可能性を見ようともする(41頁)。小田実あたりが「漂流民」的なアメリカ体験の最後だろう。
わが良心的兵役拒否の明石順三を、灯台社本部はその歴史から抹殺し、歪曲していると書いてあるが(113頁)、事実なのか。兵役拒否は輸血拒否などよりも重要な信仰の核心問題だと思うのだが、なぜ抹殺されなければならなかったのだろう。
フランクリンの俗物性や、シェーンと沓掛時次郎の対比、ターザンからスーパーマンまで、大衆文化についても多く語られているのだが、少なくとも鶴見は、基本的にはエスタブリッシュメントの側の日本人がみた、正統派の側のアメリカ文化論と読んだ。ホイットマンからプラグマティズムに至るアメリカ文化に関する鶴見の博識さはただならない。
父親(鶴見祐輔)の縁故でアメリカ東部のプレップ・スクールに留学し、その後ハーヴァード大学で学び、そのアメリカにおける「保護者」がアーサー・シュレジンジャー Jr. のお父さんであり!(61頁)、多くの日系人が強制収容されたにもかかわらず、捕虜交換船で帰国することができたという鶴見の経歴に由来するぼくの偏見かもしれないが。
彼はアメリカ(と父親)に対する「愛憎」についてどこかで語っていたが、その感情はどのように形成されたのか。アメリカへの「愛」は理解できるのだが、「憎」はどのようなものだったのか。
本書刊行の時点では、ウォーレスのような極右の人物が大統領になりかかったものの、危ういところで食い止められたが、その後トランプのような人間が実際に大統領になり、落選後も再起を図っているというアメリカの状況を、もし生きていたら鶴見はどう語るだろうか。
昨夜、NHKの Eテレ(2ch)で、ナパーム弾を開発したアメリカ人化学者のことをやっていた。あれが大量に使われたベトナム戦争の惨禍を知った後であるはずの1980年頃に、ぼくはアメリカに対して一体どのような感情をもって、鶴見や亀井の「アメリカもの」を読んでいたのだろうか。
2023年2月8日 記