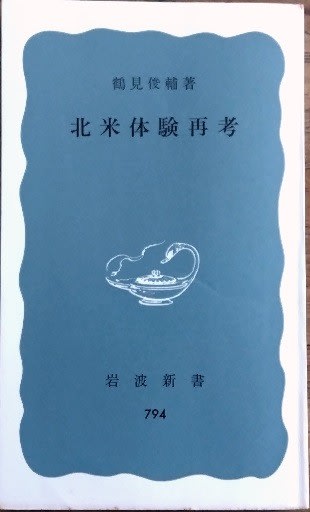鶴見俊輔『北米体験再考』(岩波新書、1971年)を読んだ。
最初に読んだのはいつだったのか、書き込みがないのでわからないが、傍線を引いたところが何か所かあるので、出版された頃に読んだのだろう。
「序章 ケムブリッジ」、「第1章 マシースン」、「第2章 スナイダー」、「第3章 フェザーストンとクーリーヴァ―」、「終章 岩国」、の4章からなる。
マシ―スンたちが何者か、どういう脈絡で並んでいるのか、まったく分からない。あとがきによると、本書は、2つの記録と3つの書評からなるというから、第1~3章が書評、その他が記録なのだろう。
「序章」では、19歳でハーヴァード大学最終学年だった(!)鶴見が、「無政府主義者」であることを申告しないで入国したとして移民法違反でFBIに逮捕され、勾留、裁判(陪審!)を経て、捕虜交換船で日本に送還された経緯(おそらく敵性国民だったことがほんとうの理由だろう)、帰国後召集逃れのために海軍に志願したものの結核で除隊し、戦後は進駐軍への協力を拒否して、ハーヴァード大学の同窓会名簿などを作っていたことが記される。
「米国ずきの私」と書いてあって(15頁)、鶴見のアメリカに対する基本的な感情がうかがえる。
「第1章 マシースン」は、マッカ―シーの赤狩りによって自殺に追い込まれたハーヴァード大学教員組合の創設者で、ニューディール左派、共産党シンパだったマシースンという人物の「アメリカの文芸復興」という本の書評の形をとりながら、入植から1940年代までのニューイングランド、ケンブリッジ周辺が語られる。
ヒューバーマン、スウィージー、ドライザー、ドルトン・トランボ(「ジョニーは戦場に行った」。「ローマの休日」も彼が匿名で脚本を書いたのではなかったか)、フランクファータら、懐かしい名前が登場する。赤狩り時代に、左翼からベトナム戦争擁護者に転向したスタインベックも登場する。中学時代に読んだ「エデンの東」「怒りの葡萄」で、ぼくはスタインベックのファンになったが、高校1、2年生の頃に、彼がベトナム戦争におけるアメリカの軍事行動を支持するエッセイを書いているのを毎日新聞だったかで読んで幻滅した。
ソロー、エマソン、ホイットマンにはまったく興味が湧かないないまま過ぎてしまった。鶴見が重視するメルヴィル「白鯨」にも興味はわかなかった。ただしアメリカにおける捕鯨の歴史が日本の開国をもたらしたことには興味がわく(67~9頁)。このテーマを取り上げた本はあるのだろうか。
ホイットマンがソローを評して、「そのへんにいるトム、ディック、ハリーといった普通の人を好きになれないというのが彼(ソロー)の欠点だと言い、自分(ホイットマン)は普通の人間の普通のくらしがそのまま偉大で英雄的なものであると思う」と言っているという文章に傍線が引いてあった(65頁)。1970年代に読んだときに気に入ったのだろう。今でも同感である。
「今日のソヴィエト・ロシアと今日の北米合州国、共産主義の理想を独裁者が腐敗させた形態と民主主義の理想を資本家が腐敗させた形態、その間に、あたらしく第三の道を見い出すことが必要だ。それは二つの社会形態の折衷ではなくて、個人と社会の双方に配慮するような、より十分な社会主義である」というマシースンの言葉にも傍線があった(71頁)。これも、今でもそう思う。
「第2章 スナイダー」のスナイダーもぼくの知らない人物だが、禅に興味を持って来日し鶴見とも親交のあった人物のようである。本章も彼の本の書評の形をとりながら、その本からは大きく外れてアメリカ・インディアン(本書の表記に従う)や黒人の側からみたアメリカが論じられる。鶴見はアメリカでインディアンにあったことがないとも書いてあった。
本章は、西部劇映画とインディアンの話から始まる。いわゆる「アメリカ」(鶴見はUSAのことを「北米合州国」と呼ぶ)の歴史はインディアンからの土地略奪の歴史であることは、鶴見を読まないでもぼくは理解していた。西部劇映画では常にインディアンが一方的に悪者にされているわけでもない。「ガンヒルの決闘」では保安官の妻はインディアン出身だったし、テレビ番組「ローン・レンジャー」では白人の主人公の斥候トントはインディアンだった(「キモサベエ」とか言っていたがどういう意味だったのか)。
インディアンの共同体の影響を受けて、自分たちを 部族(トライブ)と呼ぶ若者がこの頃から増加し、サンフランシスコで1万5千人、全米で200万人いるという(112頁)。これが今日に至るトライブ “tribe” (E・ブレイク「最小の結婚」など)の起源なのだろうか。
ジョン・ロックが「市民政府論」で示した “property” への権利、直訳すれば「財産権」だが、ロックに忠実に意訳すれば「各個人の “proper” なものへの権利」、すなわち各個人がその人らしく生きる権利=「幸福追求権」にも共感した。しかし、ロックがニュー・イングランドに入植した白人の権利を擁護して、インディアンが無駄に消尽している(“exhaust”)土地に対して、入植者が自らの手で開墾、改良し、耕作して収穫した作物(土地も)は、彼らに “proper” なものとして彼らに帰属すると書いていたのには到底納得できなかった。インディアンこそ、北米の土地やその果実を本来の趣旨に従って、エコロジカルに、生活=生きるために必要な範囲でのみ使用し収穫していたのである。
この章に関しては、鶴見にいわれるまでもなく、ぼくも理解していた。
「第3章 フェザーストン・・・」では、ベトナム戦争の当初の1966年頃は、キング牧師が戦争に対して沈黙していたこと(149頁)、日本からの北米留学生が、ジョン万次郎らの漂流民、新島襄らの脱藩浪士、小村寿太郎・金子堅太郎らの官僚から、裕福な実業家が二世へと変遷し、昭和に入ると官僚としての出世コースから外れたブルジョワ層の子弟へと変遷したという記述(165頁)が印象的である。ハーヴァードの同窓会名簿を作った経験から、実名も浮かんでいたのだろう。後に親米派の学者やジャーナリストになったフルブライト留学生などはどうか。
べ平連の招きで来日したフェザーストンが鶴見に語ったという「日本は、沖縄と沖縄以外の部分と、その二つにわかれている」という指摘も印象的である(137頁)。
本書は、60年代の黒人運動、ベトナム戦争に従軍した若い世代の中から新しい生活の流儀が生れてくるのではないかという予言によって結ばれる(186頁)。
それから60年、本書の刊行から50年が経って、はたして鶴見の予言は当たっていたのか。
ベトナムでベトナム人が日々殺されている現実を前にして、「ベトナムに平和を!」「殺すな!」との思いから、べ平連のデモの後ろを歩いていた学生時代のぼくは、鶴見俊輔のことをどう思っていたのだったか、今では思い出せない。小田実の「古今東西人間チョボチョボ主義」ほどには影響を受けなかったように思う。
ウクライナでウクライナ人が日々殺されている現在、ウクライナに平和を!、殺すな!の運動の指導者はいるのだろうか。
この本も、お別れである。
2023年2月21日 記