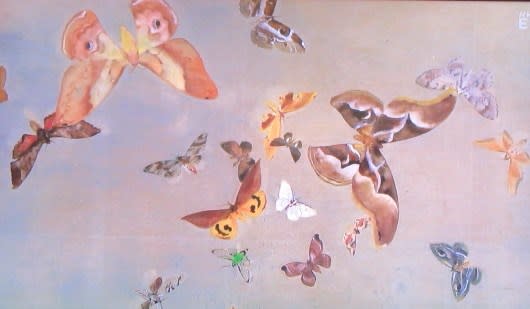モース博士といえば、知らない人はいない、大森貝塚。なんと来日3日目、横浜から東京へ向かう列車の窓からみつけたそうだ。しかし、本業の海洋動物学者としてのモースを知る人は少ないだろうし、江ノ島の漁師小屋を改造した実験室で、シャミセンガイの研究をしていたということを知る人はもっと少ないと思う。さらに、モースが明治時代の生活用品の優れたコレクターであることを知る人は、2013年にえど博で開催された特別展”明治の心/モースがみた庶民のくらし”を見た人を除いて一人もいないだろう(笑)。
モースの仕事場だった江ノ島と同じ藤沢市の日大生物資源科学部博物館で”モースと相模湾の生き物展”が開催されている。藤沢から小田急で江ノ島と反対方向、三つ目の駅”六合日大前”で降り、5分も歩けば、博物館に到着する。昨日、見学してきましたので紹介したいと思います。
モースが1877年に来日してから今年でちょうど140年目に当たるということで、企画されたようだ。展示構成は、第一部が”モースの日本滞在中に行った仕事の数々”、第二部が”モースのもたらしたもの”となっている。
第一部では、パネル展示を主体に、彼の研究者としての足跡が紹介される。おおよそ、こんな経歴である。生まれ故郷のメイン州ポートランドでは”学校嫌い”の少年時代を送り、大学も出ていない。ただ、貝のコレクションとその研究においては、学者たちに一目をおかれる存在であった。1859年、ハーバード大学博物館のアガシー教授から誘われ、学生助手に採用される。5年ほどの勤務の間、動物学一般の学問を身に付け、専門的には”生きる化石”として知られる腕足動物、とくに、シャミセン貝の研究を進めた。その後、シャミセン貝の分類やダーウィンの進化論(1859)の解釈などで、二人の間で論争があり、結局、博物館を辞める。
その後、講演活動に入ったが、ミシガン大学での聴講者に、のちにモースを東大の初代動物学教授に呼ぶことになる外山正一がいた。日本にシャミセン貝が豊富に生息していることを知り、二か年の期限付きで承諾したのだった。
研究紹介
研究材料のミドリシャミセンガイなど。
シャミセンガイの標本
石川千代松の”モース先生に就いて”。石川はモースの講義を筆記した”動物進化論”を出版し、ダーウィンの進化論を日本ではじめて紹介した。
第二部では、大森貝塚のビデオ紹介、相模湾の生物、明治時代の民具類(モースのコレクションではない)などが展示されている。モースは三度、来日して、研究の傍ら、各地を廻り、民具、陶器などの蒐集を行っている。75歳となったモースは、30年以上前の日記とスケッチをもとに、”Japan Day by Day/日本その日その日)”の執筆を開始。1917年に出版した。
Japan Day by Day
こうして、エドワード・シルヴェスター・モースは、わが国の動物学,考古学,民俗学などの基礎を作ったのである。

前二報の”とある博物館”とは、ここのことでした。
常設展示より



えのすいで生きたシャミセンガイを展示しているらしい。そのうち、訪ねてみよう。