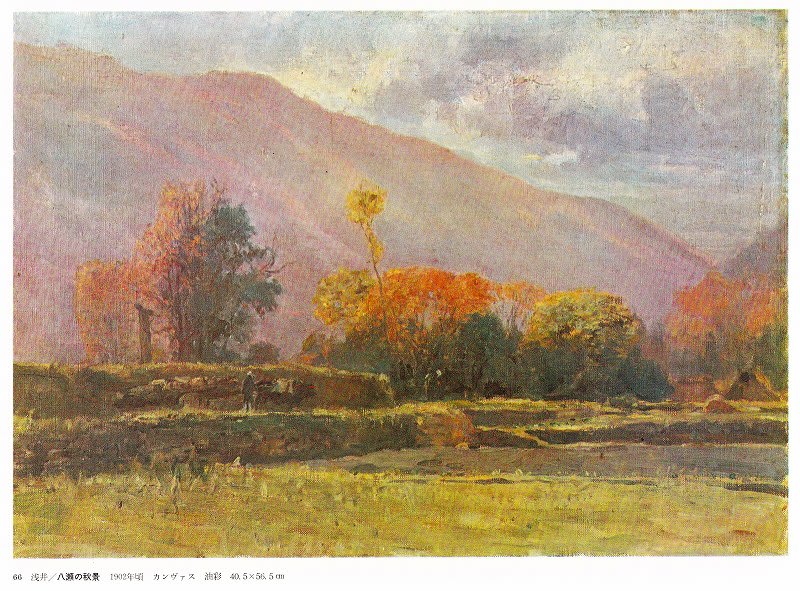この季節になると、シクラメンの鉢の花をよく見かける。そのけがれのない花に目を奪われる。白の花も気高い雰囲気をかもし出す。この花の名はどんな由来があるのか、つい気にかかる。ものの本によれば、ギリシャ語のSYCLE、まるいからきているとのことだ。花が円を描くように丸く咲くことに起因しているのだろうか。よく分からない。
ところが、豚の饅頭というのが、日本で早くつけられた名前らしい。こちらは、球根を豚の餌にすることから、sou blead豚のパンを日本語に訳して豚の饅頭なったのだという。花のゆたかな気品をみると、この名はいかにも似つかわしくない。
日はすでに暮れた。森は神秘的だったが
子牛の群れの足元に シクラメンの花が真紅に咲き乱れ、
一樹一樹つばらかに 樅の喬木が残照にてりはえていた。
『マルテの手記』を書いたオーストリアの詩人リルケは、シクラメンの花をにこんな風によみ込んでいる。シクラメンは冬に咲く花であるが、他の花と同じように日光を好む。