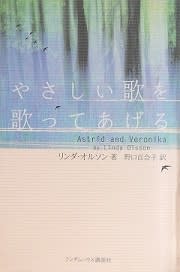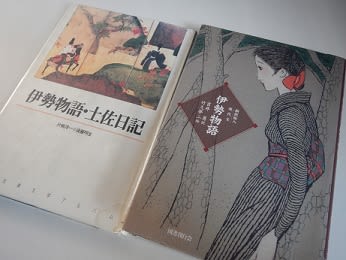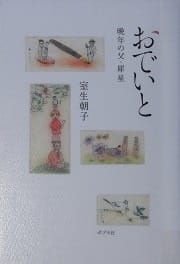

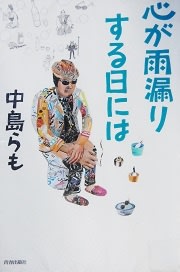
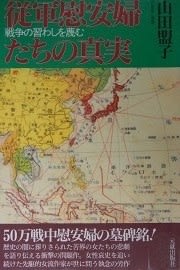
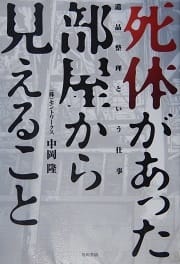
暮れから借りて、本日返却する本です。
この他、ガーデニング2冊、洋裁3冊、語学1冊。
画像の四冊は、おそらく正月番組にも飽きて退屈を感じる
・・・であろう三賀日の為に借りていましたが、
とても面白く、忙しい年末に気がつけば読み終えていました。
正月にふさわしくない内容の本ばかりに感じますが
平和な年末~正月、日米の関係や韓国のことを考える
ドキュメンタリー番組がいくつかTVでもあり、
あるいは、年明けには釜ヶ崎あいりん地区の変化や
人々をとらえた番組もありました。
こういう時期に、こういうことに触れるのもいいかもしれません。
おでいと:
室生犀星の娘、朝子さんが晩年の犀星を綴っています。
著者の主観・感情は、犀星ファンの私にとっては
最初はいらないもののようにも感じながら、
でも、読み進むにつれ、臨場感を感じたり
ワタシ自身の父親との関係に思いをはせたり
とても興味深く読みました。
タイトルの「おでいと」は、何か金沢の方言かと思いましたが
「おデート」を意味し、母の亡きあと仲のよい父と娘が
銀座に買い物に行くことを意味していました。
思い出バイヤー:
短編集で、それぞれ「幸福」や「価値観」について
ストレートに問いを投げかけます。
ラストは、予測のつく展開だったりしますが、
それでも、心に残るものがあるのは、分かっているつもりでも
自分自身の虚栄心・いやらしさがむき出しにされている気が
するからかもしれません。
でも、本当の幸せを得られず虚栄を張る側の・・・
弱さや影に暖かい目を向けてほしいとも思うのです。
キツイなぁ。。。という感じです。
心が雨漏りする日には:
著者の中島らもというひとの名前は、よく聞いて
知っている気になっていましたが、何一つ知らなかった。
この本は、うつになって、それを何とか乗り越えると
今度は躁症状が現れた自身の体験を語っています。
この本に対する感想は・・・あまり客観的に書けません。
が、一つだけ書けるとしたら著者自身が読み物としても
興味深く読める文章で語っているということの
すごさを感じたということでしょうか。
従軍慰安婦たちの真実:
私は、韓国を旅行したことがなく
ハワイに行ってもパールハーバーには近付きません。
気後れしてしまうからです。
従軍慰安婦については、日本人として信じたいように信じて
韓国人の反日感情に負けない嫌悪感を韓国の人や
韓国スターのファンなどに向ける人もいます。
・・・ですが、日本人だから悪いことをしないわけじゃない。
日本国内でも貧しい山村の女の子が村ぐるみで
斡旋されて赤線に売られていくようなことが、
実際に戦前あったことを見聞きし古い写真なども見ました。
近年、海外売春ツアーなどがあったことを考えると
ましてや戦時中、どこからどこまでが事実か、
何が本当か、わからないと思ってしまいます。
・・・が、それにしてもどのような状況下であれ
いったん当時の政府が「解決した。」と認めたことを
いつまでも蒸し返す韓国は、どうかと思いますが、
かといって、そういう事実があったことは
銅像を見せつけられる以前に、私たち一人一人が
過去の酷い記憶を恥とも思い、申し訳ないともおもうこと、
当事者の女性に同情を感じることは
女性としてはなおさら、当然のようにも思います。
それが、原爆に対するアメリカ人のように
日本人には感じられない。
韓国人に対する敬意も同情も感じられないから
韓国の人は、執拗に怒りを持ち続けるのではないでしょうか。
日頃も思っていたことですが、この本を読んで感じたのは
どこまでが時代の狂気だったのか、政府・軍に認められていたのか
それとも隊や個人の性癖・人間性の問題だったのか・・・
ということです。
いずれにしても、それで日本人全体に汚名を
かぶせる行為もひどいと思いますが、
それにもまして強く思うのは、
国粋主義的、あるいは排他(反日・反韓)的な考え方は
どちらも平和を守る考え方から
離れているのではないかということです。
反感、相手に対する警戒心は、不必要な
悲劇を呼ぶことは、過去の歴史からもわかります。
一人ひとりは、ただ「人間」であること
それを忘れたくないと思います。
(ちょっと、本からは離れてしました。)
死体があった部屋から見えること:
ショッキングなタイトルですが、
日本映画の『おくりびと』や
英・伊 合作の『おみおくりの作法』に通じるものが
あるのではないかと、手にしました。
サブタイトルの通り「遺品整理という仕事」・・・を
通して、さまざまな死や遺族の姿が取り上げられていて
ここ10年間に、近しい3組の老夫婦の死を
見届けたばかりの身としては、ツライ部分も
正直ありました。
周囲に近親者のいない還暦を迎える
自分たち夫婦のことは、いつも考えていましたが
逆に、覚悟・・・というか、開き直りというか
寝具の周りに、嘆いてくれる近親者がいない死に対して
抱いていた悲壮感が薄れました。
どんな風に生きても、家族を持っても
次代の人たちが生きるための世界であり
老いたらどんな形にせよ、消えていくしかない。
後のことは、準備も心配も暇つぶし程度に
考えている程度で。
何とかなるし、結局思い通りにはいかないもの。
・・・そんな風に今は感じます。
'みたよ♪' のポチ・・・で励まされます。
にほんブログ村