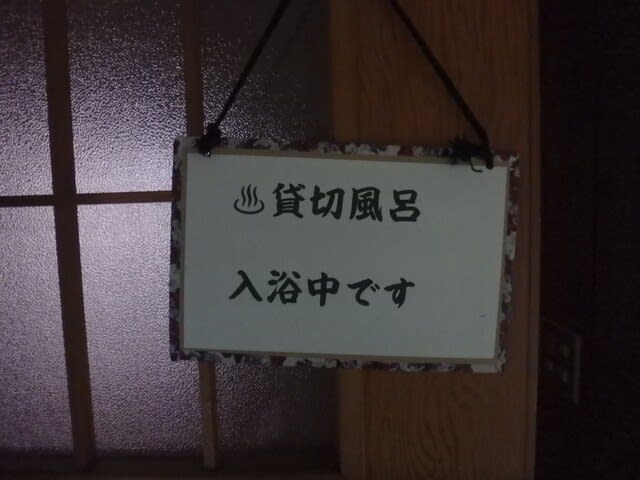※今回の記事に温泉は登場しません。悪しからず。
前回まで青森県の温泉を取り上げた記事が連続しており、まだまだこれからも続く予定ですが、ここでちょっと青森県と温泉から離れて小休止をしましょう。
日本のみならず世界各地の温泉をメインにたくさん取り上げている拙ブログですが、今までの閲覧数を確認してみますと、なぜか温泉以外の記事も多く閲覧されていることに気づきます。代表例は海外におけるレンタカー利用体験を How to 形式にして書き綴ったものですが、日本国内の地域交通ネタもちらほら閲覧されており、例えば北九州の「若戸渡船」を取り上げた
記事 は、公開から数年経った今でもコンスタントに読まれているようです。渡し船というノスタルジー溢れる前時代的な交通機関には、単なる船舶以上の魅力を感じ、しかも全国的に数が激減しているため、拙ブログをご覧くださるような旅好きな方の琴線を揺さぶるのでしょう。
かく言う私も「渡し船」と聞くと強い旅情と歴史的な情緒を感じ、機会があれば乗船してみたいと思っております。坂東太郎の異名を持つ利根川にもかつては多くの渡船が運航されていましたが、次々に架橋されることによって廃止に追い込まれ、現在では3ヶ所しか残っていないそうです。その中でも今回は唯一県境をまたぎ、しかもその航路が県道(主要地方道)に指定されているという珍しい特徴を持った「赤岩渡船」に乗ってまいりました。
赤岩渡船は埼玉県熊谷市と群馬県千代田町を結ぶ渡船で、その歴史は戦国時代にまで遡れるんだとか。具体的な場所は上地図をご覧ください。公共交通機関で当地までアクセスする場合、埼玉県側ですと熊谷駅から「葛和田」行路線バスに乗って終点で下車します。一方、群馬県側は館林駅から路線バス「館林・千代田線」に乗り、やはり終点の「赤岩渡船」で下車します。地図で位置を確認しますと、ちょうど熊谷と館林を直線で結んだ中間地点に赤岩渡船が位置していますね。先程航路が県道(主要地方道)に指定されていると申しましたが、その県道の名前は「埼玉県道・群馬県道83号熊谷館林線」。まさに両都市を結んでいるのです。
よく晴れた2021年11月初旬。私は熊谷駅に降り立ち、北口ロータリーから「葛和田」行路線バスに乗りこみました。
路線バスは真っ平らな関東平野を北上し、最終的には利根川の土手を乗り越えて堤防内に乗り入れ、約30分強で終点の「葛和田」に到着しました。バスは河原に立つ小さなプレハブ小屋の前で停まります。
「赤岩渡船」とは群馬県側の呼称であり、埼玉県側では渡船場が位置する地名を取って「葛和田の渡し」と呼んでいるようです。路線バスは数分で折り返して堤防を乗り越え、熊谷駅へと戻っていきました。
それにしても広い河原だこと。小さな頃から今に至るまで、私の生活圏の最寄りにある大きな川といえば多摩川なのですが、こんなに広い河原はありません。さすが日本屈指の大河だけありますね。
さて「葛和田」バス停前に立つこの小さな無人プレハブ小屋は、渡船を待つために設置されたもので、小屋の中には・・・
渡船の利用方法が説明されています。
これによれば、運航時間は4月1日~9月30日が8:30~17:00、10月1日~3月31日が8:30~16:30となっているのですが、特筆すべきは運賃。なんと無料なのです。赤岩渡船は県道に指定されているわけですが、一般的に県道を歩いたり車に乗ったり、あるいは県道に指定されている橋を渡る場合は、当たり前ですが誰でも無料ですよね。これと同じ感覚で、水上県道であるこの渡船も無料なのでしょう。
でも船を運航する以上はどうしても経費がかかります。この経費は県道の管理者である群馬県が負担しており、その運営を千代田町に委託しているんだそうです。このため、船頭さんは群馬県側におり、埼玉県側は常に無人です。群馬県側から客(というか通行者)を乗せた船は、渡し終えるとすぐに群馬県側へ帰ってしまいます。埼玉県側で船は待機していません。
埼玉県側から船に乗る場合、どうしたら良いのか・・・
小屋の前に黄色い旗が下りていますが・・・
掲揚ロープを引っ張って、このように黄色い旗を揚げるのです。そして、この場から対岸をひたすら注視し続けます。対岸の船頭さんがこの黄色い旗に気づくと、おもむろに船に乗り込んでこちらへ出発してくれますので、それを確認できたら、次の人のために旗を降ろします。
私が揚げた旗に気づいてくれたようなので、旗をおろして船着き場へ向かいました。遠くに赤城山がそびえ、上空をグライダーが気持ち良さそうに飛んでいます。この葛和田の乗り場一帯はグライダーの滑空場になっており、かなりの頻度で飛んでいました。後述しますが、どうやらこのグライダーの存在が渡船の存続と関係しているようです。
さて、100メートルほど歩いて船着き場に到着です。
渡し船がやってきました。
下船する人を優先し、下船が終わったら乗り込みます。そしてケースに納められている救命胴衣を自分で取り出して身に着けます。なお船に屋根はありません。
VIDEO
さようなら、葛和田渡船場。
気持ち良い船旅です。
ちょっとわかりにくいのですが、船から見える川底が非常に浅く、頑張れば歩けそうなほどでした。この浅さで操舵するのは、結構大変なのではないでしょうか。
離岸から4~5分で、あっという間に群馬県側の赤岩へ到着しました。
私を対岸へ渡してくれた「新千代田丸」。川舟らしいコンパクトでかわいらしい船体ですね。
なおこの船には自転車や原付バイクも載せることができるそうです。
逆光になっちゃいましたが、上画像の左側に写っているのが船頭さんの待機小屋です。群馬県側から乗船する場合は、旗など上げず、この小屋で船頭さんへ声を掛けるだけでOKです。
赤岩の船着場から目の前の階段を上がってすぐのところに、館林駅行きのバス停があります。本来でしたら、ここから路線バスで館林へ抜けたいところですが、便数がとても少なく、しかも私が訪ねた休日は更に減るため、事前に乗り継ぎ時刻を調べておかないと待ち惚けを食らうことになります。私もこの時は行き当たりばったりで出かけたため、次のバスまで1時間以上待つ必要がありました。どうしよう・・・
埼玉県側は「葛和田渡船場」という標識がちょこんと立っているだけでしたが、群馬県側の赤岩には灯篭のような飾りが立っていたり・・・
昭和30~50年頃の商店街を示した地図が掲示されていました。江戸時代の赤岩には既に100軒の商店があり、その後鉄道の開通によって河岸としての機能が低下しますが、戦後再び盛り返して、昭和40年代後半には約130軒の商店が甍を競ったそうです。でも現在残っている商店はわずか10軒ほど。
赤岩は歴史ある河岸として、かつては大いに栄えていたのでしょうね。しかし今ではそんなことが全く感じられないほど、農家が静かに軒を連ねるごくごく普通の集落です。
県道83号を歩いて千代田町役場方面へ向かってみることに。先程も申し上げましたが、「赤岩渡船」はこの県道83号の水上部分に当たるわけです。
赤岩の集落や県道83号線の沿道には、新しい架橋を求める看板や幟が立っていました。ここから一番近い橋は、上流側だと6〜7km先に架かる刀水橋、下流側だと4〜5km先の武蔵大橋まで橋が無いのですから、地元の方々は渡船ではなく、車で自由に行き来できる橋を求めるのはとても自然なことだと思います。
でも、そもそも架橋するほどの需要があるのか、どの自治体も財政難の今にあって莫大な建設費を要する架橋が認められるのか、などなど架橋には多くの問題が立ちはだかっているのでしょう。そして、上述したようにグライダー滑空場の存在も大きいのだとか。というのも、滑空場を他に移設できる見込みが無い現状で赤岩に橋を架けると、代替措置が無いまま滑空場を単純に閉鎖することになるためです。このような状況のため、架橋される見込みは立っていないそうです。
そんなことをスマホで調べながら歩いているうちに、千代田町の役場までたどり着いてしまいました。役場近くまで来たら、別のバス路線があるのではないかと予測していたのですが、ここまで来ても鉄道駅まで行けるバス路線は渡船場と同じであり、結局1時間待たなければならないため、面倒くさくなった私はタクシーを呼んで館林駅まで向かったのでした。
せっかくここまで来たのですから、近くの温泉で体を温めていきたいもの。
そこで館林駅から東武電車に乗った私は、羽生駅で途中下車し、羽生温泉「華のゆ」で掛け流しの良質な温泉を楽しませていただきました。ここを利用するのは5度目かな。いずれ拙ブログで取り上げたいと思っています。
<<参考>>
「赤岩渡船」 (千代田町公式サイト内)
.