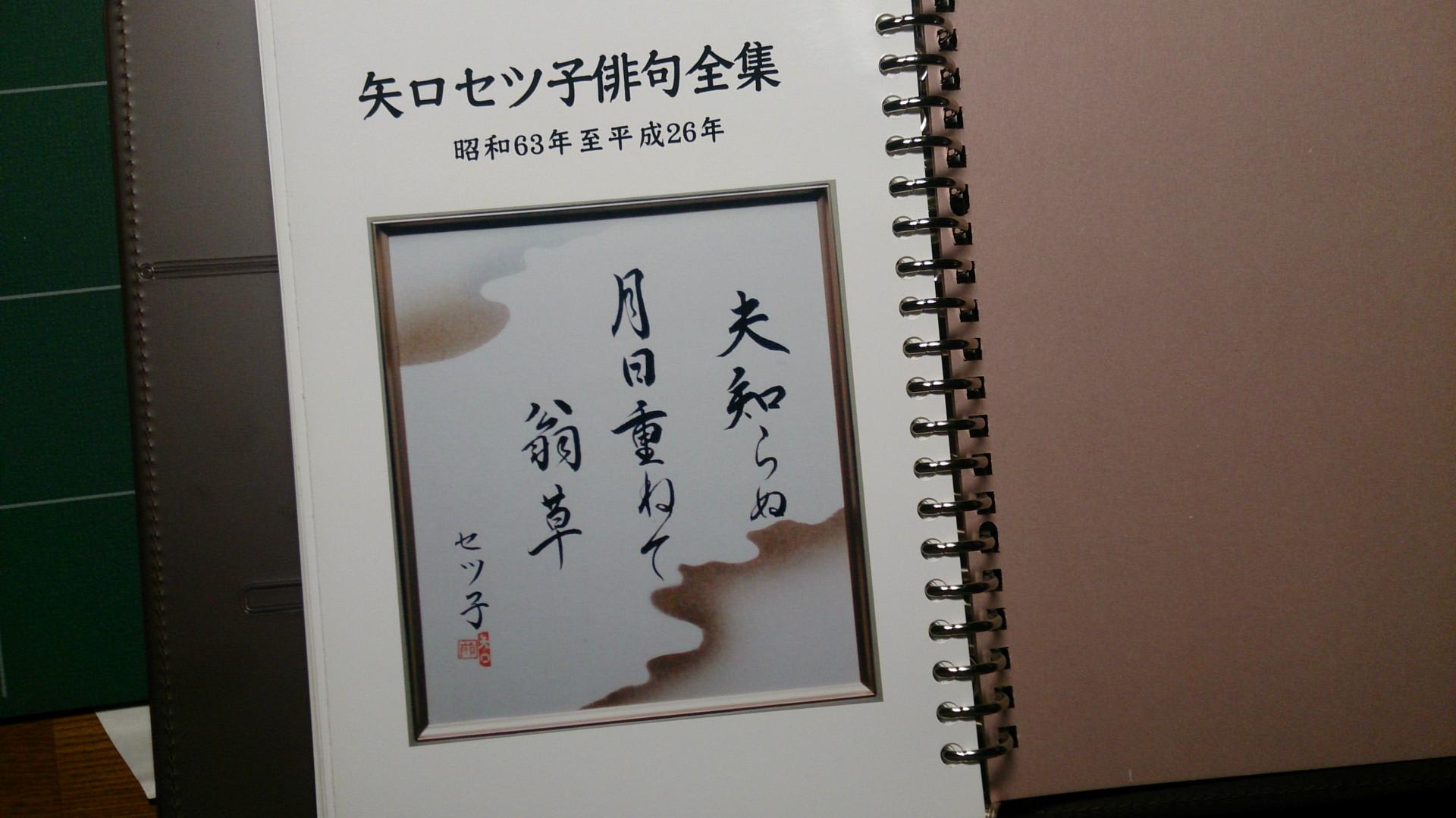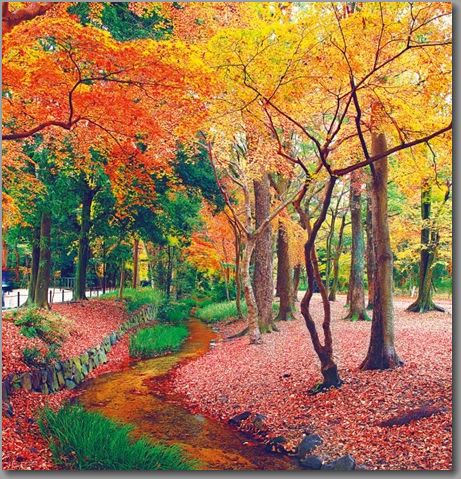好きな人と嫌いな人がいる。
何を以て人は人を好きになり、嫌いになるのだろう。
顔が嫌い、声が嫌い、話し方が嫌い、態度が嫌い、匂いが嫌い。
嫌いな要素はいくらでもありそうだ。
何を以て好きなのか。
顔か、声か、匂いか。
人は、特に子どもは母親が好きだろう。父親も少し好きかもしれない。
では、なぜ母親が好きなのか。
顔か?母親の顔がきれいだから好きなのか?そうではないだろう。
世の中、きれいな顔の母親ばかりではない。半分はきたない、いやいや普通の顔だろう。
どんな顔であれ、子どもにとって母親は世界で一番きれいに見えるかもしれない。
それは美醜ではない。
声か、これも子どもにとって母親の声が最もいい声に聞こえるに違いない。
人間にとって、いやいや全ての命にとって、自分以外の存在を心から好きになるのは、美醜やアイテムによってではないだろう。
自分の最も必要とする、自分にとって最も安全な存在を、心から愛し、全てが美しく見えるようにできているに違いない。
ということは、嫌いな人というのは、自分にとって必要ではない、安全を脅かす存在なのか。
しかし、我々には、当初嫌いと感じていた人が、あるきっかけで好きになる、ということもある。
それは、危険だと警戒していた人間が、よく知ってみると危険ではなかったというようなことかもしれない。
だとすれば、それは単によく知らなかっただけ、とも言えるだろう。意外とこれが多いのかもしれない。
悲しいのは、あれほど大事な存在だった母親が、自らの成長とともに、うっとうしくなったり、嫌いなところが次々増えてくることだろう。
必要な存在ではなくなったということか。
全ての人を好きになれればいい、などと考えたこともあったが、それは難しいことであるし、ある程度の年齢に達すると、その必要もないのかと思う。
好きな人を増やさないで、嫌いの人も増やさない方がいいのではないか。
今嫌いだと思っている人も、自分がその人のことを知らないだけかもしれない。
かといって、無理に知ろうと近づく必要もないように思う。
嫌いを増やさないために、近づかないこともあっていいのではないか。
元々友だちが少ないが、増やそうとも思わない。
その一方で、気の合う存在は、友だちを通り越して親戚、兄弟にまで近づく傾向にある。
広く浅くではなく、深く濃くというつながりを求めているようだ。
その存在は、顔がどうの声がどうの、話し方も態度も、匂いも、全く気にならなくなる。
ああ、自分にはこの人が必要なんだ。
何を以て人は人を好きになり、嫌いになるのだろう。
顔が嫌い、声が嫌い、話し方が嫌い、態度が嫌い、匂いが嫌い。
嫌いな要素はいくらでもありそうだ。
何を以て好きなのか。
顔か、声か、匂いか。
人は、特に子どもは母親が好きだろう。父親も少し好きかもしれない。
では、なぜ母親が好きなのか。
顔か?母親の顔がきれいだから好きなのか?そうではないだろう。
世の中、きれいな顔の母親ばかりではない。半分はきたない、いやいや普通の顔だろう。
どんな顔であれ、子どもにとって母親は世界で一番きれいに見えるかもしれない。
それは美醜ではない。
声か、これも子どもにとって母親の声が最もいい声に聞こえるに違いない。
人間にとって、いやいや全ての命にとって、自分以外の存在を心から好きになるのは、美醜やアイテムによってではないだろう。
自分の最も必要とする、自分にとって最も安全な存在を、心から愛し、全てが美しく見えるようにできているに違いない。
ということは、嫌いな人というのは、自分にとって必要ではない、安全を脅かす存在なのか。
しかし、我々には、当初嫌いと感じていた人が、あるきっかけで好きになる、ということもある。
それは、危険だと警戒していた人間が、よく知ってみると危険ではなかったというようなことかもしれない。
だとすれば、それは単によく知らなかっただけ、とも言えるだろう。意外とこれが多いのかもしれない。
悲しいのは、あれほど大事な存在だった母親が、自らの成長とともに、うっとうしくなったり、嫌いなところが次々増えてくることだろう。
必要な存在ではなくなったということか。
全ての人を好きになれればいい、などと考えたこともあったが、それは難しいことであるし、ある程度の年齢に達すると、その必要もないのかと思う。
好きな人を増やさないで、嫌いの人も増やさない方がいいのではないか。
今嫌いだと思っている人も、自分がその人のことを知らないだけかもしれない。
かといって、無理に知ろうと近づく必要もないように思う。
嫌いを増やさないために、近づかないこともあっていいのではないか。
元々友だちが少ないが、増やそうとも思わない。
その一方で、気の合う存在は、友だちを通り越して親戚、兄弟にまで近づく傾向にある。
広く浅くではなく、深く濃くというつながりを求めているようだ。
その存在は、顔がどうの声がどうの、話し方も態度も、匂いも、全く気にならなくなる。
ああ、自分にはこの人が必要なんだ。