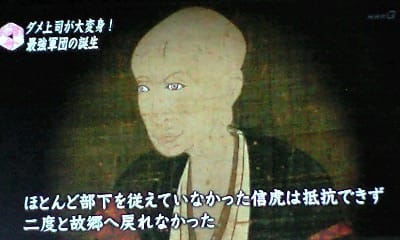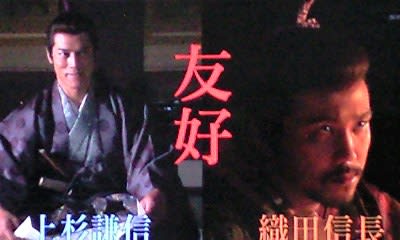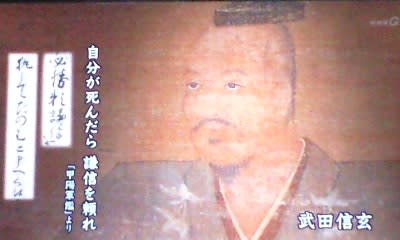■歴史秘話ヒストリア
しばらく予録したまま放っておいた番組をちょこちょこと見てみた。
大河ドラマ「軍師 官兵衛」つながりで、戦国時代に的を絞って見たら、当時の武将の姿がよりリアルに見えてくる。
■名作選 「魔王が棲(す)む魅惑の城~最新研究!織田信長 美しき城づくり~」
織田がつくった3つの城のビックリなしかけと、謎について。
土地に思い入れを持つよりも、目標に合わせて城を移す効率重視。
「天下布武」天下を武力で統一する、という意。

【那古野城】
【清洲城】信長22歳


平地で水に弱かった。
ふつうは防御のためくねくねにするところを、城までまっすぐな「大手道」が通る。

道の左右に家臣の屋敷を作り、殿は頂上てっぺん。上下関係をヴィジュアル化した。
【小牧城】信長30歳

小牧山に「城下町」の元祖を築いた。
城下町はそのまま、現代の街づくりに生かされているため、近代都市のルーツだった。
【岐阜城】信長34歳


濃尾平野が一望できる。
地下通路など、館群は迷路のようなつくりで、多くの客が招かれた→接待で味方を増やす意図。
12~15歳の家臣の息子を身近に置いて、主君を守るよう教育した。
【安土城】


八角形? 天主は7階建て30m。後の「天守閣」のさきがけ。当時は水に囲まれていた。


湖周辺には、ほかに3つの城を築き、1つが攻められたら、ほかの3つから援軍が送れる。
安土城が現存したのはたった3年。
信長の遺志は秀吉により「大阪城」に受け継がれている。


琵琶湖に「動く城」のごとき巨船を造らせた。
●盂蘭盆会のライトアップショー

「本能寺の変」の1年前、ひとつの催しがひらかれた。
色とりどりの提灯、松明で、あたりは真昼のように明るかったという(宣教師ルイス・フロイス「日本史」より
しばらく予録したまま放っておいた番組をちょこちょこと見てみた。
大河ドラマ「軍師 官兵衛」つながりで、戦国時代に的を絞って見たら、当時の武将の姿がよりリアルに見えてくる。
■名作選 「魔王が棲(す)む魅惑の城~最新研究!織田信長 美しき城づくり~」
織田がつくった3つの城のビックリなしかけと、謎について。
土地に思い入れを持つよりも、目標に合わせて城を移す効率重視。
「天下布武」天下を武力で統一する、という意。

【那古野城】
【清洲城】信長22歳


平地で水に弱かった。
ふつうは防御のためくねくねにするところを、城までまっすぐな「大手道」が通る。

道の左右に家臣の屋敷を作り、殿は頂上てっぺん。上下関係をヴィジュアル化した。
【小牧城】信長30歳

小牧山に「城下町」の元祖を築いた。
城下町はそのまま、現代の街づくりに生かされているため、近代都市のルーツだった。
【岐阜城】信長34歳


濃尾平野が一望できる。
地下通路など、館群は迷路のようなつくりで、多くの客が招かれた→接待で味方を増やす意図。
12~15歳の家臣の息子を身近に置いて、主君を守るよう教育した。
【安土城】


八角形? 天主は7階建て30m。後の「天守閣」のさきがけ。当時は水に囲まれていた。


湖周辺には、ほかに3つの城を築き、1つが攻められたら、ほかの3つから援軍が送れる。
安土城が現存したのはたった3年。
信長の遺志は秀吉により「大阪城」に受け継がれている。


琵琶湖に「動く城」のごとき巨船を造らせた。
●盂蘭盆会のライトアップショー

「本能寺の変」の1年前、ひとつの催しがひらかれた。
色とりどりの提灯、松明で、あたりは真昼のように明るかったという(宣教師ルイス・フロイス「日本史」より





























 の扱いにも長けていた。
の扱いにも長けていた。