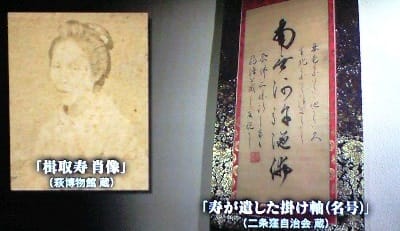■あいつぐ自然災害 あなたは逃げられますか? @週刊ニュース深読み
“70年以内に、首都圏内で直下型地震が起きる確率は30%”





印刷・配送費に約20億4000万円かかった。有料で他地域にも配布可能
この冊子の元になったのはスイスの「民間防衛」

 今回の栃木県の例
今回の栃木県の例


あらゆる避難指示は出ていた


ハザードマップは2009年に作成してあった


1mの浸水と言われてもピンと来ない/実際の浸水範囲とほぼ同じだった
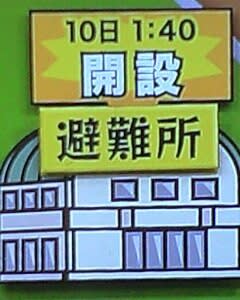

ヘリコプターは40機出動+ボートも出して3000人体勢で救出活動

逆に言えば、実際は「逃げ遅れた」「逃げなかった」人たちで、助かったのは奇跡的な偶然が重なったから
 昼間だったこと(大雨は真夜中に強くなることが多い
昼間だったこと(大雨は真夜中に強くなることが多い
 風が弱かったこと(風が強いとヘリは飛べない
風が弱かったこと(風が強いとヘリは飛べない
 堤防が4mと比較的低かったこと(高いと、逆に決壊した時の威力が大きい
堤防が4mと比較的低かったこと(高いと、逆に決壊した時の威力が大きい
 河川の名前などから分かる、その土地の歴史
河川の名前などから分かる、その土地の歴史
例:
荒川:昔、人が整備した(『ブラタモリ』でもゆってたような? 文字通り荒い川
天竜川:竜が暴れるほどの川であるという意味
 なぜ逃げないのか「正常性バイアス」
なぜ逃げないのか「正常性バイアス」

バイアスとは「偏見」の意味。
堤防などで、ある程度守られている現代。
昔は、大雨が降れば、川の様子を見に行ったり、土嚢を積んだりして対処していた。
アナウンサーも「緊迫感をもって呼びかけるように」と指導されていても、
大雨警報がきても、なぜかピンと来ない、逃げないのには心理的な「人間の本能」が作用しているという。
 「私は大丈夫」という理由
「私は大丈夫」という理由

高齢者に多い。鬼怒川は60年前にも氾濫しているが、今は堤防も整備したし、
経験値が逆の方向に作用するケース。

決壊した所からは離れている、川からウチは遠いからという理由(私の近所のおばちゃんも自信たっぷりにこうゆってた


ここまではまだ水が来ていないから大丈夫、など
「人には、危険だと思いたくない。逃げるなんて面倒だ、という心理が働く。
逃げて、何もなかった時に恥ずかしいなど。普段通りにしていたいと思う。
また、他人事だと思い、自分に不幸がふりかかると考えたくない。
しかし、そもそも災害とは、一生に一度あるかないかのこと。
このバイアスの意識を取り払うことがとても大事。命が助かるか、助からないかの問題」
 脱!正常性バイアスの取り組み例
脱!正常性バイアスの取り組み例


釜石市の子どもたちは、東日本大震災の際、自ら率先して逃げて助かった
「子どもは、教えられたことを純粋に実行するという“正常性バイアス”がまだ作られる前の段階。
子どものうちから、防災訓練をして、“疑似体験”させることで、
日常的に家庭でも話し合う機会を作る環境にすることで、大人も逃げるようになる」
 歌と体操なども作って、子どもにPRした
歌と体操なども作って、子どもにPRした


湘南に住んでいる川島さんは、東日本大震災の時、誰も逃げようとしなかったことを教訓にした。
 三条市の「逃げどきマップ」
三条市の「逃げどきマップ」



メートルではなく、具体的に「2階以上」などと書いて分かりやすくした
 ポイント1:“危険”をイメージさせる
ポイント1:“危険”をイメージさせる
 ポイント2:“行動”をイメージさせる
ポイント2:“行動”をイメージさせる


この取り組みのおかげで、死者を減らすことが出来た。


FAXからのアイデア
「もっと情報をピンポイントで出したらどうか」
 まとめ
まとめ
1.自分がどんな環境に住んでいるか、住民同士、ネットなどで情報を共有する。
2.説明するメディア、市区町村も、丁寧に、具体的に。説明会を開くなどして、他人事を「我が事」にする。
3.こうした取り組みがさかんな所は、実は、過去に酷い災害に遭った場所。経験を生かしている。
4.一人暮らしでも、家族があっても、助け合う精神「共助」が必要。
5.高齢者はとくにネットなどから情報をとるのは難しい。若者の助けが必要。
6.どれも「地域力」。行政だけではムリ。避難勧告の出し遅れの例もある。必ず出るとは限らない。
「河川課」というのは都道府県にしかない(?
「情報には“なさけ”という文字が入っている。人のココロに訴える具体性が必要。
情報は万能ではない。あらかじめ、早めに逃げる。
避難所に行って、何もなかったら“良かったね”と言える意識」
「情報には、2つの意味がある。1.インフォメーション と、2.インテリジェンス(知恵)」
「災害は繰り返す。自分が住んでいる地域の歴史、危険性(低地か、川に近いか、山に近いか、火山に近いかなど)を知ること」
“70年以内に、首都圏内で直下型地震が起きる確率は30%”





印刷・配送費に約20億4000万円かかった。有料で他地域にも配布可能
この冊子の元になったのはスイスの「民間防衛」

 今回の栃木県の例
今回の栃木県の例

あらゆる避難指示は出ていた


ハザードマップは2009年に作成してあった


1mの浸水と言われてもピンと来ない/実際の浸水範囲とほぼ同じだった
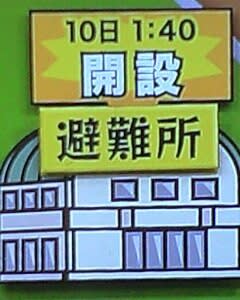

ヘリコプターは40機出動+ボートも出して3000人体勢で救出活動

逆に言えば、実際は「逃げ遅れた」「逃げなかった」人たちで、助かったのは奇跡的な偶然が重なったから
 昼間だったこと(大雨は真夜中に強くなることが多い
昼間だったこと(大雨は真夜中に強くなることが多い 風が弱かったこと(風が強いとヘリは飛べない
風が弱かったこと(風が強いとヘリは飛べない 堤防が4mと比較的低かったこと(高いと、逆に決壊した時の威力が大きい
堤防が4mと比較的低かったこと(高いと、逆に決壊した時の威力が大きい 河川の名前などから分かる、その土地の歴史
河川の名前などから分かる、その土地の歴史例:
荒川:昔、人が整備した(『ブラタモリ』でもゆってたような? 文字通り荒い川
天竜川:竜が暴れるほどの川であるという意味
 なぜ逃げないのか「正常性バイアス」
なぜ逃げないのか「正常性バイアス」
バイアスとは「偏見」の意味。
堤防などで、ある程度守られている現代。
昔は、大雨が降れば、川の様子を見に行ったり、土嚢を積んだりして対処していた。
アナウンサーも「緊迫感をもって呼びかけるように」と指導されていても、
大雨警報がきても、なぜかピンと来ない、逃げないのには心理的な「人間の本能」が作用しているという。
 「私は大丈夫」という理由
「私は大丈夫」という理由
高齢者に多い。鬼怒川は60年前にも氾濫しているが、今は堤防も整備したし、
経験値が逆の方向に作用するケース。

決壊した所からは離れている、川からウチは遠いからという理由(私の近所のおばちゃんも自信たっぷりにこうゆってた



ここまではまだ水が来ていないから大丈夫、など
「人には、危険だと思いたくない。逃げるなんて面倒だ、という心理が働く。
逃げて、何もなかった時に恥ずかしいなど。普段通りにしていたいと思う。
また、他人事だと思い、自分に不幸がふりかかると考えたくない。
しかし、そもそも災害とは、一生に一度あるかないかのこと。
このバイアスの意識を取り払うことがとても大事。命が助かるか、助からないかの問題」
 脱!正常性バイアスの取り組み例
脱!正常性バイアスの取り組み例

釜石市の子どもたちは、東日本大震災の際、自ら率先して逃げて助かった
「子どもは、教えられたことを純粋に実行するという“正常性バイアス”がまだ作られる前の段階。
子どものうちから、防災訓練をして、“疑似体験”させることで、
日常的に家庭でも話し合う機会を作る環境にすることで、大人も逃げるようになる」
 歌と体操なども作って、子どもにPRした
歌と体操なども作って、子どもにPRした

湘南に住んでいる川島さんは、東日本大震災の時、誰も逃げようとしなかったことを教訓にした。
 三条市の「逃げどきマップ」
三条市の「逃げどきマップ」


メートルではなく、具体的に「2階以上」などと書いて分かりやすくした
 ポイント1:“危険”をイメージさせる
ポイント1:“危険”をイメージさせる ポイント2:“行動”をイメージさせる
ポイント2:“行動”をイメージさせる

この取り組みのおかげで、死者を減らすことが出来た。


FAXからのアイデア
「もっと情報をピンポイントで出したらどうか」
 まとめ
まとめ1.自分がどんな環境に住んでいるか、住民同士、ネットなどで情報を共有する。
2.説明するメディア、市区町村も、丁寧に、具体的に。説明会を開くなどして、他人事を「我が事」にする。
3.こうした取り組みがさかんな所は、実は、過去に酷い災害に遭った場所。経験を生かしている。
4.一人暮らしでも、家族があっても、助け合う精神「共助」が必要。
5.高齢者はとくにネットなどから情報をとるのは難しい。若者の助けが必要。
6.どれも「地域力」。行政だけではムリ。避難勧告の出し遅れの例もある。必ず出るとは限らない。
「河川課」というのは都道府県にしかない(?
「情報には“なさけ”という文字が入っている。人のココロに訴える具体性が必要。
情報は万能ではない。あらかじめ、早めに逃げる。
避難所に行って、何もなかったら“良かったね”と言える意識」
「情報には、2つの意味がある。1.インフォメーション と、2.インテリジェンス(知恵)」
「災害は繰り返す。自分が住んでいる地域の歴史、危険性(低地か、川に近いか、山に近いか、火山に近いかなど)を知ること」










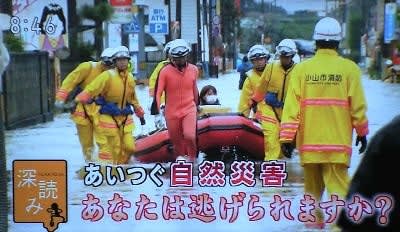

 状態メモ
状態メモ