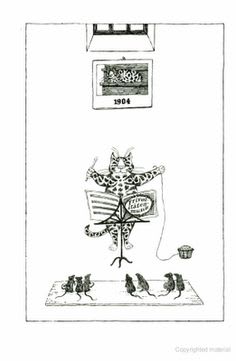■
『カリブー 極北の旅人』(新潮社)
星野道夫/著
※
「作家別」カテゴリーに追加しました。
「浅き川も深く渡れ」
(小学校の卒業アルバムに記した言葉『世話尽』から引用)
早世してしまう人は、人生の早い段階から早熟しているといつも思う。
まるで無意識に自らの命の時間を知っているかのように。
本書もきっとこれまでの総集編かなと思っていたら、
前回の
『未来への地図 新しい一歩を踏み出すあなたに』(朝日出版社)同様
また新たな感動をもらった。
「カリブーの写真集を、本当にいい形でまとめたい。
自分がつくる本の中で、これほど大切な本は後にも先にもないだろう。
写真家が1冊の本をつくるために生きているのなら、僕の場合はこの1冊に違いない。」
本人も言っている通り、人生で1冊作れるかどうかの写真集。
読者にとっても人生で1冊出逢えるか、出逢えないか、もし、出逢えても、
そこに書いてある文章、写真からのメッセージが理解できるかできないか。
これまで何度も読んだ一節でさえ、写真との組み合わせ、本の装幀、サイズなどで、印象がガラリと変わる。
本書は横に長い大型本で、2ページにわたっている写真が2枚の別のものであっても、
まるで山や地平線がつながっているように見える自然な工夫がほどこされている。
星野さんが一生追い続けた「カリブー」。
その生態はまだまだ謎だろうけど、長年の経験によって積み重ねられた知識は相当なもので、
彼らの生活、一生がなんとなく見えてきた気がした。
カリブーに関する日誌の抜粋が後半に収録されている。
著書として意識して書いた文章とはまた違った。星野さんの生の声が聞けた気がした。
1枚の写真を撮るのに、どれだけの時間、費用、人脈(!)、偶然、運が重なっていることか!
カリブーの集団を探したり、追ったり、空撮したりするための乗り物の種類だけでも多種多様。
もちろんカメラも、その瞬間、瞬間で選んで、いろいろ使い分け、
光や影の加減なども考慮していることが日誌に書かれていて、やっぱりプロの写真家なんだなあと改めて思った。
と、同時に、仕事とは分けて、アラスカという地にとり憑かれた1人の人間としての素直な感動、
失敗からも学ぶ姿勢を忘れない様子も心を打つ。
写真集はやっぱり大型本で観るのがイイ。
買うには高価だから、図書館で借りられるのは本当に有り難い/礼
こんなに果てしなく広大な土地が、同じ地球にあるものかとフシギ。
ついつい吸い込まれて、写真の中の足元の地衣類の感触を感じ、遠くの山、地平線を眺めて、
冷たい風を星野さんとともに感じることができる。

カリブーの母子が、川を泳ぐ姿を見れば、あたりにそのパチャパチャとした水音以外、
ほとんど何もないのだろうと想像を巡らせる。

都内のワンルームとは、大きくかけ離れた、もう1つの地球。
でも、星野さんは、その2つの時空を、写真と文章でつないでくれる。
映像でも、音声でもなく。
なぜだか分からないのに「一生死ぬまで追い続けることだろう」という言葉も心に残った。
1996年に急逝してしまったのに、星野さんの文章と写真には、つねに
“現在”“瞬間”が生き生きと流れている。
それが、私たちのココロを癒やし、自由にしてくれる。
本を開けば、星野さんがいて、今のアラスカの様子を語ってくれる。
私たちは日々慌しく動き回っているし、アラスカだって、今は様々な時代の変化と闘っている。
それは本書の中でもすでにひしひしと伝わってくるけれども、
この今も、極地では、グリズリーが白い息を吐いて歩き、カリブーたちは草をはんでいることだろう。
人々が目先の利益を追い求めて、ほんとうに大切なことを忘れている間も。
星野さんが心底願っていたように、この自然の営みが永遠に続いて欲しいと私も祈る。祈りつづける。

【内容抜粋メモ】
【カリブーのライフサイクル】

春の大移動
春と秋の大移動がある。春の南から北への季節移動は最も大切。
雌は、新しい命を宿して、冬の生息地から数百kmも離れた出産地に約2ヶ月かけて歩き続ける。
きっかけは、日照時間

が引き金になると言われる。
歩く場所は、雪の浅い場所、雪面がクラスト(固くなった積雪の表層)。

過酷な旅の間に、体力は極限まで消耗し、最悪子どもを失ったり、川で溺れ死んでしまう。
7月中に、約50%の子どもが死んでしまうこともある。
アラスカにはカリブーの大きな群れがいくつかあり、時には十万頭にもふくれあがる!
出産地によって属する分類が決まる。
移動が遅れた時は、移動の最中に出産する。出産にかかる時間はたった数分/驚
群れの80~90%の雌は毎年妊娠し、1頭の子どもを産む。初産は4歳以前は稀。

出産後、母は胎盤を食べてしまう。
子どもは1~2時間で立ち上がり、ミルクを飲む。
20%の脂肪を含むカリブーのミルクは、海洋哺乳類に次いで栄養価が高い。
子どもは、生まれて初めて見るものを親と判断し、後をついていく(鳥みたい
迷子になった子どもは、他の雌は育てることがないので、クマやオオカミに狙われる。
(カリブーの貴重な出産シーンに巡り会えた著者の感動が伝わる
生まれてすぐ長い旅に出なきゃならないなんて過酷。と同時に奇跡。
 「まだうぶ毛におおわれたような子どもは、川を渡り終えると、
まるで踊るように飛び上がりながら、真すぐこちらへ走ってくる。
一体何がそんなに嬉しいのだ」
「まだうぶ毛におおわれたような子どもは、川を渡り終えると、
まるで踊るように飛び上がりながら、真すぐこちらへ走ってくる。
一体何がそんなに嬉しいのだ」
出産地は荒涼としたツンドラ。捕食者が少ないから。
カリブーの武器は逃げることだけ。常にグループで危険を察知しなければならない。
カリブーの食べる「ワタスゲ」は、たくさんの栄養がある。
極北に広く分布する地衣類はたんぱく質が少ないがカリブーはそれにも適応した。
カリブーは、尿を再利用する仕組みを持っているのも関係している/驚

夏に悩ませる蚊の大群
極北で発生する蚊の数は想像を絶する。1頭のカリブーから1週間で約1Lの血を吸うと言われる/怖×∞
「トナカイヤドリバエ」は、カリブーの足に卵を産み、幼虫を寄生させる。
幼虫は背中に移動して、穴をあけて這い出す。
この雌バエの大群に襲われ、恐怖でパニックになることもある。

秋の大移動
初雪は、秋の季節移動の動きを早める。
秋は雄と雌が一緒に移動し、移動中に交尾が行われる(忙しいなあ!
雄の数が少ない理由の1つは「ハンティング」。

アラスカの冬
カリブーは、マイナス50度の中で適応できるシカ科の動物。その一生は、雪の中で生まれ、雪の中で死ぬ。
カリブーの毛は、熱に対する絶縁性が非常に高い反面、体温を下げる熱の放散が出来ない。
エスキモー、インディアンにとって、カリブーの毛皮は肉より大切だったはず。
「この土地の広さを、私はその時初めて実感した。
人間と関わりのない世界がもつ、生き生きとした空間の広がりにうたれていた」
「自然はいつも、強さの裏に脆さを秘めています。
そしてぼくが魅かれるのは、自然や生命のもつその脆さのほうです」
「地球上に、このような手つかずの自然が残されることが、人間にとって必要だと思った」
「カチカチカチカチ・・・それは蹄の音ではなく、カリブーの柔らかな下肢の腱が歩きながらスナップする音だった。
それは何という心地よい響きだったろう」

「私のテントのまわりは一面、極地の花が咲き乱れていた。
(1万頭のカリブーの群れが過ぎると)見渡す限りの花がほとんど食べ尽くされているのである。
花が消えてしまった淋しさ以上に、私は感動していた」
「いつも、いつも、遅く生まれ過ぎたと思っていた。
が、今私の目の前を、カリブーの大群が何千年前と変わりなく旅を続けているのを見て、
何かに間に合ったような気がしたのである」

「あらゆる生命が、ゆっくりと生まれ変わりながら、終わりのない旅をしている」
「木も、岩も、風さえも、魂をもって、じっと人間を見据えている。
ただ流れてゆく時を、大切にしたい。
あわただしい、人間の日々の営みと並行して、もうひとつの時間が流れていることを、
いつも心のどこかで感じていたい」
「生命とは、一体どこからやって来て、どこへ行ってしまうものなのか。
あらゆる生命は目に見えぬ糸でつながりながら、それはひとつの同じ生命体なのだろうか。
木も人もそこから生まれでる、その時その時のつかの間の表現物に過ぎないのかもしれない」
「もし人間の一生が、カレンダーで区切られるものならば、
70歳まで生きるとして、70冊のカレンダーだ。つくづく時の流れの奇妙さを思った。
最後に意味をもつのは、結果ではなく、過ごしてしまった、かけがえのないその時間である」
「今、目の前に横たわるカリブーの骨は、ゆっくりと大地に帰り、
また新たな旅が始まろうとしているではないか。
自然はその時になって、そしてたった一度だけ、
私たちを優しく抱擁してくれるのではないだろうか」
「カナダガンの編隊が空高く、やはり真すぐ南へ向かって飛んでいった。
ゆったりとして、たしかな、自然が内包するそのリズムは、
なぜか人間の気持ちを悲しくさせるような気がした。
私たちは、暮れてゆく原野に立ち、その遠い呼び声に耳をすませていた」
「彼らを包み込む自然は、太古の昔と何も変わってはいない。
彼らはピラミッドも神殿も建てはしなかったが、自然を変えなかった。
狩猟民が持つ自然観は、私たちが失ってきたひとつの力である」
「つかのまの太陽を見つめていると、可笑しいな話だが、そのいとおしさに心が満たされてくる。
そしてこの冬を越すたびに、何かが心の中に降り積もり、
この土地から離れられなくなってゆくような気がするのだ」
「地球上で、人間の手がつけられていない自然は、いったいどれだけ残っているのだろうか。
それを、いつまでも後の世代に残していけないものだろうか」
【カリブーの撮影日誌(1980・1986・1992)抜粋メモ】
※アラスカへの思いが綴られている中から、カリブーに関する記述の一部を収録。

1980年
5/28 この強風はきちがいざただ。
6/5
エスキモーにとって、カリブーは単なる食料供給源ではなく、昔からの大切な文化的意味を持っている。
その関係はかつてのアメリカインディアンとバッファローとの関係に似たものだろう。
動物保護だけに目をとらわれ、動物と密接な関係を持つエスキモーの生活のことを忘れがちである。
彼らの狩猟は、白人が行う「スポーツ・ハンティング」とははっきり区別されなければならない。

1986年
4/29
とにかく、撮影だけは厳しくやっていこう。
うまくいってる時はどんどん押してゆくこと。
そしてうまくいかない時は、投げずにじっくり動き続けてゆくこと。
4/30
カリブーの去った後の空虚さはどう表現したらいいのだろう。
英語でいうVastness(途方もない広大さ)。
5/24
もし失敗したとしても、そのことさえもプラスに考えていこう。
これだけ1つのものを待てるということ、単調さ、複雑な気持ちのめぐりあいを乗り越えられるということ、
それが次の撮影のステップになってゆくだろう。
5/29
福音館の仕事のためにキャンプ用具の撮影をした。
6/28
ヘリコプターの空撮のほうが地上よりずっといい撮影ができる。
7/3
ジムがコッツビューから来るのに1.5時間。安いフライトではない。
7/10
ヘリコプターを使うことを来年は頭に入れよう。
それが最高の方法なのだから、必ずそうしよう。
金だけの問題なら、どうにかしよう。
7/17
「アラスカ州漁業狩猟局」のダンが迎えに来てくれた(いろんな組織とも連携が必要なんだなあ

1992年
7/1
A.N.W.R.でたとえ大きな原油を得たとしても、それは何と短期的な出来事なのだろう。
一度手をつけたら、この土地のもつ意味は、たとえカリブーが生き残ろうとも消え失せるだろう。
カリブーの写真集を、本当にいい形でまとめたい。
自分がつくる本の中で、これほど大切な本は後にも先にもないだろう。
写真家が1冊の本をつくるために生きているのなら、僕の場合はこの1冊に違いない。
7/2
撮影がうまく進んでいようが、いまいが、そんなこととは無関係な時をもつことを忘れないようにしたい。
7/3
1日だけどカリブーの大群に地上で出合えて本当にラッキーだった。
あの日が一体どれだけラッキーだったかは、N.H.Kの人たちは決して理解できないだろう。
分かれと言っても無理な話なのだ。
ただそのことを理解できないかぎり、カリブーについては語れないだろう。
7/4
ドンが秋にテレメーターをつけたカリブーをもう一度捕獲するとのこと。
カリブーを撮り続けてもう13年になる。
もう十分1冊の写真集ができるだろう。
本ができたら、もうここには戻ってこないだろうか。
いや、まったく変わることなく、自分はこの土地でカリブーを撮り続けるだろうと思う。
そのことに、自分で、自分に驚いてしまう。一体なぜなのだろうか。
自分はきっと、死ぬまでカリブーを見続けるだろう。
7/7
グリズリーがカリブーを食べている。
7/9
明け方見た毛も生えていないツメナガホオジロのヒナは、4時間後には、
すっかり毛むくじゃらになっているのにはびっくりした。
こんなにも早く成長するものなのだろうか。
(同じひと?w それとも、濡れた羽根が乾いてふんわり大きく見えたとか

いろんな移動手段
エア・タクシー
スノーモービル
ヘリコプター
セスナ機の1回のフライトに$2800.00かかる!
スーパーカブ

 パニック障害者の差し歯治療(2015.10.13)
パニック障害者の差し歯治療(2015.10.13)











 (戦闘態勢
(戦闘態勢





 その1
その1 その2
その2













 が引き金になると言われる。
が引き金になると言われる。


 夏に悩ませる蚊の大群
夏に悩ませる蚊の大群