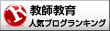子さま4時限目だけ登校、雅子さまと一緒に
 |
| 学習院初等科に登校する生徒たち Photo By スポニチ |
今月に入ってほとんど学校に行けない状態になっていた皇太子家の長女愛子さま(8)が8日、学習院初等科2年のクラスに6日ぶりに登校した。2日に登校して以来、欠席が続いていた。 宮内庁によると、愛子さまは皇太子妃雅子さまに伴われお住まいの東宮御所(東京都港区)を出発。午前11時半ごろに登校し、4時限目の国語の授業だけ出席した。愛子さまが不安に感じないようにと、雅子さまも授業を参観。45分間の授業が終わると2人で帰った。9日以降も登校するかどうかは分からないという。雅子さまが指定された参観日以外に見学されたのは初めて。 宮内庁の風岡典之次長は8日の定例会見で、愛子さまがほとんど登校できなくなっていたことについて、野村一成東宮大夫が近く天皇、皇后両陛下に直接事情を説明することを明らかにした。野村大夫は「両陛下も心配されていると思われる」として、説明を申し出た。愛子さまが6日ぶりに登校したことも伝えるという。 また、野村大夫が5日の記者会見で「学校で同学年の複数の男児から乱暴な振る舞いを受け、強い不安感や腹痛を訴えている」などと周囲の児童が絡む学校現場の状況に踏み込んで、自ら発表したことに批判が相次いでいるが、風岡次長は「学校側の了解を得ており、手順を踏んでいる。適当だった」と話した。 しかし、学習院側が「愛子さまに直接の暴力行為があったとは聞いていない」と否定するなど双方の説明に食い違いがあることについては「知らない」と言及を避けた。 』
学習院でも学級崩壊…昨年6月には“事件” 『学習院初等科では昨年夏ごろから、校内を乱す「学級崩壊」が問題になっていた。 週刊誌「サンデー毎日」は09年10月4日号で、同年6月に1年生のクラスで男子児童が、後ろの席に座る女子児童の顔を鉛筆で傷つける“事件”があったと報じた。愛子さまと同じ2年生のクラスでも、授業中に先生の話を聞かずに騒ぐ児童が増え、授業が成立しない学級崩壊状態に。ひどい児童は勝手に立ち歩いたり、廊下にまで出て行って走り回ったりしていたという。
こうした状況を児童から聞いた保護者の代表は7月初旬、三浦芳雄科長(初等科の校長)に面会。学校側に改善策を求め、学校側が1学期の終業式当日にこのクラスだけの「緊急学級父母会」を開催する事態にまで発展した。
東園氏はこの日、取材陣に対し、学級崩壊について「残念ながら、あるクラスにかたよって起こっていたことはある。先生の手に余ってしまうクラスがあったようだ」と説明。その上で「愛子さまのクラスではない」とした。 対応策については「個別指導をすると、親の反発を買う可能性もある。乱暴な振る舞いをする児童にレッテルを張るのも教育上の問題がある」とその難しさを指摘した。 学習院には天皇陛下や皇太子さまをはじめ、歴代天皇家の大半が通学。しかし、最近では高円宮家の長女承子さまが早大に進学したほか、秋篠宮家の長女眞子さまが国際基督教大に、長男悠仁さまもお茶の水女子大付属幼稚園に4月から通う予定。“学習院離れ”が進んでいる。』 [ 2010年03月6日スポニチ
「学習院でも学級崩壊…昨年6月にに1年生のクラスで男子児童が、後ろの席に座る女子児童の顔を鉛筆で傷つける“事件”があったと報じた。愛子さまと同じ2年生のクラスでも、授業中に先生の話を聞かずに騒ぐ児童が増え、授業が成立しない学級崩壊状態に。ひどい児童は勝手に立ち歩いたり、廊下にまで出て行って走り回ったりしていたと言う 。」何とだらしない学習院の小学校と世間の人は言うと思います。学習院は、清く、正しく、美しくのイメージに反するような耳を疑う出来事です。名門学習院初等部、小学校は、世間の人達は児童への生徒指導も行き届いている思っています。学級崩壊や教室の外廊下に出て授業放棄をする児童など学習院の恥です。本当に信じられない出来事です。このような児童を厳しく指導しなかった学級担任や生活指導担当教諭の責任問題では有りませんか。お坊ちゃんやお嬢ちゃんで有ろうと無かろうと小学校低学年から、先生が悪い事をしたら悪いとその時、その場、子供達に注意し、叱って置かない中学生や高校生になってから注意しても、親の言うことは聞かないで先生に反感を持ち暴力を振るうだけです。大きくなってからでは後祭りで時既に遅しです。今の学校教育の興廃も小さい時からの躾けの悪さでは有りませんか。教育現場での子供達への学校としての躾けを初めに忘れたらこのような状況になるのは非を見るに明らかで小さいうちに悪い芽は摘み取れの生活指導基本原則を学校が忘れています。学級崩壊は、学習院初等部だけの問題では有りません。先生の手に余ったクラスが有ったとか個別指導をすると親の反感を買うなどとても考えられないことです。学習院初等部の小学校2年の児童なのに学校として生徒指導も十分せずに乱暴な振る舞いをする児童を学校として注意し叱らない、個人的に先生が指導しないと今回のような学級崩壊が又起き、終いには学校全体に進み取り返しが付かない事態になると思います。学校としての生活指導方針と取り組みの甘さに問題が有ると言わざるを得ません。愛子様以外にも乱暴狼藉を働いた男子児童は、実際には沢山いるのでは有りませんか。伝統ある名門学習院として、三浦芳雄科長、初等科の校長や生活指導担当の先生が、真剣に児童への生活指導に今後取り組むべきです。そうしないと18歳人口の減少による少子化の時代です。名門学習院初等科に入学する生徒が、来年度から現実に減少するのでは有りませんか。愛子様に対する乱暴狼藉問題は、学習院が学校として誠意を持って対応し、解決すべき学校内の問題です。国民も皆注視していますので、学習院側が責任を持って解決しないと伝統のある学習院の伝統と信頼に傷付くと思います。
URL http://www18.ocn.ne.jp/~abc8181
プログランキングドツトネット http://blogranking.net/blogs/26928
日本プログ村 http://www.blogmura.com/profile/232300.html
人気プログランキング
http://parts.blog.with2.net/bp.php?id=627436:aLHKFCm5fBU"></
「 自動車の「スズキ」や楽器の「ヤマハ」などが本社を置く浜松市。JR浜松駅から車で15分ほどの文教地区に静岡大学浜松キャンパスはある。 ここから日本のものづくりの歴史に名を刻む技術者が何人も巣立っていった。その伝統が息づく「第14回テクノフェスタIN浜松」が開かれた11月中旬、キャンパスを訪ねた。 1996年に始まり、工学部と情報学部の研究室が最新の研究や実験の面白さを伝えようと、工夫を凝らす看板イベント。来場者は2日間で9000人を超えた。「ゴー・ヨン・サン・ニー・イチ!」。雨上がりのグラウンドで、カウントダウンとともに空に飛び出したペットボトルのロケットが大きな弧を描くと、子どもたちが歓声を上げた。 ロケットの作り方を教えていた機械工学科4年の松本拓也さん(22)はこの日、久しぶりにキャンパスに戻った。日頃の研究拠点は、東京・調布の宇宙航空研究開発機構(JAXA)。大学は06年に協定を結び、大学院生2人を含む計3人を研修生として送っている。 9月から東京に住む松本さんは「設備が充実しているし、大学ではできない実験にも取り組める」と、スペースデブリ(宇宙ゴミ)の除去に関する研究に没頭。航空宇宙分野は、浜松市や地元商工会議所も将来の中核産業化をにらんで力を入れ、産学官連携が進む。 グラウンド脇には、高柳記念未来技術創造館。高柳とは、工学部の前身の浜松高等工業学校で教えながら、電子式ブラウン管テレビを発明した「テレビの父」、高柳健次郎氏のことだ。 同校では、「ホンダ」創業者の本田宗一郎氏も聴講生として学んだ。「『やらまいか』(とにかくやってみよう)という遠州の人に共通のチャレンジ精神が、キャンパスにも息づいている」と、柳沢正工学部長(59)が解説してくれた。 県西部の浜松キャンパスが「西」と呼ばれるのに対し、静岡キャンパスは「東」。その東で10月、学内ベンチャー企業が生まれた。最先端のトマト キャンパスから西へ25キロ。藤枝市の地域フィールド科学教育研究センターでは、ビニールハウスでトマトが赤く色付き始めていた。250ミリ・リットルの小さな容器に入れた培地で1株ずつ育てる最先端の技術。「定植や収穫後の片付けが簡単で、経験がない人でもできる」と糠谷明教授(59)。水やりを抑え、深い甘みを持つ「静大トマト」として世に出す考えだ。 日々の管理を担う農学研究科1年の江岸諭史さん(23)は福井県出身。将来の営農を見据え、4年次からトマトを専門にしている。温度や湿度などのデータを細かく取り、栽培ノウハウの確立を目指す。「狙った通りの育ち方をしてくれるのが一番うれしい」と連日、500平方メートルの隅々まで目を光らせている。 卒業生の間には「苦労を乗り越え、自らやり抜く気概を持つ人が減った」と懸念する声もあるという。それでも地道な研究の先に時代を切り開こうとする意志は、確かに感じられた。)」読売新聞2009年12月4日
大都市圏の国立大學では取り組めない、地元地域に密着した研究や地域に貢献出来るのが地方の国立大学ではないでしょうか。地方の大学ならではの緑豊かな自然環境と最先端科学技術を生かしたトマト栽培で、後継者不足の悩む日本の農業問題の解決や日本の食料自給率の向上に大学の研究が役立つのでは無いでしょうか。地方の国立大学は、地元地域の皆さんとの交流通じて地元に開放された大學として地域産業、地場産業に役立つ、拠点としての大切な役割があるのではないでしょうか。静岡県の産業界や地域経済や地域住民のグーロカル化を高める大切な役目を背負っていると思います。最近唱えられている地方の活性化の中心的存在が、地方の国立大学の21世紀のこれからの姿では無いでしょうか。浜松高等工業学校で聴講生として学ばれた本田技研の創業者の本田宗一郎氏 の「会社はつぶれてもいいから、人の真似をするのだけは絶対にいやだ。」と言われた名言どおり他に類をみないユーニクな研究業績を上げて下さい。
「テレビの父」高柳健次郎氏
高柳の功績と教訓
1.研究は世の中のため、人の幸せのために
- 高柳の発想の原点は、いつも「将来のためになるか、世の中のために役に立つか、人々の幸せにつながるか」であった。
- 方法は、「何のために」 が先ずあり、すべてのエネルギーをその目標に向けて注ぎ込むやり方である。
技術者が陥りがちな、技術開発それ自体を自己目的化したり、いたずらに他とスペックを競い合う不毛な先陣争いには目もくれなかった。
まして自分の利益や名声はまったく眼中になかった。 - 浜松高工でのテレビの研究開発では、自分のアイデアを惜しげもなくチーム研究に注ぎ込んだ。
「テレビという、将来必ずや人々に幸せをもたらすであろう夢の機械を創り出す」 この明確なターゲットが、高柳とそのチームのメンバーの気持ちを一つにした。 - 戦後、日本ビクターに入社後まもなく結成された「テレビジョン同好会」も、高柳が「テレビの技術を伸ばしていくためには、どうしても技術者が集まってお互いに研鑚に努めなければいけない」と、郵政省、学校、企業、NHKなどの研究機関にいるテレビ研究者に声をかけ30人位でスタートしたのだった。企業の枠を超えて、毎月1回会合を開き、情報交換して互いに切磋琢磨した。
このグループは4年後(昭和25)には(社)日本テレビジョン学会に発展・改組され、またS.27年ころ、テレビの普及促進のために標準型の受像機を作ろうと、業界が一致できたのも、この「同好会」以来の共通の基盤があったからだった。 - 理想を掲げ、その旗の下で産業発展に尽くすという姿勢は、VHSの開発と世界を舞台とする新しい映像文化の創造に命をかけた“ミスターVHS”のニックネームを持つ高野鎭雄氏に受け継がれ、花開いた。
- 高柳の思想が、昨今の情報機器やディスクメディア等の分野での、「我こそは最高スピード」「ウチのが最大容量」云々の先陣争い、その結果としての短命な技術ライフサイクルなど、ともすればユーザー不在、目標不鮮明となりがちな技術開発競争の現状に、改めて警鐘を鳴らしているのではないだろうか。
2.「個の成長と、全体の成果」の両方を実現するプロジェクトチーム
- 1930年(昭和 5)の「天覧」を機会に、浜松高工の高柳研究室は公式にテレビジョン研究施設に昇格、予算、人員などが増強され、念願の「チームによる研究」が可能になった。1934年(昭和9)の欧米視察以後1年余りをかけて撮像管を完成させたのは、テーマを絞り込んで共同研究に取り組んだ「高柳式プロジェクトチーム」の成果だった。
- 高柳は著書『テレビ事始』のなかで、当時のことを次のように回顧している。
「私たちは一週間おきに研究会議を開いて報告し、お互いに報告について遠慮なく意見を述べあい、次の段階へ向かって激励しあった。一人は信号板の光電微粒子の製法について画期的な発明をしてくれたし、またある者は、信号版を撮像管の中に封入するよい方法を考え出すなど、誰もがみな適切な改良を行った。
私は一生を通じて、これほど充実した研究生活を送った時期はないと思う実際的な成果も大きかったが、多くの人たちと心を一つにして、しかも一人一人の能力を最大限に発揮するという雰囲気がおのずと作られていった、そのこと自体が貴重なことだったからである。」 - 高柳の「全員が成長できるチーム研究」の方法は、「学者であれ発明家であれ、その人だけが卓越した知識を持ち、独占し、弟子たちはまったくの補助協力者として扱われて、重要なことは何ら教えられず、弟子自身が生み出した成果さえ先生のものとされてしまうといいう時代」(同書)にあって画期的であったというにとどまらない。
現代の大学や企業の研究開発プロジェクトチームにありがちな、個々のメンバーを手駒として集め、研究システムの歯車や部品のように構成してテーマを追い込んでいく最近のやり方にも、是非を問うものと言えそうである。
3.自らの体験に報い、教育・人材育成に献身
- 高柳は、子どもの頃劣等生だった自分が担任の先生から、「やればできる」ことを教わり勇気づけられたこと、大学の恩師に「目先にとらわれず、遠い先を見て将来の世の中に役立つ人間になれ」とアドバイスされたことを生涯の指針とした。自分の能力を生かすことができ、社会への貢献が第一という思想も、自分が受けた教えから形成されたと信じ、教育の偉大さを痛感していた。
- プロジェクトチーム研究での、皆がやりがいを持って参加でき、その過程で一人一人が力を伸ばすことができることを重視した指導法も、人を育てることへの意欲の現れだった。
- 日本ビクターでの功績も、カラーテレビの大幅改良はもとより、世界の標準ステレオ方式となった「45-45方式」や、4チャンネル「CD-4」システムなどオーディオ分野の技術開発、VTRの基礎技術から「VHS」開発へと、研究開発部門のリーダーとしてプロジェクトチームを指揮、人材の育成と事業化を先導した。日本ビクターが、世界市場が認めるオリジナル志向の技術開発型企業へと発展してきたのには、この高柳の貢献に負うところ大である。
《高柳の研究開発指導方針》
|
- 高柳の後進育成への熱意は、浜松電子工学奨励会、(財)高柳記念電子科学技術振興財団といった、私財を基金とした研究助成のほか、(社)日本テレビジョン学会、日本ビクター技術報告大会での「高柳賞」制度として今も受け継がれている。(上記すべての会、団体に「高柳賞」がある。)
高柳記念財団設立では、「現在は世間に認められていなくても、将来を目指して頑張っている芽をつぶさないで、応援したい」という高柳の発案で研究助成のプログラムが作られた。
☆静岡大学のホームページwww.shizuoka.ac.jp
〈沿革〉
1875年に開学した静岡師範学校など5校が1949年に統合され、文理学部、教育学部、工学部でスタート。51年に農学部、65年に文理学部から分離した人文学部と理学部、95年に情報学部が発足した。静岡キャンパスに人文、教育、理学、農学部、浜松キャンパスに工学部と情報学部がある。学生数は約8800人。入学者の7割を県内を含む東海地方出身者が占める。緑豊かな静岡キャンパスは竹林が多く、毎年4月にタケノコ掘りのため開放される。

リサイクルショップに売られていたペコちゃん人形(昨年9月、和歌山東署で) 【読売新聞社】
(読売新聞) 2010年3月12日(金)09:22
「洋菓子店「不二家」のペコちゃん人形を盗んだとして窃盗と同未遂罪に問われた大阪府四條畷市、解体作業員池田興應被告(38)の論告求刑公判が11日、和歌山地裁(国分進裁判官)であった。 検察側は「持ち出しや売却を担い、常習的な犯行」として懲役3年を求刑した。 起訴状によると、池田被告は2008年12月30日~09年2月12日、和歌山など2府2県の不二家で、ペコちゃん人形計7体(約40万円相当)を盗み、同1月3日、大阪府岸和田市で1体を盗もうとしたとされる。 被告人質問で、池田被告は犯行を思い立った経緯について「週刊誌で高値で売れると知った」と話した。検察側は「国民的アイドルといえるペコちゃん人形を窃取した犯行の社会的影響は無視できない」と主張。弁護側は「深く反省している」と訴えた。」2010年3月12日(金)09:22
不二家のペコちゃんは、1950年(昭和25年)不二家のアイドル「ペコちゃん」誕生(年齢6才)誕生しました。幼児や小年、少女のアイドル的存在です。子供達の夢と希望のシンボルを7人分も盗むのは許されません。大人が、子供達の夢を奪うのは良くないと思います。検察側の「国民的アイドルと言えるいえるペコちゃん人形を窃取した犯行の社会的影響は無視できない」は子供達からの代弁でも有ります。私の亡くなった大正15年生まれ、昭和元年に近い母もペコちゃんのファンでしたよ。日本の子供達の国民的アイドルのぺコちゃん人形を大切にして欲しいと思います。
☆詳しくは皆下記をご覧下さい。
Peko World ペコワールド | 不二家
www.fujiya-peko.co.jp/pekoworld