
天木 直人
きょう9月5日のニュースで私がもっとも関心を持って受け止めたのは何と
言ってもこれだ。
すなわち9月4日、日本プロ野球選手会の新井会長がワールド・ベースボール・
クラシック(WBC)への不参加表明を一転して撤回し、参加宣言をしたというニュースだ。
こうなることは当初より予想できた。
プロ野球フアンの事を考えれば不参加はありえないからだ。
この問題の政治的意味合いに気づかない一般国民にとっては不参加は
金目当てのプロ野球選手のわがままとしか映らないからだ。
労組である日本プロ野球選手会が経営者である日本野球機構(NPB)
に逆い続けることは難しいからだ。
そして何よりも日本のプロ野球界を牛耳っているが対米従属のナベツネ
と日本プロ野球コミッショナーに天下った元駐米大使の加藤良三氏である
からだ。
今度の不参加撤回劇は対米従属の日本外交をそっくりそのまま象徴して
いるのである。
どの新聞もはっきり書かない。
だから国民はわからない。
しかし今回の合意は米国の不合理な要求には指一本つけることなく
日本人同士で、つまり日本野球機構と日本プロ野球選手協会との間で折り
合いをつけて解決したものなのだ。
米側と日本側の利益配分66%対13%という不合理を、大リーグ機構
(MLB)と大リーグ選手会は一歩も譲らないと最初から公言していた。
嫌なら参加しなくて結構だという態度を貫いた。
日本を守ってもらいたかったら不平等条約に文句を言うなという日米
同盟の論理とまったく同じ構図だ。
だから選手会が勝ち取ったとされる侍ジャパンのスポンサー権の承認
などはNPBが日本プロ野球選手会に約束したものでしかないのだ。
あたかも日本政府が沖縄に金をばら撒いてなだめるようなものだ。
オスプレイの配備の強行と同じだ。安全性の確保を強調して国民に泣き
ついて認めさせる。
要するに日本人同士が内輪で大騒ぎして最後は妥協して収める。
米国の腹はまったく痛まない。米国の方針は何があっても揺るがない。
このような残念な決着ではあっても、私はプロ野球選手会を批判する気
はない。
新井選手会長とプロ野球選手会、そしてもっと言えば、隠れた主役である
日本プロ野球選手会の松原徹事務局長の反骨魂を讃えたい。
閉塞した日本のプロ野球支配構造に一石を投じた勇気を讃えたい。
妥協してなお「このような要求は本来は選手会がやることではない。NPB
が大リーグ側とやるべきだ」と言って対米従属の加藤良三コミッショナーを
批判した、その気骨を評価する。
少なくとも対米従属の日米同盟に異を唱えない日本の一般的な国民より
はるかに政治的に目覚めている。
それにしてもと思う。
今度のプロ野球選手会の謀反を、対米従属批判の脈絡でとらえたメディア
は皆無だ。
メディアが気づかないはずはない。
知っていながら一切その事に言及しない。
日米同盟の矛盾に少しでも疑義を抱かせるような事は書かないという
驚くべきタブーが間違いなくこの国のメディアには存在するということである。
了
「天木直人のメールマガジン」は報道の裏にある真実を求めて
毎日配信しています。
この他にも次のようなテーマで書いています。
1.「山本美香さんの死」 から読み取る曽野綾子の選民意識
2.トルコとクルドの交戦にまで飛び火したシリアの内戦
3. 破綻した日本のアフガン復興支援
4. 目の前の原発問題を何一つ処理できずに原発ゼロを論じる欺瞞
5. 大使車襲撃事件の真相を一番よく知っているのは日本大使館だ
6. 国民を忘れて選挙の顔選びに忙しい亡国の国会議員たち
7. 地方主権を成功させるには地方議員の質を高める必要がある
8.カザフスタンで開かれていた核廃絶を訴える国際会議
9.もはや米中全面戦争はありえなくなった
10. 慰安婦問題を原点から見直せと書いた毎日新聞記者
11.情報工作をするものは情報工作によって自滅する
12.「民意から遠い野田首相」と書いた東京新聞
13.オスプレイ広報大臣で終わる森本防衛大臣
申し込みはこちらから ⇒ http://goo.gl/YMCeC
定期購読申込と同時に当月配信のメルマガ全てがさかのぼって購読できます。
◎2012年 8月配信分テーマ ⇒ http://goo.gl/E81By
◎2012年 7月配信分テーマ ⇒ http://goo.gl/hGnWH
◎2012年 6月配信分テーマ ⇒ http://goo.gl/YiYws
それ以前のバックナンバーはこちら
⇒ http://goo.gl/lq86t
Copyright ©2005-2012 www.amakiblog.com













 投稿: 管理人
投稿: 管理人 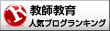















最近のコメント