我慢してない?「おなら」はためると身体に負担が!
・便秘を改善する
・緊張、ストレスを解消する
少し前の報道であるが、12月14日の東京新聞が報じていた。
トランプ次期米国大統領が12月12日の自らのツイッターで、米国防総省が米ロッキード・マーチン社から購入予定の最新鋭ステルス戦闘機F35について、「高額すぎる」と疑問視したと。
そして、トランプ氏の政権移譲チームは、「次期政権は納税者のために、あらゆる場面で税金を節約していく」と語ったと。
私がこの東京新聞の記事で驚いたのは、その発言を受けた日本の対応だ。
稲田朋美防衛相は13日の記者会見で、「現時点で日本側の方針に変更が生じることはない」と述べて、一機約180億円もするF35を空自が最終的に42機購入することに変わりはないと言わんばかりの発言をしたのだ。
しかし、それから10日ほど経ったきのう12月25日の日経が、ワシントン発共同として、つぎのような一段の小さな記事を掲載した。
米ロッキード・マーチン社のヒューソン最高経営責任者は23日、最新鋭ステルス戦闘機F35の値下げについて、「積極的にコスト削減に取り組む」との考えをトランプ氏に伝えたとする声明を発表したと。
この一連のやりとりを我々は見逃してはいけない。
来年度予算におけるF35の購入積算根拠が、もし一機約180億円となっていれば、それはもはや無効だ。
ロッキード社がトランプ政権に最終的にいくらで納入するかを見届けたうえで予算を変更する必要がある。
果たして来年1月20日から始まる国会において、F35機の購入計画についての見直し議論が行われるだろうか。
野党は安倍政権を追及できるのか。
我々は来年の国会審議から目を離してはいけない(了)

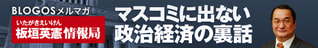

 |
野党協力の深層 (詩想社新書) |
| クリエーター情報なし | |
| 星雲社 |
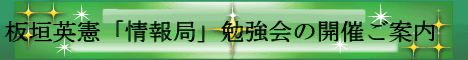
 |
911テロ/15年目の真実 【アメリカ1%寡頭権力】の狂ったシナリオ 《完ぺきだった世界洗脳》はここから溶け出した |
| クリエーター情報なし | |
| ヒカルランド |
 |
トランプと「アメリカ1%寡頭権力」との戦い 日本独立はそのゆくえにかかっている! |
| クリス・ノース(政治学者),ベンジャミン・フルフォード(元フォーブス誌アジア太平洋支局長),板垣英憲(元毎日新聞政治部記者),リチャード・コシミズ(日本独立党党首) | |
| ヒカルランド |
産経新聞 12/26(月) 14:15配信 14:04
『 勤務中に部下の20代の女性巡査の胸をわしづかみにしたとして、兵庫県警が来年1月に加古川署の男性巡査部長(33)を強制わいせつ容疑で書類送検する方針を固めたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。県警は同日、巡査部長を停職3カ月の懲戒処分にした。 捜査関係者によると、巡査部長は今年7月21日、署内の会議室で部下の巡査と2人きりになった際、服の上から巡査の胸を左手でわしづかみにした疑いが持たれている。 巡査部長は2月から約7カ月間、署内や交番などで数十回にわたり巡査の胸や尻を触るセクハラを繰り返していたが、巡査は当初、巡査部長から仕事を教えてもらっていることを理由に被害を申告しなかった。 同僚の女性警察官が9月末、巡査にセクハラを受けていないか確認し、被害が発覚。巡査部長は県警の調べに、「行動を共にするうちに異性としての魅力を感じるようになり、行為がエスカレートした」と説明しているという。』
勤務中に部下の20代の女性巡査の胸をわしづかみにするくらいなら、紙幣をわしづかみにしてください。
上司と部下の公私混同は、警察官としてよくありません。

朝日新聞デジタル 12/25(日) 20:52配信
中国艦船の動き
防衛省統合幕僚監部は25日、同日午前10時ごろ、中国初の空母「遼寧」を含む艦船6隻が宮古島の北東約110キロで南東へ航行しているのを、海自の哨戒機と護衛艦が確認したと発表した。沖縄本島と宮古島の間を通って太平洋へ向かったが、中国の空母が太平洋に抜けるのを海自が確認したのは初めて。今後、南シナ海に向かうとみられる。領海への侵入はなかった。 遼寧はウクライナから入手した旧ソ連の空母を改修した中国初の空母で、2012年に就役。山東省青島が母港だ。統幕によると遼寧にはミサイル駆逐艦3隻とフリゲート2隻が同行。24日午後4時ごろには、海自の護衛艦が東シナ海中部で遼寧を確認していた。 中国側は、日本や台湾などを結ぶ「第1列島線」を越え、遠洋での空母の実戦能力を向上させる構え。遼寧が南シナ海に入れば、13年に試験的な航行をして以来で、今回は多数の艦載機を載せるなど実戦的な装備で臨むことになる。 中国軍は一連の訓練を「年度計画に基づく」ものとしているが、南シナ海で「航行の自由」作戦を続けてきた米軍や、台湾問題や南シナ海問題などで対中強硬姿勢を見せる米国のトランプ次期政権を牽制(けんせい)する狙いもあるとみられ、緊張が高まる恐れがある。(福井悠介、北京=西村大輔)
原子力空母を10隻保有する最強のアメリカ海軍は、外見は建造時とさほど変わらなくても旧日本海軍とは違い最新技術力を駆使し改良に改良を重ねた 空母で、中国海軍が人昔前の一隻空母を就役させても米次期政権への牽制にもならないのではありませんか。
東南アジア諸国への空母による示威と威嚇、砲艦外交、、空母外交の一環でしょう。
世界一の大国を目指す中国、アメリカ海軍との衝突も今後考えられます。
アメリカ海軍は、第七艦隊は中国海軍との腕はなるなる、腕試しなど実戦経験豊富な海の男だ、朝飯前で中国海軍の技量を計るためにこの一戦ぐらい平気で望むと思います。
最初に建造されたのは1960年進水のアメリカ海軍の「エンタープライズ」である。移動できる兵器としては人類最大のものである。そのため、多くの映画・小説・テレビ番組にも登場し、アメリカ海軍の象徴的な存在である。
2016年現在、原子力空母を運用しているのはアメリカ海軍のニミッツ級10隻とフランス海軍の「シャルル・ド・ゴール」の合わせて11隻だけである。旧ソ連海軍も計画していたが、ソ連崩壊により中止された。
アメリカ海軍で90機、仏海軍のシャルル・ド・ゴールで40機ほどの各種航空機を艦内に収容して、海上戦闘、航空戦闘、陸上への戦力投射、輸送、軍事活動支援、人道援助、外交などの各種活動に多角的に対応できる柔軟性を持つ。
アメリカ海軍では空母打撃群(Carrier Strike Group, CSG)の中核となり、空母の船としての指揮は艦長である大佐が行い、空母航空団(Carrier Air Wing, 略記号ではCVW)の指揮官はCAG(キャグ、Commander, Air Group)と呼ばれる別の大佐が行なう。空母打撃群を指揮する少将のもとに両大佐が直属する。なお、艦長を補佐する副長(XO)も、CAGを補佐する副CAG(DCAG)も共に大佐である。
1艦に2,000人から5,500人もの人員が乗り込み、何ヶ月もの長期(多くが6ヶ月間)に渡り本国を離れた遠い洋上で生活するため、艦内に診療室、床屋、郵便局、売店、教会などを備えた小さな街を形成している。
2016年現在の時点で原子力空母を語ることは、多くの点でアメリカ海軍の原子力空母を語ることになる。
米国の原子力空母を含む大型空母は通常は一隻の空母とミサイル巡洋艦、ミサイル駆逐艦など複数の護衛艦艇および攻撃型原子力潜水艦、高速戦闘支援艦・給油艦・戦闘給糧艦などよりなる空母打撃群(Carrier Strike Group, CSG)を構成して空母単艦では脆弱な海中や空中からの攻撃などにそなえている。
もともと空母という軍艦は、水上偵察機からはじまって、海上戦闘のための艦上戦闘機や艦上攻撃機を海上で運用することを目的に開発が進められた。真珠湾攻撃で陸地への攻撃が有名になったように陸への攻撃が有効である場合もあるが、第二次世界大戦当時やその直後の段階では大型爆撃機と無誘導爆弾が空から陸上への攻撃の主体であり、狭い空母の甲板では小型の爆撃機ですら運用が難しかった。
ベトナム戦争では、空母発進の戦闘攻撃機が内陸へ爆撃を加えることもあったが、爆撃の主力は地上から飛び立つ戦略爆撃機であった。やがて時代は進み、大陸間弾道ミサイルですらかなりの誘導精度を持つに至ったが、核弾道弾の恐怖からくる核戦争へのリスクが、安易なミサイルの使用を制限し、費用対効果の点でも飛行機による陸への攻撃という手段が徐々に大きな地位を占め始めた。やがて1992年に アメリカ海軍は新しい戦略のキーワードとして「From The Sea」を発表した。その中心は潜水艦による陸地へのミサイル攻撃と合わせて、空母打撃群による陸への「力の投射」戦略である。空母を海上戦闘に使うこと より、積極的に陸地を攻撃することを目的とするこの戦略転換により冷戦終結後の軍縮の危機を米海軍は上手に生き延びた。
近年のアメリカの、武力によって世界に積極的に関わっていく政策下では、原子力空母の登場する機会が今まで以上に増しており、ここ数年は中東のイラン、イラクと東アジアの北朝鮮、中国を意識した態度表明として、ペルシャ湾内外と日本海、東シナ海に空母打撃群を1-3個程度配備している。これがいわゆる空母のプレゼンスで、いつでも必要な時に、必要な種類の攻撃を、必要なだけの規模で行える事で敵性国家や敵性地域の近くの公海上から威嚇しながら、場合によっては情報収集を行うことを指している。この複数の空母打撃群による威嚇は強力で、国際社会におけるアメリカ大統領の力の根源の大きな柱の1つとなっている。
原子力空母の配置について、その第一義的な意義を第50機動艦隊(第5空母群)司令官リチャード・レン少将は、その地域の軍事的安定による紛争発生の抑止にあるとしている。
アメリカ海軍では空母の大量動員能力を「サージ能力」(surge capability)と呼び、艦隊即応計画(Fleet Response Plan)の中心となる概念である。世界各地の紛争や戦争に対応して、30日以内に6個、90日以内にさらに2個の空母打撃群をすばやく大量に派遣できる 能力を確保する計画である。
アメリカ国内がテロ攻撃にさらされた後でも、その原子力空母に依存する「力の投射」戦略が今後のアメリカの平和を守り、アメリカ自身のプレゼンスを守りきれるのか、原子力空母外交の今後が注目される。