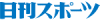教育を考えるシリーズの第2弾です。朝日新書「リベラルは死なない」からの抜粋です。
――――――――――――――――――
すべての人に質の高い教育を
支えあう社会を築き、労働者の生産性を高めるためには、すべての人に開かれた教育システムが不可欠である。すべての人に質の高い教育を受ける権利を保証しなくてはならないし、特に人生のスタートラインにいる子どもたちの教育機会の不平等は許されない。
さらに踏みこめば、親の所得格差が子どもの教育格差につながっている現状は、社会的公正の観点から望ましくない。同時に地域間格差や障がいの有無による格差も解消しなければならない。いずれにせよ、生まれによって子どもたちが不利益を被ることのない教育システムをつくることが、政治の役割であり、社会の責任なのである。
国際機関等の近年の研究は、格差拡大が経済成長の足を引っ張ることを明らかにしている。格差拡大や格差の固定化を防いで社会の流動性を担保し、「努力すれば報われる社会」を築くためにも教育は重要である。
以上の観点からすれば、塾や予備校に通い、幼稚園や小学校の「お受験」や中学受験をしなくては、質の高い教育を受けられない状況もまた許容できるものではない。親の所得に関係なく、すべての子どもに質の高い教育を提供するためには、やはり公教育の充実、および、私学助成の強化が必要不可欠である。
また、初等中等教育だけではなく、生涯学習や社会人の職業訓練・再教育にも政府がより重要な役割を果たすべきだ。
誰でもいつでも学べる環境は、国民にとって権利であり、より良い社会と国際競争力のある経済を築くうえでも重要な意味を持つ。また、技術革新のスピードが加速し、高校や大学で学んだ知識や技術がすぐに陳腐化してしまう現在の知識基盤社会においては、いつでも学び直せる場が生産性向上に不可欠である。
だからこそ、就学前教育から初等中等教育、高等教育から生涯学習や社会人向け職業教育まですべての世代に開かれた教育システムが必要なのだ。本章では、学ぶことを権利ととらえ、誰でもいつでも学べる場を提供する「日本型Education for All」を実現することを提唱したい。
義務教育段階の公教育の充実
すべての子どもの教育の質を向上させるには、親の所得に関係なく受けられる公教育(特に初中等教育)の充実が最優先課題である。日本は家計の教育費負担が重たいが、その一因が小中学校の塾通いや予備校通いである。学習塾や予備校といった学校外の私的教育機関に頼らなくても十分な学力が身につく公教育が求められる。
初等中等教育の質を高め、子どもたちの学びを高度化させるには、教員自身が自己研鑽の時間と機会を持ち、深い教養と広い知識を身につけることが必要条件である。
そのためには、現職教員が学び直す機会を増やし、新しい教育理論や教材にふれる環境を整える必要がある。さらには、長期休業中の研修や現職教員の大学院等での研修を拡充し、「学び続ける先生」をサポートする仕組みを整えなければならない。
みなさんも耳にされたことがあるかもしれない。現場の教員の過酷な勤務実態が報告され、教員が子どもたちと向き合う時間が十分持てていない。この状況は異常である。
教員が教えることに集中できるように、学校事務員やスクールソーシャルワーカー等の非教員のサポート体制を強化する必要がある。また、少人数教育や習熟度別授業を推進するには教員の絶対数が足りない。教員のワークライフバランスを回復するためにも教員増は不可欠である。
大学の教員養成課程の質を高めることも有益である。安倍政権のもとで国立大学の教員養成学部の削減が示唆されているが、現実はまったく逆であり、教員養成課程の充実が必要な状況である。教授法の改善という点でも、国立大学の教員養成学部における教育と研究の充実は重要である。
学校現場における非正規教員の増加は深刻な問題である。ふつうに考えて、同じ教室で同じように教えているのに給与水準が大幅に異なるのは健全ではないし、教員として経験を積み専門性を高めるうえで不安定な雇用は足かせになる。教員の質を高めるためにも、非正規教員の正規化を進めるべきである。
やむを得ず非正規教員を採用している背景には、人件費を抑制せざるを得ない予算状況がある。正規教員1人分の人件費で非正規教員を2名雇用するといった慣行が全国で広がっている。教育予算を増やし、OECD加盟国で最下位の公的教育支出(GDP比2.9%)をOECD平均の4.2%に少しでも近づけなければならない。
現在、経済界などの主張に沿って、小学校における英語教育が拡大されている。十分な準備もなく、小学校の英語教育を義務化するのは問題である。現在進められている小学校の英語教育の教科化については、外国語教育の専門家の間でも効果を疑問視する声が多い。
しかも、英語の教科化が進めば、国語や算数といった主要科目が削られる。あるいは、他の科目が削られずに単に英語の授業時間が増えるだけであれば、現場の教員と子どもたちの負担がさらに増え、その場合も弊害が大きい。
そもそも小学校の現職教員の大多数は、外国語教授法の訓練を受けていない。準備不足の教員が不得意な英語を教えることの悪影響も考慮されるべきである。小学校における強引な英語の教科化は、単に「英語嫌いの低年齢化」を招くだけだ。すべての子どもにとって必須の国語や算数などの基礎学力を向上させることこそが、本来の公教育の役割である。
*ご参考:井手英策編著 2019年「リベラルは死なない」朝日新書










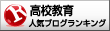


 l山内 康一
l山内 康一