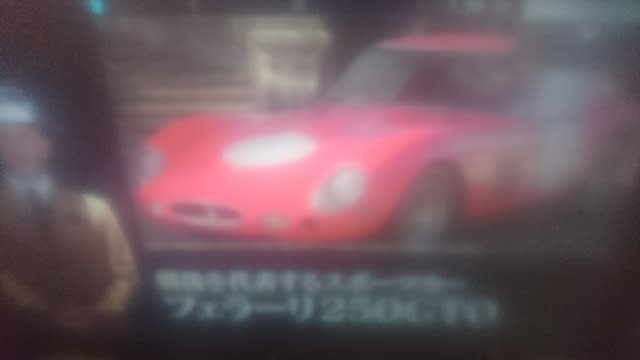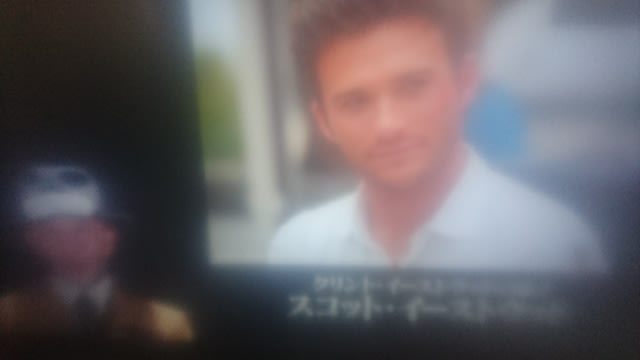読売新聞朝刊 日曜版の「よみほっと」から
「ニッポン絵ものがたり」の連載記事があります
今日2月7日は タイトルがサムライ大使で支倉常長像の絵(敬虔なクリスチャン姿の肖像画です)も
1613年仙台藩藩主の伊達政宗の命を受けて 洋式帆船サン・ファン・バウティスタ号でスペイン、ローマへ向かった支倉六右衛門常長
帰国したのは7年後
この旅に同行したルイス・ソテロ神父が後に九州で書いた手紙によれば ー常長は「敬虔のうちに死去」し、子供達に所領での布教は宣教師の保護を遺言した
この遺言を裏付けるように息子の常頼が宣教師をかくまっており (江戸時代 鎖国政策 キリシタン迫害 キリスト教は禁じられた)
常頼の弟や召使がキリスト教の信徒となっていたので1640年に処刑され家は断絶
後に仙台藩は常頼の息子に支倉家を再興させた
支倉家13代目の子孫となる常隆さんは「常長に大変な苦労をさせたとの伊達政宗の思いへの配慮があった」のではないかと
常隆さんは2014年 常長一行のグアダルキビル川遡上の航海に参加
(前年の2013年 当時皇太子だった天皇陛下が400周年の記念行事でコリア・デル・リオで桜を植樹 ハポンの姓の方々と交流)
宝塚歌劇団宙組はこの史実から想像の翼を広げ「エルハポン~イスパニアのサムライ」を上演した
舞台となったのはコリア・デル・リオの街
この街には「ハポン」を姓として名乗る人々がいる 実に600人ほど
「使節団の中で残留したサムライが先祖」との伝承を誇りにしてくれているそうだ
最大の理由は 欧州各地で支倉常長に接した人々が書き残した品格、賢明さへの称賛や「信頼され人を引きつける」などの描写
このハポン姓を名乗る人々の中に「サムライ審判」と呼ばれるホセさん(スペインサッカー1部リーグの審判さんだった)
ホセさんは何十年も常長の生涯を調べ
「困難極まる船旅を耐え 貿易交渉が不調に終わっても粛々と主君・伊達政宗のもとへ戻る そんな生き方に魅了された」
コリア・デル・リオの川岸には支倉常長の銅像もあると
セビリアを拠点に長年観光ガイドをされる今江克彦さんは
「鳥居や日本語の公園標識 商店の看板などがあり 随所へ日本への親愛の情を感じる」
コリア・デル・リオの街には 支倉常長が率いた施設にちなみ「慶長」というお酒も
原料の一部に米を使ったライスリキュールなのだそうです
小学生の頃 勝海舟の伝記で あの時代にアメリカまで咸臨丸でーと当時の人々に感動し感心しました
海が荒れれば船は沈みますー
それより前に 荒海越えて言葉も分からぬ国へ
よほど肝が据わっていなければ もはや死ぬ覚悟よりもっともっと凄い使命感
出航前の華やかな踊りから始まる「エルハポン~イスパニアのサムライ」
スペインとの交易交渉は成功しませんでしたが 海を越えて到着したこと
そんな自分達のことに触れる支倉常長を演じる寿つかささんのセリフがあります
常長「我らの旅は失敗であったと思うか」
内藤半十郎(演じたのは松風輝さん)
「さあ、それは ・・・。 口性ない人は、そう申すかもしれません」
常長「そうだな。・・・だが私は、失敗であったとは思わない。
少なくとも我々は、自ら船を築き、大海を越え、この地へ足を踏み入れた。
無論、その程度のこと、我らでなくとも、いずれ誰かが成し遂げたであろう。
しかし、誰かが踏み出さねばならぬ一歩であったことも、また事実だ。
我々の成果はきっと、この後へ繋がっていくはずだ」
夢を見た人々により 世界は広がり近くもなっていった
彼らが見た夢が現在に繋がっている
真心 誠実さ
人の心を打つ「何か」は幾百年経とうとも消えることはないのだなと