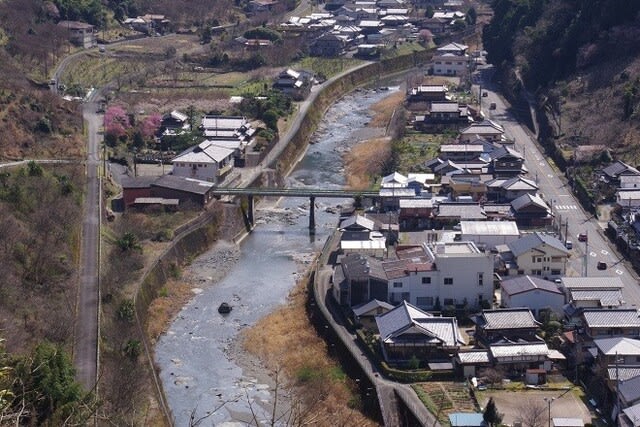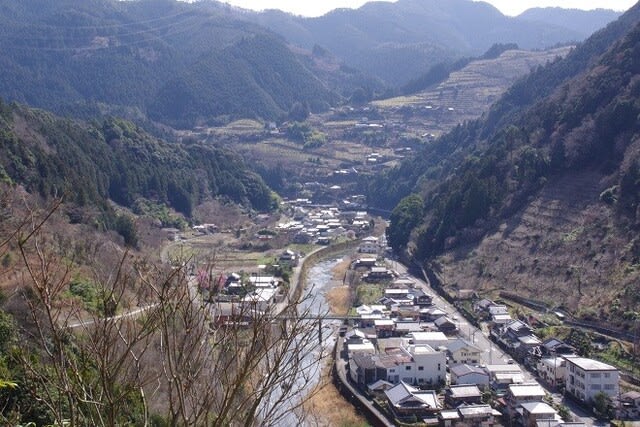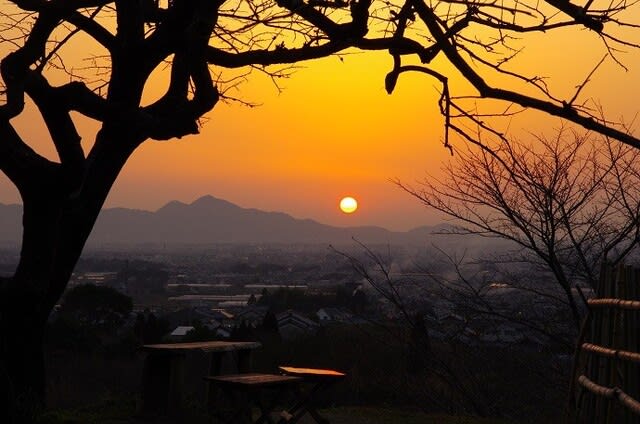.
相変わらずの二上山
今日はちょっとコースを変えて、長~い 長~ い 階段を歩いてきました。
ろくわたりの道から ~ 雌岳の西へ ~ 小さなピークを越えて ~ 少し下ったら、太子町のグランド方面から上ってくるコースと交差する、ここで東に向かい馬の背 ( 雄岳と雌岳の間 ) へ出る長~い階段がある、このコースを登る


こんな木の根っこを通り

小さなピークから下って行く

登山道の交差点、ここを右折して階段を上って行く






こんな長~い、階段~階段~階段を フーフーハアハアと

数えながら歩いた、495段目でやっと馬の背へ到着

馬の背の石柱
雌岳頂上まで 100m 雄岳頂上まで 600m

雌岳頂上近くより
あべのハルカスは中ほどに、今日もかなり霞んでる

山頂のさざんかは、盛りを過ぎたのも、まだ元気なのもいろいろ

今日の雌岳山頂は賑わっている

葛城山・金剛山が見える
木々が繁って視界が悪かったが、伐採されて見晴らしが良くなっている

雌岳山頂への階段はかなり傷んでたが、修復されてキレイになっている

下りの途中に石切場へ寄る、
明日香村・高松塚の石棺はここから切り出して運んだそうです

若い桜の木は控えめな感じに花を咲かせていた
長~い階段を歩いて 6160歩、今日もいい運動になりました
相変わらずの二上山
今日はちょっとコースを変えて、長~い 長~ い 階段を歩いてきました。
ろくわたりの道から ~ 雌岳の西へ ~ 小さなピークを越えて ~ 少し下ったら、太子町のグランド方面から上ってくるコースと交差する、ここで東に向かい馬の背 ( 雄岳と雌岳の間 ) へ出る長~い階段がある、このコースを登る


こんな木の根っこを通り

小さなピークから下って行く

登山道の交差点、ここを右折して階段を上って行く






こんな長~い、階段~階段~階段を フーフーハアハアと

数えながら歩いた、495段目でやっと馬の背へ到着

馬の背の石柱
雌岳頂上まで 100m 雄岳頂上まで 600m

雌岳頂上近くより
あべのハルカスは中ほどに、今日もかなり霞んでる

山頂のさざんかは、盛りを過ぎたのも、まだ元気なのもいろいろ

今日の雌岳山頂は賑わっている

葛城山・金剛山が見える
木々が繁って視界が悪かったが、伐採されて見晴らしが良くなっている

雌岳山頂への階段はかなり傷んでたが、修復されてキレイになっている

下りの途中に石切場へ寄る、
明日香村・高松塚の石棺はここから切り出して運んだそうです

若い桜の木は控えめな感じに花を咲かせていた
長~い階段を歩いて 6160歩、今日もいい運動になりました