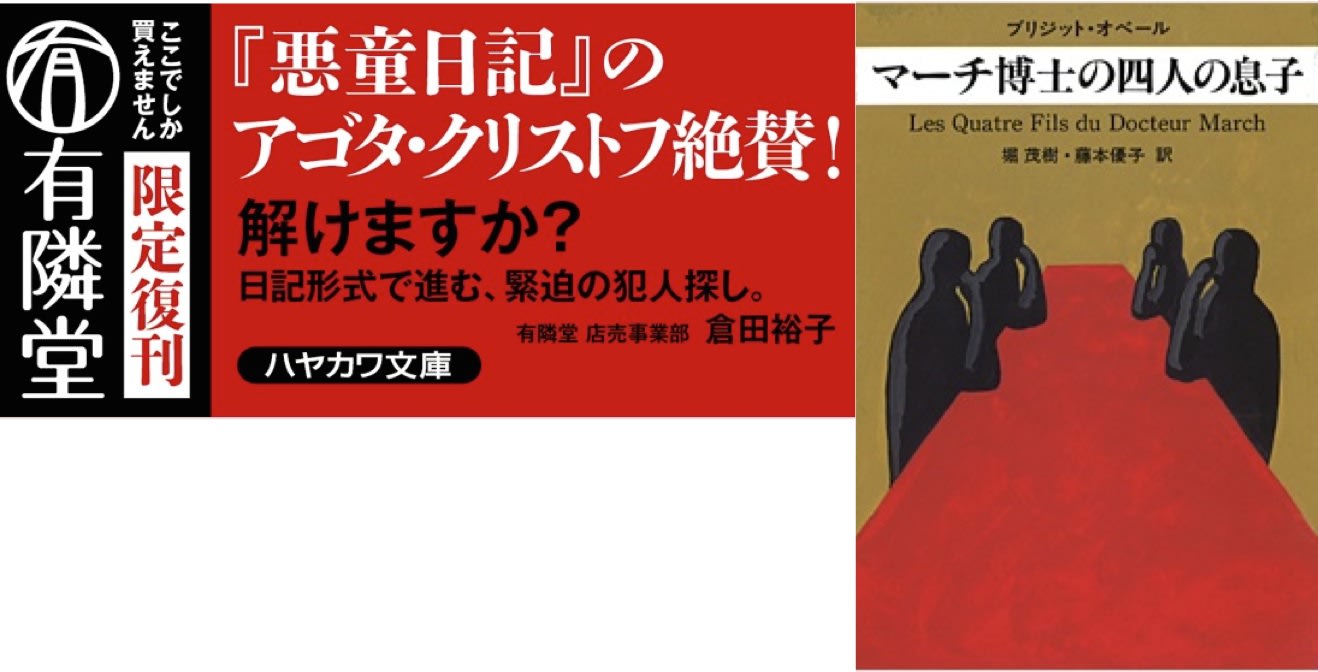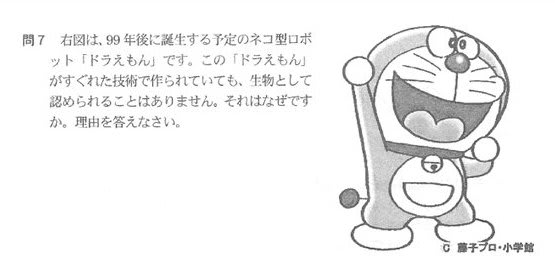ワイドショーでは小保方さんが佐村河内氏と交代しているが...
珍しく,佐村河内守こと新垣隆氏の音楽を正面から取り上げた文章.
「どこまでがドビュッシー(17)」青柳いずみこ.定価はあるが,書店で只で貰える雑誌,岩波書店の「図書」2014 年 4 月号の48ページ.
佐村河内名義の作品を演奏したり賞賛したりした音楽家・批評家はほとんど著者・青柳さんのお友達らしい.これらの作品群自体は,「オリジナリティには欠けるものの.弾き手が感情移入しやすいメロディと琴線にふれるハーモニーに満ちており,素直に観客の心に届く」とおっしゃる.
青柳さんが新垣氏本来の作風はどんなものかと,YouTubeで「インヴェンション または倒置法III」と「Suburb」を視聴されたとのこと.根本にあるのは,聴衆を陶酔させておいてわざとそれをぶちこわす「天の邪鬼」精神.まるで不条理劇のような展開に,客席からは笑い声がもれる.新垣氏は,佐村河内名義では聴衆を泣かせ,本人名義では人を笑わせる,すごい二重人格ぶり,という評価だ.
嫌いではないが,照れくさい音楽のためには,新垣氏にとって「佐村河内」はちょうどいい隠れ蓑だったということ?
本職 ? の上記2曲は 16 トンも視聴したが,途中で飽きてしまった.でもライブなら違うかも.演奏する方が面白そうだが,どうせなら自分のアイデアでやるほうが良い.
青柳さんの文章らしく,タイトルどおりに,最後はドビュッシーが登場.彼もまたジキルとハイドのような分裂した性格で知られたのだそうだ.死後原稿が発見されたオペラ「ロドリーグとシメーヌ」は,リリカルで感動的.中でもロドリーグとシメーヌによる二重唱はワーグナーのトリスタンとイゾルデのそれにも劣らない濃厚なロマンティシズムを湛えている...とのことである.