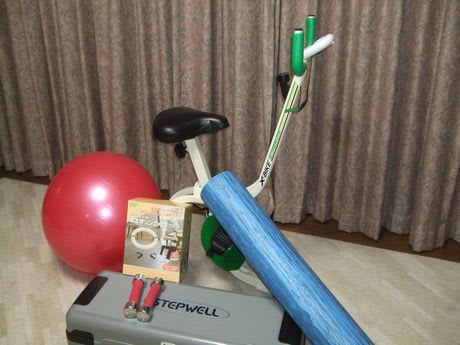2014年1月21日(火)曇 3.7℃~-4.8℃
会津若松市の下町 西若松駅周辺は14世紀に鎌倉から葦名氏がやってきて以来、松平氏まで会津西街道(日光街道)や越後街道などに通じ賑わっていた。特に戊辰戦争(会津戦争)では、西軍に勝った唯一つの場所である。また、山川太蔵が小松の彼岸獅子を先頭にして鶴ヶ城へ帰城する際通った道である。昨日の健康ウオークのコースは下記古戦場などを中心にして散策した。


秀長寺
永正二年(1505)十月下旬より塩川において合戦があり、芦名の臣富田志摩守秀長は戦死した。家嗣右馬允時長亡父の菩提を弔うべく小田山城在勤の下屋敷をもって天文六年(1537)に一宇の草庵を建立して水月庵と号した。蒲生氏の頃、猪苗代に隣松院という一宇があった。住僧の伝廊禅師は当時猪苗代城主であった蒲生の長臣町野左近とは心を開いた友であった。その後隣松院は度々の火災に見舞われて再建に行き詰まり、禅師は水月庵に来て仮住まいの身となった。町野左近はその頃白河の城主に遷っていたが、これを深く憂えて領主蒲生秀行に請い、慶長十年(1605)この水月庵に寺地を加えて一宇を創建し、禅師を住まわせて町野家の菩提寺として雲龍山秀長寺と号した。

秀長寺古戦場
慶応四年(明治元年・1868)八月二十三日以来、籠城戦中の若松城下は東西両軍の攻防戦が激戦となってきた。九月五日城下にて奮戦する会津藩兵の野戦軍総督佐川官兵衛は、日光口(会津西街道)より侵入してきた西軍が大内宿から本郷を経て、大川を渡り、城下に攻め入ってくることを偵察した。官兵衛は、配下の軍勢を片原町柳原などに伏兵として置き、自身は200余名の藩兵を指揮し、会津藩砲兵隊と協力して秀長寺の西側に散在する民家に、また、林や草むらに伏せさせた。加えて、南口外郭門の守備兵と援軍の水戸藩兵に材木町の南部付近一帯を守備させた。早朝、薩摩・肥前・中津・大田原・館林・人吉・宇都宮・芸州・黒羽・大垣の十藩の兵が押し寄せ住吉川原一帯までに渡る激戦となった。しかし、西軍は周章狼狽し、退路を失って銃砲弾薬や金円糧食及び毛布類等を遺棄して敗退した。 佐川官兵衛直清歌碑がある。
※世が明治と変わる僅か3日前の慶応4年9月5日、この付近で大激戦がありました。世に言う「材木町の戦い」あるいは「秀長寺の戦い」「住吉河原の激戦」です。
会津方の指揮官は佐川官兵衛で、長命寺の戦いで破れて以降苦戦続きであった会津軍は遂にこの戦いで大勝利をおさめたのでありました。結果、会津藩は城への補給路を確保し、これ以降の籠城戦を可能たらしめたのです。この勝利以降、城内の籠城兵が気軽に城外へ兵糧を確保に行くことが出来る様になったのであります
会津若松市の下町 西若松駅周辺は14世紀に鎌倉から葦名氏がやってきて以来、松平氏まで会津西街道(日光街道)や越後街道などに通じ賑わっていた。特に戊辰戦争(会津戦争)では、西軍に勝った唯一つの場所である。また、山川太蔵が小松の彼岸獅子を先頭にして鶴ヶ城へ帰城する際通った道である。昨日の健康ウオークのコースは下記古戦場などを中心にして散策した。


秀長寺
永正二年(1505)十月下旬より塩川において合戦があり、芦名の臣富田志摩守秀長は戦死した。家嗣右馬允時長亡父の菩提を弔うべく小田山城在勤の下屋敷をもって天文六年(1537)に一宇の草庵を建立して水月庵と号した。蒲生氏の頃、猪苗代に隣松院という一宇があった。住僧の伝廊禅師は当時猪苗代城主であった蒲生の長臣町野左近とは心を開いた友であった。その後隣松院は度々の火災に見舞われて再建に行き詰まり、禅師は水月庵に来て仮住まいの身となった。町野左近はその頃白河の城主に遷っていたが、これを深く憂えて領主蒲生秀行に請い、慶長十年(1605)この水月庵に寺地を加えて一宇を創建し、禅師を住まわせて町野家の菩提寺として雲龍山秀長寺と号した。

秀長寺古戦場
慶応四年(明治元年・1868)八月二十三日以来、籠城戦中の若松城下は東西両軍の攻防戦が激戦となってきた。九月五日城下にて奮戦する会津藩兵の野戦軍総督佐川官兵衛は、日光口(会津西街道)より侵入してきた西軍が大内宿から本郷を経て、大川を渡り、城下に攻め入ってくることを偵察した。官兵衛は、配下の軍勢を片原町柳原などに伏兵として置き、自身は200余名の藩兵を指揮し、会津藩砲兵隊と協力して秀長寺の西側に散在する民家に、また、林や草むらに伏せさせた。加えて、南口外郭門の守備兵と援軍の水戸藩兵に材木町の南部付近一帯を守備させた。早朝、薩摩・肥前・中津・大田原・館林・人吉・宇都宮・芸州・黒羽・大垣の十藩の兵が押し寄せ住吉川原一帯までに渡る激戦となった。しかし、西軍は周章狼狽し、退路を失って銃砲弾薬や金円糧食及び毛布類等を遺棄して敗退した。 佐川官兵衛直清歌碑がある。
※世が明治と変わる僅か3日前の慶応4年9月5日、この付近で大激戦がありました。世に言う「材木町の戦い」あるいは「秀長寺の戦い」「住吉河原の激戦」です。
会津方の指揮官は佐川官兵衛で、長命寺の戦いで破れて以降苦戦続きであった会津軍は遂にこの戦いで大勝利をおさめたのでありました。結果、会津藩は城への補給路を確保し、これ以降の籠城戦を可能たらしめたのです。この勝利以降、城内の籠城兵が気軽に城外へ兵糧を確保に行くことが出来る様になったのであります