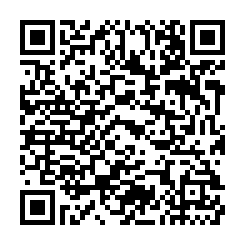JRが国鉄と呼ばれていた頃、まだ蒸気機関車が主流だった頃は、どんな小さな駅にも駅員がいた。
駅舎も小さいながらも、駅員室や窓口があり、待合室にはベンチがあった。
壁には観光ポスターや防犯ポスターが貼られていた。
駅の前には必ず蘇鉄が植えられていたり、小さな雑貨屋があった。
国鉄がJRに名前を変える前後から、小さな駅は無人駅になっていった。
第3セクターとなった、九州の辺境の実家の近くの駅も、今は往時の面影は消え、駅舎も改札もなく、プラットホームと駅名表示板があるだけの侘しい佇まいだ。
その昔は、集団就職で都会に出て行く子らも、地元の人々の見送りを受けて、その駅から旅立っていった。
私も京都の大学への入学時には、ちっぽけなセンチメンタリズムを胸に、その駅から旅立っていった。
親父のアルバムには、駅舎をバックにした、戦時中の出征兵士の壮行の写真もあった。
今や1時間か2時間に1本の電車が通るだけだ。
それは国鉄の凋落を物語っているのか、時代の流れを物語っているのか。
駅舎も小さいながらも、駅員室や窓口があり、待合室にはベンチがあった。
壁には観光ポスターや防犯ポスターが貼られていた。
駅の前には必ず蘇鉄が植えられていたり、小さな雑貨屋があった。
国鉄がJRに名前を変える前後から、小さな駅は無人駅になっていった。
第3セクターとなった、九州の辺境の実家の近くの駅も、今は往時の面影は消え、駅舎も改札もなく、プラットホームと駅名表示板があるだけの侘しい佇まいだ。
その昔は、集団就職で都会に出て行く子らも、地元の人々の見送りを受けて、その駅から旅立っていった。
私も京都の大学への入学時には、ちっぽけなセンチメンタリズムを胸に、その駅から旅立っていった。
親父のアルバムには、駅舎をバックにした、戦時中の出征兵士の壮行の写真もあった。
今や1時間か2時間に1本の電車が通るだけだ。
それは国鉄の凋落を物語っているのか、時代の流れを物語っているのか。
狙いは読後感。読めばわかる、あるいは読んでもわからないかもしれないが、なんとなく心の片隅に残る奇妙な違和感。ありきたりで普通を装った妙な安心感。 そんな小説を、Amazon Kindle Storeに30数冊アップしています。★★ 拙著電子書籍ラインナップ・ここから買えます。
読後のカスタマーレビューをいただけたら幸いです。