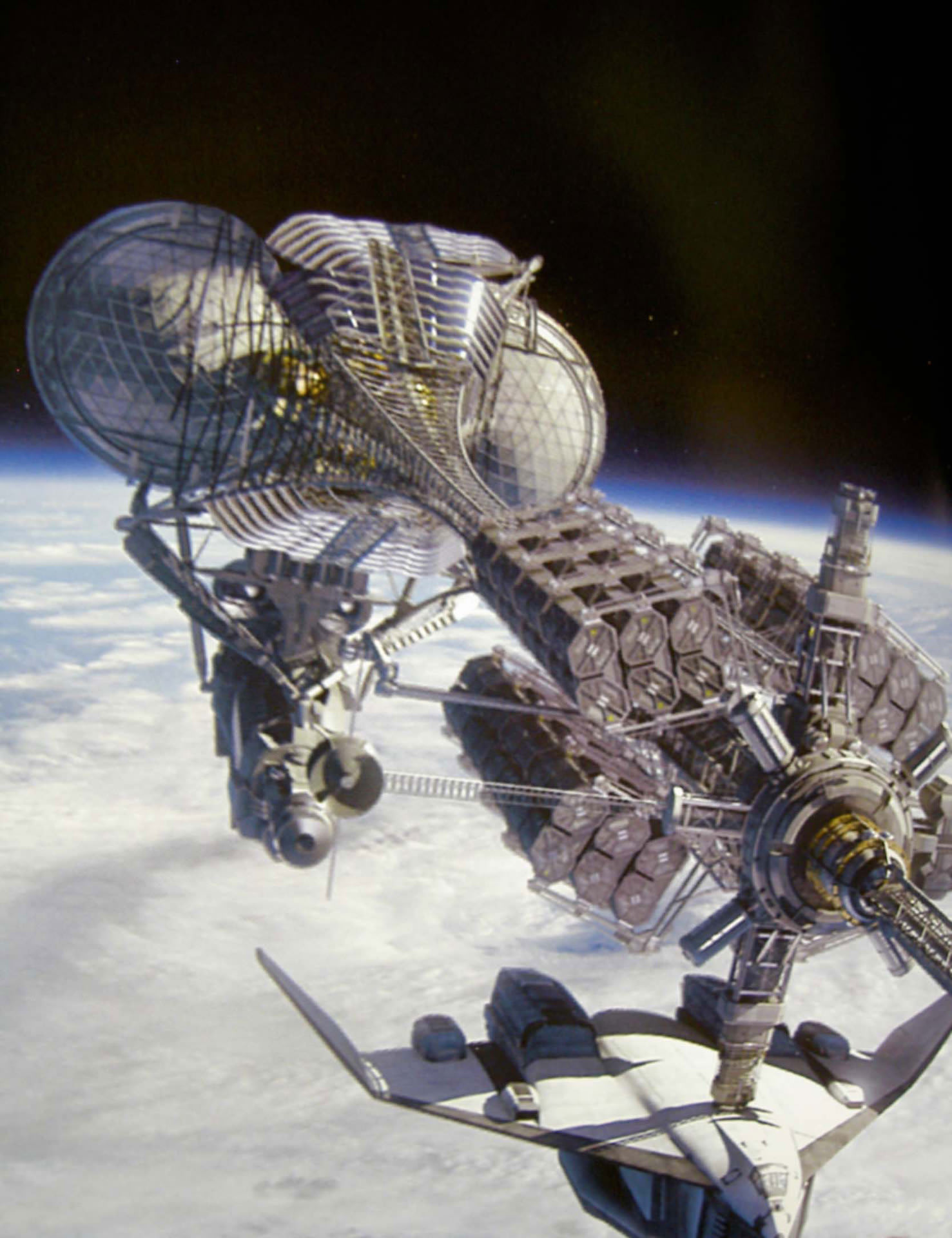斜里川の魚道付きダム付近にみられた悲惨なオショロコマの病気
20XX-9-20 晴れ
しばらくぶりで斜里川のこの水域に入ってみたのだが、いつのまにか新たに大きな魚道付きダムが二基出来て、その上流には見事に大きなダム湖ができていた。
ダム湖はこのところの好天で当然ながら水温がかなり上昇している。ダム湖に5-6匹の小さなオショロコマの群がゆっくりと回遊しているのが見えたが活性は低くエサは追わない。
ダム下で釣るとオショロコマはまあまあ釣れたが元気なく概して小型。
ぶよぶよした白っぽいゼリー状隆起性斑点の皮膚病をもつオショロコマが1割くらいに見られ(水カビ病と仮称する)、こんなことは初めてだ。
何かがおかしい。いずれにしても斜里川のオショロコマに異変がおきているようだ。
ダム湖の下は魚道の両脇に流れがよどむたまり水の水域があり、茶褐色のヘドロ状堆積があり汚い。そこの水温は20℃もある。
この汚水域からは本流に汚い水が流れ込んでいる。ダム下は水温14℃と高く低水温を好むオショロコマの生息にはちょっときついといえようか。
この魚道付きダムに由来する汚水と高水温がオショロコマの水カビ病と何らかの関係があるかも知れない。









このあたりは悲惨な水カビ病オショロコマが多い。






ダムの上は一見美しい風景だが湖底にはヘドロ状堆積ができはじめ、場所によっては異臭を発する。ダム湖のため、本来冷涼であった渓流の水温が上昇する。このような水域をnative 渓流魚は嫌い、一般には放流されたニジマスくらいしか泳いでいない。

魚道付きダム周囲に多くみられるヘドロ堆積がめだつところ。






大型ダム建設後の河川環境の悪化パターンは枚挙にいとまがないが、そのほんの一例につき述べてみましょう。たとえば二風谷ダムからのドブ臭い悪臭。
一般的に砂防ダムができるとその上流には、最初に程度の差はあれダム湖ができる。最初は美しくさえ見えるダム湖はやがてヘドロ状の土砂堆積が続いて泥沼状態になりやがてダムは埋まってしまう。
そこは、ずぶずぶと埋まってしまうため当初は歩くことも出来ない。この過程でヘドロ状土砂堆積に腐敗が起こってまるでドブみたいな悪臭をだしているところも多い。巨大ダムではダム機能を維持するため、このヘドロ状堆積を排泄すれば、実際に黒部ダムや日置ダムなどでみられるように下流域や海に重大な影響が懸念される。
最近、巨費をかけてダムを建造後、あっという間に土砂で埋まってしまい、このお粗末ダム建設により水害の頻度が逆に急増している北海道沙流郡の二風谷ダム(裁判で違法ダムとされた)のほとりに住む人たちも、この埋まってしまったダム湖からのドブ臭い悪臭に辟易しているという。
その結果、当初の予測通りに清流とうたわれた沙流川は完全に死んでしまった。
そんなことには目もくれずダム建造にともなう諸々の巨大利権に群がる(それが見え見えなのが悲しい)勢力が、その上流にさらに平取ダムを造ろうとしているのは悲しいことだ。
日本中で長年慣習的に行われてきたダム建造の悪しき構図を如実にさらけだしている。
川が暴れる真の原因はまったく別のところにあることは我が家のわんこでも知っている。
民主党政権の時代、この悪しき慣習にくさびが入ったかにみえたが、これも単なる経済的理由からきていたに過ぎないのはちょっとさみしい。
今後は少なくとも治水に関してはダム以外の根本的な方策を真剣に検討する時期になったのではなかろうか。
私は道内各地の渓流で欠陥だらけの魚道付きダムをみてきたがいわゆる魚道さえ作れば物事が多少なりとも解決するという安易短絡的発想は極めて危険と断言する。魚道は流木や土砂などで、そのままではすぐに機能しなくなる。維持管理をきちんと行うのは魚道をつくるよりも、もっともっと大変だろう。
魚道付きダムによるその後の環境変化も重大だ。たとえば斜里川源流域などでは魚道付きダムのためダム周辺によどんだ高水温の汚水水域が増え、そのせいかオショロコマにこれまで見たこともない前述の悲惨な皮膚病が急速に蔓延しつつある。
この現象は斜里川と良く似た構造の羅臼川の魚道付きダム群周囲でも起こりうる。実際に知床の魚道付きダムのある渓流では斜里川と同じ水カビ病がみられる水域がある。そのうちこのブログでご紹介します。斜里川ではこの皮膚病はヤマベにも広がりつつある。