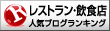2006年 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ映画。
ボスニアという国は、我々からあまりに遠い。
東欧の国というくらいの認識で、私にはそのイメージすら浮かんでこない。
確か、80年代にサラエボ・オリンピックが開かれ、共産圏で初めての冬季オリンピックということで話題になったような…
1992年、ユーゴスラヴィアが解体して行く中で勃発したボスニアの内戦は95年まで続いたが、死者は20万人、難民は200万人も発生したのだそうです。
イスラム教徒のムスリム人、セルビア正教徒のセルビア人、カトリック教徒のクロアチア人、その宗教や民族が憎みあい反発しての戦いだったと。
驚くべきは、その時民族浄化という名目で2万人の女性がレイプされたということ。
「ボスニアの花」は、その時レイプされて生まれてきた娘と、その母親の物語です。
2006年ベルリン国際映画祭で金熊賞(グランプリ)を受賞。
映画の中で、戦争や暴力的なシーンは一切ありません。
社会的な説明も、声高な訴えもありません。
ただ、貧しい中で必死に娘を育てる母エスマと、12歳の娘サラの日常を淡々と描いているだけです。しかしサラは多感な年頃になってきて、自分の父親、出生に関して疑問を持つようになってしまった。サラがエスマに向かって「私は父さんに似ている?」と問うシーンがあります。なんと残酷な質問でしょう…
エスマが受けた陵辱は、しかも突発的な犯罪ではない。
「毎日何人にもレイプされた。おなかが大きくなってからも奴等は毎日レイプした。」
そうしてエスマは妊娠に絶望して
「おなかを思い切り拳で叩いた」のだけれども、流産しなかったのです。
ところが、生まれ出てきた我が子を見て
「こんな美しいものが世の中にあるか」と感動して、育てることにしたのでした…
民族浄化という恐ろしい言葉は昔からあったのだろうかと見てみたら
Wikiによると
”民族浄化(ethnic cleansing)は、複数の民族集団が共存する地域において、
ある民族集団が別の民族集団を強制移住、大量虐殺、迫害による難民化などの手段によってその地域から排除しようとする政策。
特に強姦や強制妊娠などを伴う民族抑圧を指して言う場合もある。
1990年代に内戦中の旧ユーゴスラビアのメディアに頻繁に使用されたセルビア語を翻訳したもので、1992年頃から世界の主要メディアでも広く使用されるようになった。”のだそうです。
以前、プロテスタントのアメリカ人と話していて驚いたことがあります。
彼らは基本的に人工妊娠中絶に反対なのだそうですが、レイプされた場合でも原則は変わらないというのです。
生まれてくる子供には罪はないのだから、と。
私にはとてもそこまで思えない。
この映画でも、出生の秘密を知ってしまった少女サラは、この先どんなに苦しむでしょう。サラを心から愛するエスマも、かつて受けた傷は一生忘れることができない。
それでもラストシーンのサラの微笑みは、何よりもの救いでした。
ちなみに、現在サラエボオリンピックのメインスタジアムは、
ボスニア紛争で破壊され、紛争で亡くなった人々の墓地になっているのだそうです。
「サラエボの花」
ボスニアという国は、我々からあまりに遠い。
東欧の国というくらいの認識で、私にはそのイメージすら浮かんでこない。
確か、80年代にサラエボ・オリンピックが開かれ、共産圏で初めての冬季オリンピックということで話題になったような…
1992年、ユーゴスラヴィアが解体して行く中で勃発したボスニアの内戦は95年まで続いたが、死者は20万人、難民は200万人も発生したのだそうです。
イスラム教徒のムスリム人、セルビア正教徒のセルビア人、カトリック教徒のクロアチア人、その宗教や民族が憎みあい反発しての戦いだったと。
驚くべきは、その時民族浄化という名目で2万人の女性がレイプされたということ。
「ボスニアの花」は、その時レイプされて生まれてきた娘と、その母親の物語です。
2006年ベルリン国際映画祭で金熊賞(グランプリ)を受賞。
映画の中で、戦争や暴力的なシーンは一切ありません。
社会的な説明も、声高な訴えもありません。
ただ、貧しい中で必死に娘を育てる母エスマと、12歳の娘サラの日常を淡々と描いているだけです。しかしサラは多感な年頃になってきて、自分の父親、出生に関して疑問を持つようになってしまった。サラがエスマに向かって「私は父さんに似ている?」と問うシーンがあります。なんと残酷な質問でしょう…
エスマが受けた陵辱は、しかも突発的な犯罪ではない。
「毎日何人にもレイプされた。おなかが大きくなってからも奴等は毎日レイプした。」
そうしてエスマは妊娠に絶望して
「おなかを思い切り拳で叩いた」のだけれども、流産しなかったのです。
ところが、生まれ出てきた我が子を見て
「こんな美しいものが世の中にあるか」と感動して、育てることにしたのでした…
民族浄化という恐ろしい言葉は昔からあったのだろうかと見てみたら
Wikiによると
”民族浄化(ethnic cleansing)は、複数の民族集団が共存する地域において、
ある民族集団が別の民族集団を強制移住、大量虐殺、迫害による難民化などの手段によってその地域から排除しようとする政策。
特に強姦や強制妊娠などを伴う民族抑圧を指して言う場合もある。
1990年代に内戦中の旧ユーゴスラビアのメディアに頻繁に使用されたセルビア語を翻訳したもので、1992年頃から世界の主要メディアでも広く使用されるようになった。”のだそうです。
以前、プロテスタントのアメリカ人と話していて驚いたことがあります。
彼らは基本的に人工妊娠中絶に反対なのだそうですが、レイプされた場合でも原則は変わらないというのです。
生まれてくる子供には罪はないのだから、と。
私にはとてもそこまで思えない。
この映画でも、出生の秘密を知ってしまった少女サラは、この先どんなに苦しむでしょう。サラを心から愛するエスマも、かつて受けた傷は一生忘れることができない。
それでもラストシーンのサラの微笑みは、何よりもの救いでした。
ちなみに、現在サラエボオリンピックのメインスタジアムは、
ボスニア紛争で破壊され、紛争で亡くなった人々の墓地になっているのだそうです。
「サラエボの花」