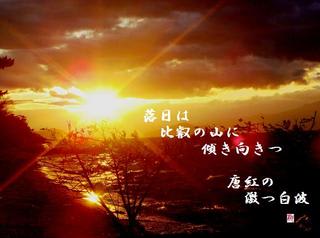落日は 比叡の山に 傾き向きつ 唐紅の 激つ白波 
【反物質の閉じこめに成功?!】
 山崎泰規
山崎泰規
ビックなニュースが飛び込む。反陽子
(陽子の反粒子)と陽電子が結合した
反水素原子を作り強い磁場を発生する
磁気瓶に38個閉じ込めることに、理化
学研究所と東京大学が参加する国際チ
ームが成功したというのだ。
スイスのジュネーブ郊外にある世界最
大の素粒子物理学研究所、欧州合同原
子核研究機関(CERN)の反陽子減速器
で実験し、電気的に中性である「反物
質」を捕らえた世界初の成果となる。
理研基幹研究所のダニエル・デ・ミラ
ンダシルベイラ客員研究員、山崎泰規
上席研究員(東大特任教授)らが、米
国や英国、カナダなど8カ国で構成す
る国際共同研究チームで実験した。
anti-matter what is it ?
反物質の代表格である反水素原子を捕
らえてその性質を測定し、対応する水
素原子と比べて物質と反物質の振る舞
いに違いが見つかれば、物理学で最も
基本的だと考えられている対称性(CP
T 対称性)が破れていることになる。
この宇宙はビッグバンで始まった
と信じるに足るいくつもの証拠が
ある。同時に、これまでのところ
様々な物理量についてCPT(Charge,
Parity, Time)対称性が高い精度で保
存していることも知られている。
多くの理論的取り扱いも、CPT対
称性が保存するような枠組みのも
とに構築されている。これを信じ
ると、ビッグバンでは物質と反物
質が等量生成されたはずだと結論
できる。一方、これまでの観測か
ら、我々の視野に入っている宇宙
は物質から成り立っていて、物質
-反物質間の対称性は破れている
ように見える。この「消えた反物
質」の不思議は様々に議論されて
いるが、一つの有力な仮説がCPT
対称性の破れである。CPT対称性
はペアを組む物質と反物質は、質
量や電荷(の大きさ)、寿命等の
物理的性質が全く同じであること
を主張するので、まずなすべきは、
両者の間に違いがあるか、あると
すればどの程度かを実験的に確か
めることである(中略)さて、C
PT対称性は破れているとしても
ごく僅かだと予想されるので、C
PT対称性のテストには高い精度が
要求される。高精度を実現するた
めには長い観測時間が必要で、従
って、ほぼ静止し極低温にある反
物質を大量に生成する必要がある。
この目的に最適の反物質が反水素
原子である(上図1参照)。反水
素原子は真空中で安定であり、比
較対象とすべき水素原子はその分
光学的性質が非常に高い精度で知
られているためである(1S-2S遷
移エネルギーは14桁、基底状態の
超微細分裂は12桁の精度で決定さ
れている)。
『山崎原子物理研究室』
【麹文化の深耕】
デスクワーク主体で運動も食事もおろ
そかになっている。そんな時、日本の
食事は本当に重宝だ。ダイエットも兼
ねて1日2食だけは継続できているの
はその所為。味噌汁はいつも準備され
ているのだが、面倒くさいので最近は
納豆玉子かけご飯と昆布茶パウダーと
九条葱の刻み1膳とお茶だけのファス
トフードというわけだ(『朝から納豆
を食べる。』)。玉子は予め冷蔵庫か
ら取り出し1分程煮沸したお湯で暖め
ておく。炊飯器の技術レベルも格段に
進歩しているからそれを取り出し、納
豆、玉子、好みのパウダー・トッピン、
醤油で完成。食事後は水洗いし乾燥機
に入れ、玉子の殻を家庭菜園の「EM
菌×油糟(米糠)」堆肥に使えば『デ
ジタル革命』時代の衛生栄養環境シス
テム工学のモデルが実現する。
ところで、日本酒、味噌、醤油、酢、
みりんなどの伝統的な調味料、そして、
野菜や魚を発酵させた様々な食品は日
本の食文化の根幹で微生物たちの働き
の発酵過程を経たもの。とりわけ、日
本の食文化の根幹を支える「麹」は身
近かな発酵文化だ。しかし、日本酒の
消費の衰退が著しく、1972年の日本酒
消費量は約130万㌔㍑→2008年には約
50万㌔㍑と半分以下に激減。一方、海
外での日本酒の消費量は飛躍し、日本
酒の輸出量をみると2008年は1.2万㌔㍑
と10年間に1.7倍にもなっている。ま
た、米国、中国、オーストラリア、ブ
ラジルなど海外でも日本酒が生産され
4.6万㌔㍑と推定されている(外国で
消費されている清酒は、合計5.8万㌔㍑)。
となり、国内消費の1割を超している。
この様に、微生物を用いた発酵の分野
は、常に世界をリードする分野であっ
たし、これまでに多くの成果が得られ
ている。特に高コレステロール血症治
療薬(スタチン)と免疫抑制剤(FK506)
の発見と発酵生産は特筆されるべきも
のがあり、アミノ酸発酵、核酸発酵とと
もにノーベル賞受賞の最右翼候補であ
ることに難くなく世界的な「発酵文化」
の振興に期待したい。
ところで、郷社の世話活動から日本酒
を飲む機会が多くなったが、どうも昔
から悪酔いをしやすく敬遠勝ちだった
のだが、それだけでなく、沢山飲むと
後味に嫌みが残ることもその理由だと
いうことに気が付き、カクテルするこ
とでそれがなくなることに成功した(
他のひとにも言えるかというと定かで
ないが、酒豪の先輩もこれ以上飲めな
いという時は麦酒カクテルしていたと
いう記憶が残っている)。作り方は簡
単、日本酒10に対し麦酒1~3を加え軽
くステアするだけで、キリッとした飲
み口になり御神酒も進むというわけだ。
【水素酸化酵素の産業利用】※
水素酸化反応は環境汚染物質を生じな
いので、徹生物の好気的水素代謝を利
用したバイオプロセスは環境調和型物
質生産法としては理想的だ。水素酸化
酵素ヒドロゲナーゼは燃料電池触媒や
水素生産への利用が可能な重要な生物
資源であり、好気性水素酸化細菌から
は空気中での酸化失活に強く、触媒活
性と安定性に優れるものが見いだされ
ている。ヒドロゲナーゼの分子エンジ
ニアリングの可能性も示されてきた。
水素利用バイオプロセスによる水素
を副原料とした光学活性アルコール
の合成
【水素利用バイオプロセスと有用性】
水素細菌の水素酸化反応を行う酵素ヒ
ドロゲナーゼは、細胞膜の電子伝達系
と共役してATP生成に関与する膜結合
型ヒドロゲナーゼ(Membrane-bound hy-
drogenase : MBH)と、水素の酸化により
ピリジン補酵素を還元する可溶性ヒド
ロゲナーゼ(Soluble hydrogenase : SH)が
知られる。水素細菌はバイオプロセス
反応の駆動力であるATPやNAD(P)Hを水
素ガスの酸化によって供給できるため、
産業上有用な反応を行う酵素と共役さ
せ、水素を利用した物質変換が可能と
考えられる(以下のような優れた特徴
が期待できる)。
①環境汚染物質を生じない。
②反応制御が単純。
③ヒドロゲナーゼの高い触媒効率、優
れた反応駆動性をもつ。
④有機溶媒に溶けやすい。
⑤ヒドロゲナーゼの水素に対する高い
親和性は副生水素や廃棄物からの水
素利用を広げる。

【水素利用微生物触媒の開発と反応】
(1)クリーンエネルギー開発における
ヒドロゲナーゼ機能の有用性
ヒドロゲナーゼは水素の酸化反応、お
よび逆反応であるプロトンの還元によ
る水素生産反応を触媒する。水素酸化
反応は希少な白金触媒に替わる水素燃
料電池触媒として期待される。
ヒドロゲナーゼをグラフアイト電極に
固定化して得られる水素酸化電流を評
価し、白金と同等以上の触媒活性があ
ることを示している。プロトンの還元
反応は、例えば光化学反応による電子
の供給と組み合せることで、水の光分
解による水素生産を可能にする。緑藻
類では、光化学反応で生じた余剰還元
力を消費するためにこのような反応が
起こる。また、光化学タンパク質をア
ノード側電極に、ヒドロゲナーゼをカ
ソード側電極に固定化することで、各
機能性タンパク質をコンポーネントと
して扱う試みをしている。アノードに
光を照射することによって水から電子
を取り出し、カソード側での水素生産
に利用する仕組みでヒドロゲナーゼは
有用な機能を持つ生物資源である。
(2)水素細菌由来の
高安定性ヒドロゲナーゼ
ヒドロゲナーゼは活性中心の構成金属
によって[NiFe]型と[Fe]型に分けられ
る。[Fe]型は空気にさらされると活性
中心が酸化され、秒単位で活性が失わ
れるものが多い。[NiFe]型は比較的こ
のような酸化に強く、とりわけ好気的
な水素代謝を営む水素細菌からは耐酸
素性と触媒活性に優れた[NiFe]型ヒド
ロゲナーゼが見みられる。
(3)光化学系トヒドロゲナーゼ複合
体の創製による光水素生産の効率化
緑藻類やシアノバクテリアは光化学系
H(PSH)の働きで水分子の光分解を行う。
水から引き抜かれた電子は一連の電子
伝達反応と共役したATP生成(光リン酸
化)に利用され、さらに光化学系(PSI)
の働きで再び光励起を受けてフェレド
キシンを還元する。還元型フェレドキ
シンは様々な反応に電子を供給するが、
主に炭酸固定に必要なNADPHの生成に
利用される。余剰還元力となった場合
はヒドロゲナーゼまたはニトロゲナー
ゼによるプロトンの還元反応に使用さ
れ、水素ガスが発生する。
----------------------------------
※『低炭素社会をめざした水素酸化酵
素の産業利用』西原宏史(BSI)より