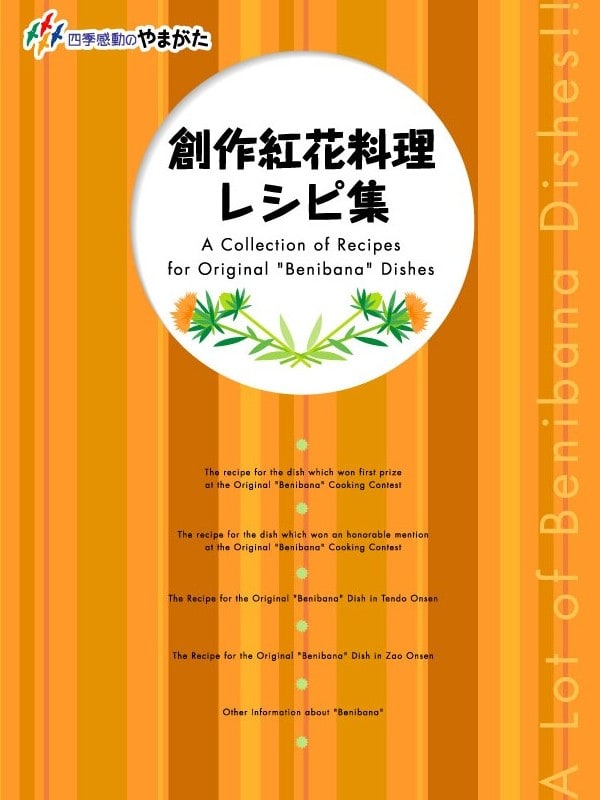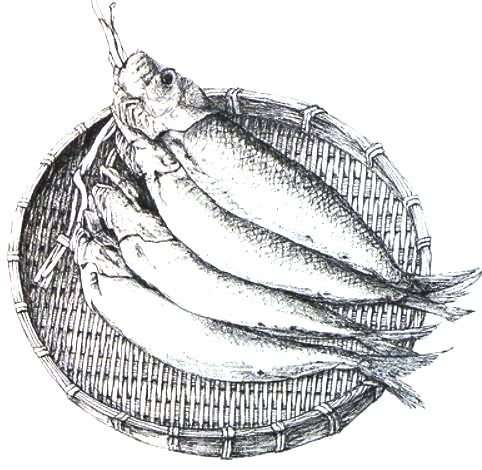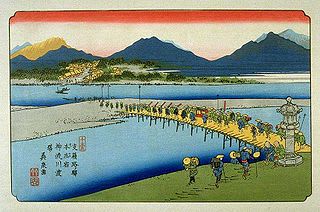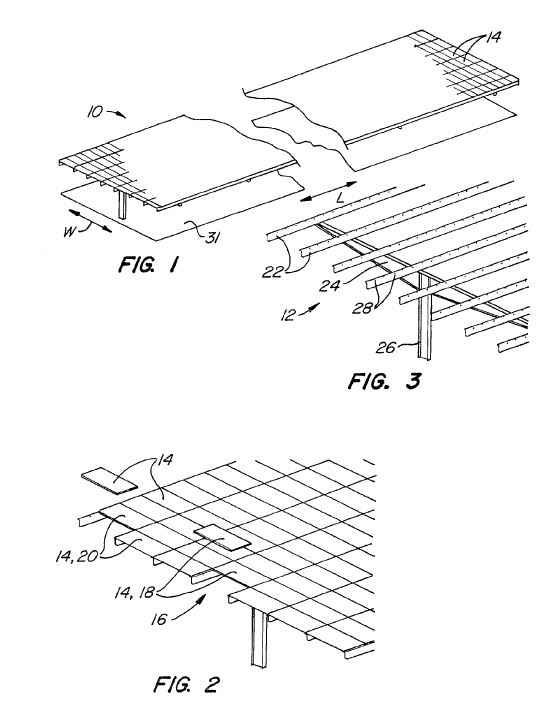【フード・ファントム・メナス(9)】
カニ
●ズワイガニは放射能汚染の心配がない
ズワイガニは、地域ごとに名前が付いている。島根県、鳥取県、兵庫県、京都府で
獲れると「松葉ガニ」、兵庫県でも津居山港で水揚げされると「津居山ガニ」、京都
府でも同人港に揚がると「間人ガニ」となる。福井県は「越前がに」、石川県は「加
能ガニ」である。
これらのブランドガニは、その近くの海で獲れたカニだから、放射能の心配はない。
ズワイガニは、茨城県から北の太平洋側でも獲れるが、ほんの少しだから、他の地
域のスーパーで見かけることはない。
国内の漁獲量4700tに対し、ロシアなどからの輸入は3000tを超えてい
る。輸人物も、放射能汚染の心配はない。
ベニズワイガニ
ベニズワイガニもほとんどが日本海側で獲れる。ズワイガニより安いので、庶民が
食べることが多いが、これも放射能の心配はない。
ロシアなどから輸入されているベニズワイガニも放射能の心配はない。
タラバガニ
タラバガニの主産地はオホーツク海だから、放射能の心配はない。
ロシア、アメリカ、ノルウェーからも輸入されているが、これらも心配ない。
花咲ガニ
花咲ガニは、ほとんどがオホーツク海から北に生息していた。ところが、稚ガニを
放流して、釧路でも多く獲れるようになっている。
釧路沖で獲れたマダラから低い値ではあるが放射能が検出されるようになっている
ので、花咲ガニを買うときは産地を確認しなければならない日が来るかもしれない。
毛ガニ
毛ガニの産地は、春はオホーツク海、夏は内浦湾(噴火湾)、秋は根室・釧路沿岸、
冬は十勝沿岸と変わっていく。今のところ毛ガニに放射能の心配はないが、太平洋に
面している産地は、これからどうなるかわからない。
消費量の半分はロシアからの輸人物だが、これも放射能の心配はない。
ワタリガニ(ガザミ)
ワタリガニは、日本中どこにでもいるカニで、かつては「カニ」といえばワタリガ
ニを指していた。ところが生息地の海岸がコンクリートで固められて漁獲量が減り、
カニといえば北海道がイメージされるようになった。
ワタリガニは、関東や東北で獲れたものは、放射能の不安がある。
ウナギ
●ネオニコチノイド系農薬がウナギを激減させている
ウナギの値段が高騰して、ウナギ専門店が次々と廃業している。
価格が上がった理由は、稚魚(シラスウナギ)が、日本で激減したからだ。
1960年代には全国で220tを超えたこともある漁獲量が、80年には100
tを割り、2010年からは10tを割り込んで、価格が高騰した。2011年の最
高額は、シラスウナギー匹が1000円を超えた。
これを買って育てるのが、ウナギの養殖だから、値上げは避けられない。
シラスウナギは20年以上前からヨーロッパ産が輸入されている。味は問題なく、
老舗のウナギ屋が、ヨーロッパ産のシラスウナギを自社の養鯉場で使っていたほどだ。
ところが、ヨーロッパでも、シラスウナギが減少して、ワシントン条約で2007年
に規制が決まり、2009年から輸出量が把握されるようになっている。
中国でもシラスウナギが不足して同じくヨーロッパから輸入している。この中国か
らウナギの成魚を輸入している日本は、今以上に輸入することはできない。
本来なら天然ウナギを食べたいところだが、2012年7月に利根川で獲れたウナ
ギから放射性セシウムが1㎏当たり二九ベクレル検出されている。今は、消費量の9
9%以上が静岡県以西か輸入の養殖物なので、放射能汚染の心配はない。天然ウナギ
の減少は、1960年代の後半にはすでに問題になっていた。
当時は、合成洗剤の泡が多摩川から飛んでいて、合成洗剤がウナギを減少させてい
た。川がきれいになると、一時期ではあるがシラスウナギも成魚も回復した。
農薬によるウナギ減少説も当初からあった。ウナギが減り始めた1960年代は、
何十年も残留する有機塩素系農薬の使用が日本では終焉を迎えようとして
いた。
1970年代からも、低毒性の有機リン系農薬が全盛になったが、この農薬は、魚
への毒性が強いので、天然ウナギを減らす主原因の一つだったと考えられる。
1990年代には、数ヵ月の残留性があり、毒性も浸通性もかなり高いネオニコチ
ノイド系農薬が登場し、田畑や山林で使う量が急激に増えた。この農薬は魚への毒性
が弱いので見逃されているが、ミツバチがいなくなっただけでなく、山や田畑に虫が
いなくなったように、水生昆虫に決定的なダメージを与えている。
水生昆虫がいなくなると、ウナギのエサが減るので、ウナギの成魚が減り、その結
果、シラスウナギが減るという悪循環に陥る。
ネオニコチノイド系農薬を禁止しないと、ウナギは成魚も稚魚も回復できない。
天然ウナギの減少などは気にせず、全国の川をすみずみまで護岸工事し、コンクリ
リートで固めて、海から日本列島に戻ったウナギを住みにくくしてきたことも、ウナ
ギを食べられなくしている一因であることは疑う余地がない。
ウナギを食べようと思うなら、ウナギの生育を阻害すると考えられるすべての要因
を同時に取り除いていかなければ、ウナギが復活することはないだろう。
●養殖ウナギは、抗菌剤などの薬剤が怖い
輸入ウナギからは、遺伝毒性と発ガン性があり、日本では使われなくなったニトロ
フラン類が毎年、検出されている。
ニトロフラン系の「合成抗菌剤」は、もともと日本で開発され、1974年までA
F2という食品添加物として許可され、多くの食品に使われていた。この合成殺菌料
は、将来にわたって日本人に遺伝病の被害を出すと遺伝学者たちが訴え、世論の支持
を得て禁止に追い込んだのだが、まだ大きな問題が残っていた。
家畜や養殖魚に、病気予防や肥育促進の効果があるとして、ニトロフラン系薬剤の
使用は、70年代の末まで増え続けたのだ。
その後、ニトロフラン系抗菌剤は遺伝的な影響があるとして、EUでは90年代に、
アメリカでは2002年に家畜への使用が禁止された。
それで、日本でも生産が中止されると、2003年6月に食品安全委員会が、「ニ
トロフラン類の分解物が残留した食品を流通しないようにすること」と見解をまとめ
て、2005五年から実態検査が始まった。
すると、ウナギでは、中国産から二八件、台湾産から12件、ベトナム産から3件
検出された。2006年から本格的に取り締まりが始まったが、それ以降も、少しだ
がニトロフラン系の抗菌剤は検出され続け、2011年には韓国産のウナギからも検
出されている。
毎年ニトロフラン系の薬剤が検出されていることは、検査をすり抜けて、少しでは
あるが、抗菌剤の残留したウナギが国内に出回っていることを意味する。
中国のウナギ養殖場でエサに混ぜている薬剤のリストを見せてもらったら、他の抗
菌剤が複数使われていたから、中国産ウナギは常に抗菌剤の不安がある。
日本では、抗菌剤を使わないウナギ養端場がある。
鹿児島県の山田水産は、豊富な伏流水を使って「無投薬」ウナギを生産している。
このウナギは、イオンの「トップバリュ」「グリーンアイ」として販売されている。
ヤマネ・イワナなどの川魚
●淡水魚がが出荷自粛になった地域では汚染が続いている
淡水魚は、ミネラルの少ない淡水からミネラルを吸収しながら生きている。
セシウムもストロンチウムもミネラルのI種なので、川や湖が放射性セシウムや放
射性ストロンチウムで汚染されると、海の魚より汚染度がよりひどくなる。
2012年4月から食品の新基準が適用されたときに、出荷を自主規制したり、出
荷規制を受けたりしたのは、福島、岩手、宮城、千葉、茨城、栃木、群馬各県の主流
河川や湖沼で獲れるヤマメ、イワナ、ウグイ、ワカサギ、コイ、フナ、ウナギだ。
福島第コ原発から出た放射能は、風にのって飛びながら山の斜面にある森林で捕捉
された。それが少しずつ流れ出て川や湖が汚染され続ける。特に湖は放射能がたまる
一方だから、淡水魚はこれから長期にわたって汚染が続くことになる。
川の先にある湾も、ひどい放射能汚染が起きている。淡水魚が出荷自粛になったと
ころの下流の湾の魚介類も食べないようにしよう。
ホッケの開き
●調味料が注射針で注入されている
ホッケの開きをフィルムで密着パックし、「天然物」「とろ」などと表示して売って
いる。フィルムを取り除いてホッケを切り身にし、切り口を曲げると、液体がでてき
て、ポタッ、ポタッと落ちた。
このホッケには注射器で「調味液」が注入されていたからだ。
調味液は、食塩水がベースで、還元水あめ、でんぷん、ゼラチン、リン酸塩、甘味
料、pH調整剤、増粘多糖類、化学調味料、酸化防止剤、日本酒などが入っている。
この液をタンクに入れ、魚に数百本の細い注射針を刺して注入すると、1~2割、
増量できる。この「インジェクション処理」が、今では、広く行われている。
焼いたホッケの背骨を取ろうとすると、注射針を刺したときに骨が折れているので、
背骨は取れない。食べると「おいしい」と言う人もいる。化学調味料が入っているか
らだが、ホッケ本来の味ではない。
調味液の成分は、毒性がないものばかりだが、保温剤としてリン酸塩が使用されて
いるから、ミネラル不足になって心身を病む危険性がある。
サケ、サバ、アジ、サンマ、ツボダイ、ニシンなどの開きで、密着パックしたもの
には、インジェクション処理がよく行われている。
2012年6月に、北海道沖で獲れた真ホッケから、放射性セシウムが6ベクレル
/㎏検出されているので、ホッケもだんだん安心できなくなっている。
西京漬け
●大切な微量栄養素を失った魚に
「魚の○○漬け」も、よくインジェクション処理が行われている。
大量の魚の切り身を味噌や粕床に漬け込むと、漬かり方にムラができやすい。そこ
で、たくさんの注射針を剌してインジェクション処理し、パックに入れると、その中
でなじんで、均一に味付けすることができる。短時間ですむから、効率もいい。
しかし、切り身の魚を漬け込んだ商品には、栄養的には大きな問題がある。
冷凍魚をカットして身を穴だらけにするので、そこから魚の栄養素が溶け出してし
まうのだ。
冷凍したときに細胞膜が壊れるので、解凍したとき、細胞膜に含まれていて水に溶
けやすいレシチンがまず溶け出す。それから、細胞内にあったミネラルなども溶け出
る。
焼く前に、健康のために必要な微量栄養素が失われた魚になっているのだ。
栄養素の代わりに、化学調味料が入っているので、味はいい。しかし、魚の組織が
壊れているので、魚とは思えないようなほぐれ方をする。
私たちは、いつの間にかこんな魚を食べるようになっていたのである。
サワラ、タラ、ブリ、ハマチなどの「○○漬け」は、インジェクション処理がよく
行われているので、注意が必要だ。
小若順一 著 『食べるな危険!』、PP.52-62
※ ネオニコチノイド系農薬
有害性が問題視される有機リン系農薬に替わり、1990年代に日本でも登場し、近年多用さ
れている農薬、殺虫剤。タバコの有害成分ニコチンに似ているため、ネオニコチノイドと
いう名前がその由来という。

※ コンクリートで固めるという工法について
「コンクリートから人へ」というスローガンあるように、高度経済成長期の大規模な土木
工事をともなう公共事業のコスト・ベネヒット(費用便益分析)の悪さから否定される風
潮が定着したが、コンプリート工法は、そのの歴史は古く、紀元前には使用されていたこ
とが発掘された遺跡調査などから確認されている。ローマ帝国時代には、コンクリートは
革新的な建設材料として使用され、ローマ帝国の発展に大いに貢献していた。ローマ帝国
以前は気硬性(自然乾燥で硬化)の石灰は固まるのに時間がかかっていたが、ローマ人は、
紀元前2世紀頃にイタリアのポッツォリ近郊の火山性堆積物(ポッツォラーナ)などを使
用し水を混ぜるとすぐに固まる(水硬性)コンクリートを発見しことにはじまる。その利
便性利用上、生態系とのバランスを崩してきたことによる反省がある。しかし、生態系へ
のデメリット評価(事前調査)を工法に組み込むことで両立できるものだと考えている。
従って、「コンクリートから人へ」は「コンクリートの最適化」へ呼び変えるるべきだろ
う(→グリーンコリドー/ビオトープ)。
こういったことを考えていたら『未来型田園都市』の構想(イメージ)を描いてみたくな
ったが、マルチメディア技術事典の掲載が終われば取り組むことに。