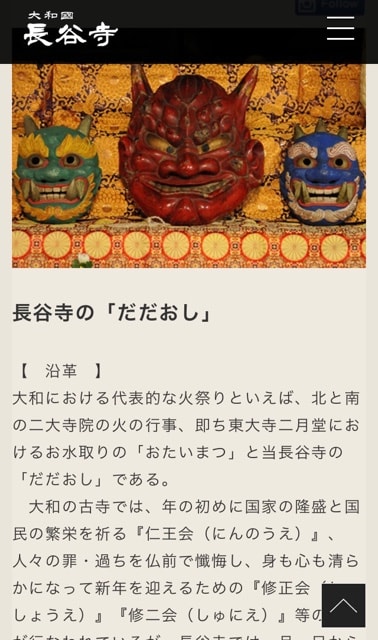今日は曇ってて陰鬱なかんじ。
何の日かなと、長谷寺でもらった暦みると
針供養、確かにそんな日ありました。
針仕事が身近だった子どもの頃、折れた針とかまとめて処分供養し、裁縫上達を願ったものだった。
ネットで確認したら関西では12月8日となってたけれど、私の記憶は定かでない。
その日がなんでこと始めなんだろな。
調べてみました。
古くから2月8日と12月8日は、事八日(ことようか)と呼ばれ、
事を始めたり納めたりする様々な行事が行われてきた。
その代表的な行事が針供養。
この事八日の2日間は「事始め・事納め」とも言われ、神様をお祭りする日でもある。
実はこの2月8日と12月8日は、神様を迎える行事と捉えるのか、人の日常生活の期間と捉えるのかで、事始めの日と事納めの日が逆転する。
12月8日が事始め、2月8日が事納め
神様を迎える行事期間と捉えた場合、
神様をお迎えするための準備をスタートさせるのが12月8日で、
この日より正月行事のために煤払いなど大掃除をしたり、
門松を準備したり松迎えなどを始める。
正月を経て、それらの後片付けも含めすべてを納める日を2月8日とし事納めとする。
12/8は事始めの日。
年を司る神様である年神様を迎えるために、正月行事の準備を始めるのが12月8日の「事始め」で、年越しの「神事」が始まる日です。
2月8日が事始め、12月8日が事納め
神様を迎える行事の最終日が、人の日常生活が始まる初日。
旧暦の2月8日は、草木が芽吹く春を迎えるべく、農作業が開始される時期。人々の暮らしがいよいよ本格的に始動する2月8日は、人にとっての事始めの日となった。
暦には、もう一つ気になることが書かれてました。
長谷寺修二会(~14日)
修二会といえば東大寺二月堂のお水取り。
長谷寺でもめんめんと受け継がれてきてたんですね。
もうちょっと詳しく調べて項を改めます。
つづく