
頭が猿、体は虎、尾は蛇のような妖魔退治した藤原高光。

国道265号線から高賀口で右に折れて高賀川沿いに進みます。
後になって地図を見て、
牛戻し橋(谷戸橋)に気づきました。
「
高賀の伝説を彩る、この橋より先へは牛を入れてはいけないといい伝えの残る橋」
なんか意味ありげでしょう。





高賀山(1,224m)の麓に鎮座する高賀神社、
神社の創建は、奈良時代の養老元(西暦717)年。
二十三柱もの神々を祀り、妖魔退治伝説を今に伝えています。
御祭神
国常立尊(クニコトタチノミコト)
天御中主尊(アメノミナカヌシノミコト)
国狭槌尊 (クニサズチノミコト)
豊斟淳尊(トヨクムヌノミコト)
泥土煮尊(ウイジニノミコト)
沙土煮尊(スヒジニノミコト)
大戸道尊(オオトジノミコト)
大戸辺尊(オオトマエノミコト)
面足尊(オモダルノミコト)
吾屋惺根尊(アヤカシコネノミコト)
伊弉諾尊(イザナギノミコト)
伊弉冉尊(イザナミノミコト)
大日婁貴(オオヒルメノムチ)
天忍穂耳尊(アメノオシホミミノミコト)
瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)
彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト)
鵜鵐草葦上合尊(ウガヤフキアエズノミコト)
素盞鳴尊(スサノオノミコト)
太玉命(フトタマノミコト)
天児屋命(アメノコヤネノミコト)
猿田彦命(サルタヒコノミコト)
金山彦尊(カナヤマヒコノミコト)
日本武尊(ヤマトタケルノミコト)

社務所にいらして、どちらから来られましたかと声かけてくださった宮司さん?
宝物殿(右手にある建物で写ってません)の中を案内してくださった。
立派な珍しい神像とか宝物が所狭しと並んでた。
画像ないし、説明も全部消化しきれなかったけど、なんか凄いとこやなぁというのだけ実感しました。
直前まで雨降ってたそうで、木々の緑も清められすがすがしかった。

左に円空記念館(平成7年7月7日開館)、その建物との間にさるとらへび伝説像があります。
 さるとらへび伝説
さるとらへび伝説とは、平安時代に藤原高光が二回この地に訪れて妖魔退治をしたことを伝えます。
ところが、
高賀宮記録によれば、
「
当宮の始めは、霊亀年中(710年代)何処ともなく夜な夜な怪しい光が空を走り丑寅の方角へ飛んで行くのを都の人たちが見て驚いた。
都から見て東北の山々、すなわち高賀山を探したが、見つけることはできなかった。
そこで、高賀山麓に神壇を祀ったところ、光が現れなくなったという。これが高賀山本神宮の始まりだといわれています。
その後、高賀山一帯に、牛に似た妖怪が住み付き、村人に危害を加えたので、平承3年(933)、藤原高光が御門の勅命によりこれを退治した。このとき再び妖怪が住みつかないように高賀山の麓に神々を祀った。
また、天暦年間(947~957)には、キジの鳴き声をする大鳥が村人を困らせたので、再び藤原高光による魔物退治が行われ、この時、高賀山麓の六ヶ所に神社を建立したとされている」
記録される妖魔は最初が「
牛の角を持った大鬼」、二回目が「
キジのような鳴き声を発する大鳥」
頭は猿、体は虎、尾は蛇に似るという「
さるとらへび」なる妖魔ではありません。
高校時代に古文を習ったときのかすかな記憶では、鵺(ぬえ)が登場します。
 鵺とは
鵺とは - Wikipedia より
日本で伝承される妖怪あるいは物の怪
平安時代末期、天皇(近衛天皇)の住む御所・清涼殿に、毎晩のように黒煙と共に不気味な鳴き声が響き渡り、二条天皇がこれに恐怖していた。
遂に天皇は病の身となってしまい、薬や祈祷をもってしても効果はなかった。側近たちは、かつて源義家が弓を鳴らして怪事をやませた前例に倣って、弓の達人である源頼政に怪物退治を命じた。
頼政はある夜、家来の猪早太を連れ怪物退治に出向いた。
すると清涼殿を不気味な黒煙が覆い始めたので、頼政が矢を射ると、悲鳴と共に鵺が二条城の北方あたりに落下し、すかさず猪早太が取り押さえてとどめを差した。
これにより天皇の体調もたちまちにして回復し、頼政は天皇から褒美に獅子王という刀を貰賜したという。

歌川国芳:源三位頼政 鵺退治の図

一勇齋国芳(歌川国芳):鵺退治(ボストン美術館所蔵)
高賀の「さるとらへび伝説」は、古文書としては何も残らず口伝によるものです。
時代は下り、1180年源頼政は、後白河天皇の第三皇子・
以仁王と結んで平家打倒の挙兵をあげたが、宇治平等院の戦いで敗れ自害。
実際、源頼政の墓は宇治平等院の鳳凰堂の裏に江戸時代に作られています。
しかし首級を頼政の伯父・山県国直の居地である美濃植野の地に家臣が葬ったといわれていて、岐阜県関市植野の蓮華寺にも源頼政の墓と伝える石塔があるそうです。
こうしたご縁で、12世紀末の都の「鵺退治伝説」がこの地にも広まり、10世紀半ばの高賀の妖魔退治が「さるとらへび退治」へと置き換わったのかもしれません。
この記事の最初に書いた、牛戻し橋の疑問、
こんな答え見つけたので引用させてもらいます。
「牛戻し橋」は、牛頭天王信仰がこの地に入ってくる(8世紀から9世紀にかけて)ずっと以前からあったのではと考えます。
高賀山自体を神と崇める自然崇拝で、その生贄として「牛」を使っていたとするなら、「牛が一旦この橋を渡ったら最後二度と戻れないぞ」との思いから、「牛戻し橋」と呼ばれるようになったと考えられます。
中国では、古来より神の怒りを静める方法として、牛を生贄に使ってきました。その風習は、6世紀から7世紀頃には渡来系の人たちによって日本に流入していたはずです。この地に、渡来系の人々による信仰が広まっていたならば牛を生贄として使う風習があってもおかしくないはずです。
引用元
洞戸なんでもわけあり情報
そのブログを読ませてもらってたら、
猿丸太夫の墓 という記事エントリー発見。
過去に2013-11-10
蝉丸 猿丸 山の民? という記事で書きましたが、猿丸って不思議だなと思ってました。
ひとつの答えを今日発見できてうれしい。
猿丸太夫の墓が、高賀山に連なる今渕ヶ岳の麓、瀧神社参道横にあるそうです。
美濃市乙狩板山地区には、高賀の魔物退治と絡んで、猿丸太夫の伝説が残ってました。
「高賀の魔物退治をしたと言われている藤原高光。
高光の命によって集まった矢作りの人々の中に「あきよ」という娘がいました。高光とあきよの間に一子が生まれ、猿丸と名づけられました。猿丸は、やがて都に登って父に会い、天皇から賞賛されるような歌人になりました。しかし猿丸は、父の迷惑を考えて終生素性を語りませんでした。 ○美濃市史通史編上巻より」

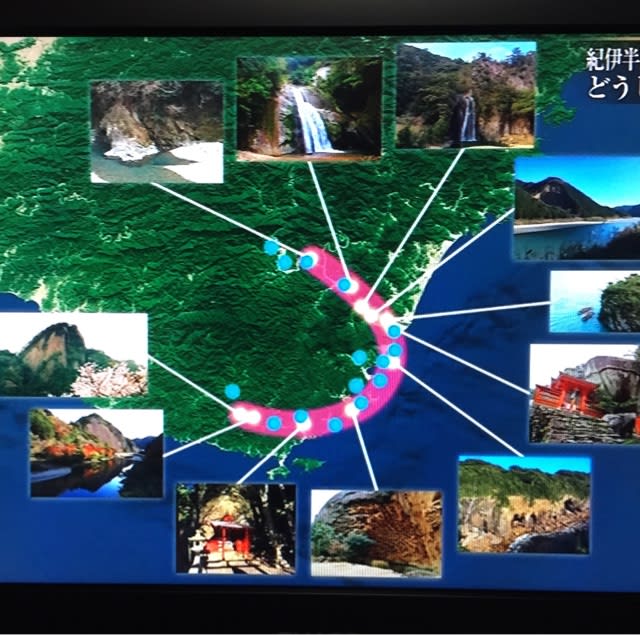





































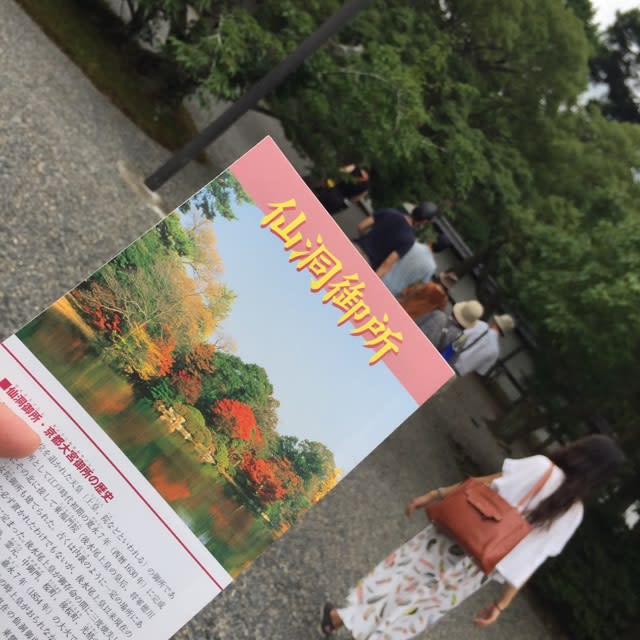








































































 『椿説弓張月』より崇徳上皇が讃岐で崩御し、怨霊になる瞬間を描いた一場面(歌川芳艶画)
『椿説弓張月』より崇徳上皇が讃岐で崩御し、怨霊になる瞬間を描いた一場面(歌川芳艶画)