都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「蜀山人 大田南畝」 太田記念美術館
太田記念美術館(渋谷区神宮前1-10-10)
「蜀山人 大田南畝 - 大江戸マルチ文化人交友録 - 」
5/1-6/26
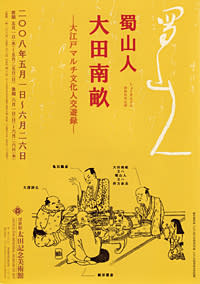
会期終了間際の駆け込みで見てきました。狂歌師や劇作者として名を挙げ、また江戸文化人コミュニティのハブとしても活躍した大田南畝の回顧展です。

南畝の活動を概観するのにこの上ない展覧会であったのは間違いありません。冒頭、南畝が賛を入れた春章らの肉筆浮世絵にはじまり、鳥文斎栄之、または谷文晁らの描いた彼の肖像、さらには冒頭には源内の序文もあるデビュー作「寝惣先生文集」の紹介からペンネーム『四方赤良』として活躍した数々の劇作、それに漢詩、書、あげくの果てには彼を取り巻く絵師たちの画までがズラリと揃っていました。同美術館のスペース上、例によって展示品の半数以上が会期途中で入れ替わっていましたが、それでも南畝の人に触れ、業績を知るのには不足ないラインナップです。楽しめました。

ハブコネクション的な存在ということで、南畝は同時代に活躍していた文化人らを横に繋げる役割も務めています。文人たちのたまり場、料亭の八百善に集うのは南畝の他、浮世絵師北尾政美、また書家で儒学者の亀田鵬斎、漢詩人の大窪詩仏などでした。(「江戸流行料理通」より。ちらし表紙に掲載。)また数多くの浮世絵などに賛を入れた南畝だけあって、文字と画のコラボの作品をいくつも堪能出来ます。その中で印象深いのは栄之画、南畝賛の「秋の隅田川図」です。浅草の隅田川上の屋形船にてお月見をする様子が風流に描かれています。また南畝本人の画もいくつか紹介されていました。「藤娘図」は、その稚拙な描写が画の素人であった彼の作と推定出来得るという一枚です。確かにぎこちない線描ながらも、その人形のような可愛らしい造形には素直に惹かれるものがありました。
最後には抱一の登場です。率直なところ、彼と南畝との関係を鑑みるともう少し突っ込んだ展示が欲しいところでしたが、抱一、其一、南湖の画に鵬斎の賛を合わせた「松に鶴亀図」はなかなか軽妙な技の冴える作品でした。抱一が描いた部分は其一の表した松の先端にのる二羽の鶴だけですが、彼の署名も「文詮」の落款も確かに入っています。贅沢なコラボです。

これからは、絵師や作家などをネットワーク状に繋いだ南畝のような人物がさらに注目されていくのではないでしょうか。太田記念美術館ならではの好企画でした。(展覧会は既に終了しています。)
「蜀山人 大田南畝 - 大江戸マルチ文化人交友録 - 」
5/1-6/26
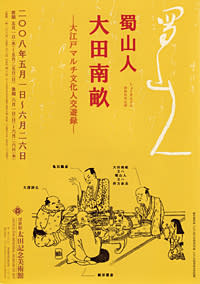
会期終了間際の駆け込みで見てきました。狂歌師や劇作者として名を挙げ、また江戸文化人コミュニティのハブとしても活躍した大田南畝の回顧展です。

南畝の活動を概観するのにこの上ない展覧会であったのは間違いありません。冒頭、南畝が賛を入れた春章らの肉筆浮世絵にはじまり、鳥文斎栄之、または谷文晁らの描いた彼の肖像、さらには冒頭には源内の序文もあるデビュー作「寝惣先生文集」の紹介からペンネーム『四方赤良』として活躍した数々の劇作、それに漢詩、書、あげくの果てには彼を取り巻く絵師たちの画までがズラリと揃っていました。同美術館のスペース上、例によって展示品の半数以上が会期途中で入れ替わっていましたが、それでも南畝の人に触れ、業績を知るのには不足ないラインナップです。楽しめました。

ハブコネクション的な存在ということで、南畝は同時代に活躍していた文化人らを横に繋げる役割も務めています。文人たちのたまり場、料亭の八百善に集うのは南畝の他、浮世絵師北尾政美、また書家で儒学者の亀田鵬斎、漢詩人の大窪詩仏などでした。(「江戸流行料理通」より。ちらし表紙に掲載。)また数多くの浮世絵などに賛を入れた南畝だけあって、文字と画のコラボの作品をいくつも堪能出来ます。その中で印象深いのは栄之画、南畝賛の「秋の隅田川図」です。浅草の隅田川上の屋形船にてお月見をする様子が風流に描かれています。また南畝本人の画もいくつか紹介されていました。「藤娘図」は、その稚拙な描写が画の素人であった彼の作と推定出来得るという一枚です。確かにぎこちない線描ながらも、その人形のような可愛らしい造形には素直に惹かれるものがありました。
最後には抱一の登場です。率直なところ、彼と南畝との関係を鑑みるともう少し突っ込んだ展示が欲しいところでしたが、抱一、其一、南湖の画に鵬斎の賛を合わせた「松に鶴亀図」はなかなか軽妙な技の冴える作品でした。抱一が描いた部分は其一の表した松の先端にのる二羽の鶴だけですが、彼の署名も「文詮」の落款も確かに入っています。贅沢なコラボです。

これからは、絵師や作家などをネットワーク状に繋いだ南畝のような人物がさらに注目されていくのではないでしょうか。太田記念美術館ならではの好企画でした。(展覧会は既に終了しています。)
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )









