都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「モチーフで読む美術史」 ちくま文庫
「欲望の美術史」に続き、宮下規久朗先生の新聞連載が書籍化されました。ちくま文庫の「モチーフで読む美術史」を読んでみました。
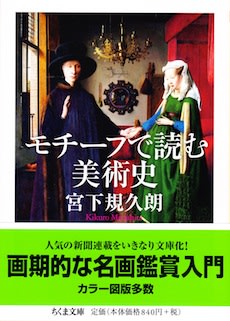
「モチーフで読む美術史/宮下規久朗/ちくま文庫」
さて西洋絵画におけるモチーフやアイテムの意味については、以前に拙ブログでも紹介した「アイテムで読み解く西洋名画」をオススメしたいところですが、本書に関しては西洋にとどまらず、日本や東洋、さらには現代美術にまで言及し、文化論として読み応えがあるのもポイントかもしれません。
ではまず扱われているモチーフから。その数は全66点。犬や鶏などの動物にはじまり、パンやチーズなどの食べ物、そして薔薇から月や星に雷、さらには鉄道や端、また性愛や夢といった素材も。具体的なものから観念的なものへ。非常に多岐に渡るモチーフが引用されています。

牧谿「観音猿鶴図」13世紀後半 京都、大徳寺
早速、東西比較で興味深いところを。例えば冒頭の「猿」。西洋では異端や淫欲などの邪悪的な意味が。翻って日本ではどうなのか。それこそ等伯の猿しかり、決して陥れるような主題ではありません。よく知られた森派の猿など、猿自体の習性や仕草をよく観察して描いた作品が残されています。
西と東で特に対照的なのは「竜」。西洋ではしばしば蛇と混同され、悪魔や異端の意味が。一方で東洋では特に中国が皇帝のシンボルとして扱うなど、神聖な動物と見なされています。また日本でも蛇神信仰などと融合して雨の神様として崇められました。

カラヴァッジョ「蛇の聖母」1605-06年 ローマ、ボルゲーゼ美術館
ちなみに今、引用した「蛇」、確かに西洋では否定的なモチーフとして知られていますが、それはキリスト教の価値に由来するもの。例の原罪のモチーフです。よってキリスト教以前の西洋では時に良い意味も持ち合わせ、例えば雨の象徴として祭儀に用いられたとか。また医術の神の持つ杖に絡むような賢い動物である、といった表現も残されているそうです。

高橋由一「鮭」1877年頃 東京藝術大学大学美術館
また面白いのが「鮭」。高橋由一の鮭を引用していますが、これは贈答用として描かれたもの。論はそこから西洋の静物画へと展開。そもそも静物画もクセニアと呼ばれる贈答用の食材を描いた絵画から発生したジャンルだとか。これは知りませんでした。
なお食の観点から言えば「肉」と「魚」についても言及。魚を描いた作品は日本でも多数ありますが、肉のみを捉えたものはあまりありません。一方で西洋では肉の塊を描いた静物もいくつか。単独のモチーフとして確立しますが、元来は肉を物質的な欲望を示す否定的なモチーフとして位置づけていたのだそうです。

「柳橋水車図屏風」17世紀 滋賀、MIHO MUSEUM
章が進むにつれて西洋画の引用が多くなりますが、それでも例えば「橋」で再び日本美術に言及。キーワードは彼岸への道です。しかしながら西洋では「梯子」や「虹」は多く登場するものの、「橋」に象徴的な意味を与えることはありません。何故なのでしょうか。
さらに「分かれ道」では西洋のヘラクレスの主題を引用するともに、日本の画家、北脇昇の「クオ・ヴァディス」についても。私も近美で何度か目にしたことのある作品。道をどちらに進むべきか。どことない迷いの気持ちを感じます。
このペースであげていくとキリがありませんが、「ジャガイモ」の項では北朝鮮の画家、キム・ソンリョンの作品も。幅広い視点が論を深めています。
モチーフに派生する美術表現の東西文化比較論。その観点からも注目すべき一冊ではないかと思いました。
 「モチーフで読む美術史/宮下規久朗/ちくま文庫」
「モチーフで読む美術史/宮下規久朗/ちくま文庫」
まずは書店にてご覧ください。
「モチーフで読む美術史」 ちくま文庫
内容:絵画に描かれた代表的な「モチーフ」を手掛かりに美術を読み解く、画期的な名画鑑賞の入門書。カラー図版150点を収録した文庫オリジナル。
著者:宮下規久朗。1963年愛知県生まれ。美術史家、神戸大学大学院人文学研究科准教授。
価格:840円(+税)
刊行:2013年7月
仕様:272頁
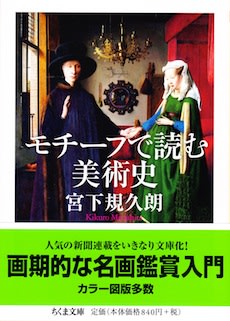
「モチーフで読む美術史/宮下規久朗/ちくま文庫」
さて西洋絵画におけるモチーフやアイテムの意味については、以前に拙ブログでも紹介した「アイテムで読み解く西洋名画」をオススメしたいところですが、本書に関しては西洋にとどまらず、日本や東洋、さらには現代美術にまで言及し、文化論として読み応えがあるのもポイントかもしれません。
ではまず扱われているモチーフから。その数は全66点。犬や鶏などの動物にはじまり、パンやチーズなどの食べ物、そして薔薇から月や星に雷、さらには鉄道や端、また性愛や夢といった素材も。具体的なものから観念的なものへ。非常に多岐に渡るモチーフが引用されています。

牧谿「観音猿鶴図」13世紀後半 京都、大徳寺
早速、東西比較で興味深いところを。例えば冒頭の「猿」。西洋では異端や淫欲などの邪悪的な意味が。翻って日本ではどうなのか。それこそ等伯の猿しかり、決して陥れるような主題ではありません。よく知られた森派の猿など、猿自体の習性や仕草をよく観察して描いた作品が残されています。
西と東で特に対照的なのは「竜」。西洋ではしばしば蛇と混同され、悪魔や異端の意味が。一方で東洋では特に中国が皇帝のシンボルとして扱うなど、神聖な動物と見なされています。また日本でも蛇神信仰などと融合して雨の神様として崇められました。

カラヴァッジョ「蛇の聖母」1605-06年 ローマ、ボルゲーゼ美術館
ちなみに今、引用した「蛇」、確かに西洋では否定的なモチーフとして知られていますが、それはキリスト教の価値に由来するもの。例の原罪のモチーフです。よってキリスト教以前の西洋では時に良い意味も持ち合わせ、例えば雨の象徴として祭儀に用いられたとか。また医術の神の持つ杖に絡むような賢い動物である、といった表現も残されているそうです。

高橋由一「鮭」1877年頃 東京藝術大学大学美術館
また面白いのが「鮭」。高橋由一の鮭を引用していますが、これは贈答用として描かれたもの。論はそこから西洋の静物画へと展開。そもそも静物画もクセニアと呼ばれる贈答用の食材を描いた絵画から発生したジャンルだとか。これは知りませんでした。
なお食の観点から言えば「肉」と「魚」についても言及。魚を描いた作品は日本でも多数ありますが、肉のみを捉えたものはあまりありません。一方で西洋では肉の塊を描いた静物もいくつか。単独のモチーフとして確立しますが、元来は肉を物質的な欲望を示す否定的なモチーフとして位置づけていたのだそうです。

「柳橋水車図屏風」17世紀 滋賀、MIHO MUSEUM
章が進むにつれて西洋画の引用が多くなりますが、それでも例えば「橋」で再び日本美術に言及。キーワードは彼岸への道です。しかしながら西洋では「梯子」や「虹」は多く登場するものの、「橋」に象徴的な意味を与えることはありません。何故なのでしょうか。
さらに「分かれ道」では西洋のヘラクレスの主題を引用するともに、日本の画家、北脇昇の「クオ・ヴァディス」についても。私も近美で何度か目にしたことのある作品。道をどちらに進むべきか。どことない迷いの気持ちを感じます。
このペースであげていくとキリがありませんが、「ジャガイモ」の項では北朝鮮の画家、キム・ソンリョンの作品も。幅広い視点が論を深めています。
モチーフに派生する美術表現の東西文化比較論。その観点からも注目すべき一冊ではないかと思いました。
 「モチーフで読む美術史/宮下規久朗/ちくま文庫」
「モチーフで読む美術史/宮下規久朗/ちくま文庫」まずは書店にてご覧ください。
「モチーフで読む美術史」 ちくま文庫
内容:絵画に描かれた代表的な「モチーフ」を手掛かりに美術を読み解く、画期的な名画鑑賞の入門書。カラー図版150点を収録した文庫オリジナル。
著者:宮下規久朗。1963年愛知県生まれ。美術史家、神戸大学大学院人文学研究科准教授。
価格:840円(+税)
刊行:2013年7月
仕様:272頁
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )










