山梨県より 『富士の国やまなし観光ネット』
『富士の国やまなし観光ネット』 が配信され、いつも観光情報欄をチェックしています。
が配信され、いつも観光情報欄をチェックしています。 その中で西桂町に
その中で西桂町に クマガイソウ
クマガイソウ の群生地があり、約5,000株が5月初めから中旬にかけて見頃であります。とありました。
の群生地があり、約5,000株が5月初めから中旬にかけて見頃であります。とありました。

それも、環境省によりレッドデータブックの絶滅危惧Ⅱ類の指定を受けた貴重な花とのことであります。 その花とは、どんな花なのだろう
その花とは、どんな花なのだろう  と思い出かけてみました。
と思い出かけてみました。

日本では北海道南部から九州にかけて分布し、低山の森林内、特に竹林・杉林などに生育し大きな集団を作るようです。 地下茎は節間が長く全長は1m以上になり、硬くて柔軟性に欠け先端の生長点は鉢の内壁などに当たると枯死し鉢植えに適さないそうです。
なのに乱獲や盗掘が後を絶たず、 絶滅が危惧されるラン科アツモリソウ属に分類される多年草の植物です。
絶滅が危惧されるラン科アツモリソウ属に分類される多年草の植物です。

全体の特徴は、草丈40cmくらい、葉は 対生するように2枚つき、それぞれ扇型の特徴的な形をしている。 花はその間からのびた茎の先につき、横を向く。
対生するように2枚つき、それぞれ扇型の特徴的な形をしている。 花はその間からのびた茎の先につき、横を向く。 花弁は細い楕円形で緑色を帯び、唇弁は大きく膨らんだ袋状で、白く紫褐色の模様があり、唇弁の口は左右から膨らんで狭まっている。
花弁は細い楕円形で緑色を帯び、唇弁は大きく膨らんだ袋状で、白く紫褐色の模様があり、唇弁の口は左右から膨らんで狭まっている。

こんな特徴を持つ珍しい花にビックリしました。 西桂町では5株から栽培を始め、一時は約3万株にまで増えていたようですが、乱獲や盗掘により約5,000株にまで減少したため、町が大切に保護しているということです。
西桂町では5株から栽培を始め、一時は約3万株にまで増えていたようですが、乱獲や盗掘により約5,000株にまで減少したため、町が大切に保護しているということです。

名前の由来ですが、鎌倉時代の武将 『熊谷直実』(くまがいなおざね)
『熊谷直実』(くまがいなおざね) が背中に背負った母衣(ほろ:弓矢を防ぐためのに大きく膨らませた布のこと)に見立てたことから、 「熊谷草」(クマガイソウ)という名前がついたようです。
が背中に背負った母衣(ほろ:弓矢を防ぐためのに大きく膨らませた布のこと)に見立てたことから、 「熊谷草」(クマガイソウ)という名前がついたようです。











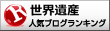

 春、7年に一度の
春、7年に一度の 御開帳
御開帳

 その六寺とは、
その六寺とは、 信濃善光寺(長野県)
信濃善光寺(長野県)  甲斐善光寺(山梨県)
甲斐善光寺(山梨県)  飯田元善光寺(長野県)
飯田元善光寺(長野県)  善光寺東海別院(愛知県)
善光寺東海別院(愛知県)  関善光寺(岐阜県)
関善光寺(岐阜県)  岐阜善光寺(岐阜県)であります。
岐阜善光寺(岐阜県)であります。
 焼失を
焼失を 恐れ、永禄元年(1558)ご本尊
恐れ、永禄元年(1558)ご本尊

 その後、武田氏滅亡により、ご本尊は織田・徳川・豊臣氏を転々といたしましたが、慶長3年(1598)信濃に帰座なさいました。
その後、武田氏滅亡により、ご本尊は織田・徳川・豊臣氏を転々といたしましたが、慶長3年(1598)信濃に帰座なさいました。
 また、金堂下には「心」の字をかたどる、珍しい「お戒壇巡り」があり、真っ暗な中を手すり伝いに進み、ご本尊下にある
また、金堂下には「心」の字をかたどる、珍しい「お戒壇巡り」があり、真っ暗な中を手すり伝いに進み、ご本尊下にある 鍵
鍵 に触れることができました。
に触れることができました。 ご本尊様とご縁を結べ、良い年となることを、お祈りして来ました。
ご本尊様とご縁を結べ、良い年となることを、お祈りして来ました。
 二頭
二頭





