せっかく今日、晴れ間が見えたのに、また雲が…
明日は、‘きらら'の体操教室があるのに… 雨が心配です。
『運動の秋』です、脚の痛みが少ない時に、工夫をして運動を
少しでもして欲しいと思います。
『食欲の秋』だけ、満喫しないように!
ぜひ、頑張って下さい。
今日も、『100歳までウォーキング』続けます。
■歩行と歩行障害の要因
①歩行のしくみ 一昨日の続きから一
また、股関節の運動は、股関節周辺を取り巻く大きな筋群の強力
なバネの力によって行われています。この股関節のバネ運動は、
体幹と下肢の屈伸バネ運動を仲介し、調節してからだ全体を前進
させる力を生み出します。体幹の屈伸運動を行うバネの力は、
重力に抵抗して立つ姿勢が鉛直の直立姿勢であるほど効率よく
はたらき、からだが前傾位や水平位では効率が悪くなります。
一方、下肢では下腿骨が重力に抵抗して前傾するほど効率よく
前進することができるので、下肢のバネの力の大小は、膝と足の
バネのはたらきにかかわっています。ですから、前方へ移動する
歩行能力のよし悪しは、体幹、下肢ともに重力に抵抗して起立する
能力にかかわっていることになります。この能力は体重を支える
骨格と筋力から成り立っていることになります。
歩く時のもう1つの大切な運動に、体重の左右移動の運動があり
ます。人の歩行動作の特徴は前に述べたように左右の足を交替し
て、1本足で体重を移動させます。1本足で体を前方移動しつつ、
同時に体重を支えるためには、確実にしかも安全に体重を同じ側
の大腿骨頭の上に移動することが大切になります。
片足で体を支えるときは、体重の3倍くらいの大きな力が股関節
に加わります。体重の左右移動では、体重より大きな力が下肢に
かかりますので、この調節が不良のときには、異常に大きな力が
下肢に加わり筋肉が疲労します。この力に耐えられないときに転倒
するのです。ですから、体重の左右移動に適合した骨格の構造や
関節の構造が重要となるのです。
前に説明した体幹の横楕円形の骨格構造が、これに相当します。
横楕円形の骨格構造は、骨盤の腸骨翼が外側に張り出し、鎖骨
が広い肩幅を作って胸郭にも横楕円形の体型がつくられました。
腸骨翼の発達とともに腸骨翼外側前方部にある股関節臼蓋部
(きゅうがいぶ)が発達して、大腿骨頭を外側まで大きく覆うように
なって安全な体重左右移動ができるようになったのです。
外側に張り出した骨盤の左右運動は、同じく外側に張り出した
肩の左右運動によって、体重が外側に行き過ぎないように調節さ
れて転倒を予防しているのです。骨盤や肩などの体幹だけでなく、
下肢も体重の左右移動運動を調節します。この運動は、足や足の
指全体で行う運動が中心となっています。
足が床に着くときには、体重が足の外へ行き過ぎないように制止
する運動(制動運動)を行います。また、離床の踏み切る時には、
反対側の足の方へ体重を内側へ移動するようにけりだし運動(駆動
運動)を行います。
足が行うこの制動と駆動の運動は、体重の左右運動を調節する
うえで大切な足の役割です。
 季節の変わり目、皆さん、お体大切に!
季節の変わり目、皆さん、お体大切に!『変形性股関節症に負けないでね!』










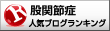
 まだまだ続きます。
まだまだ続きます。 5月の内容と重複することがあります。
5月の内容と重複することがあります。 『100歳までウォーキング』
『100歳までウォーキング』 国益が損なわれないような外交をぜひ、頑張って欲しい、
国益が損なわれないような外交をぜひ、頑張って欲しい、 たしか、一番初めにスナッピングの音を確認したのは…
たしか、一番初めにスナッピングの音を確認したのは… たぶん、今、私が医者へ行っても…
たぶん、今、私が医者へ行っても… う――――ん。まいった! 外にも行けない!
う――――ん。まいった! 外にも行けない!



