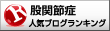自分の踊っている姿(ビデオ)を観れるようになるまで…
5年かかりました。
昨日から、ビデオ→DVDへダビングし直しています。
20歳から、変形性股関節症の関節唇切除と筋解離という手術を
受けて舞踊家を引退するまでの52歳まで、舞台へ出た回数、数知
れず、生徒さんのために振り付けした作品のビデオも含め…
100本以上。ダビングしながら、垣間見た踊る自分の姿!
冷静に観れました!
やっと、自分の病気「変形性股関節症」が、受け入れられた?
のかもしれません。 長い時間かかりました…
今日は、ちょうこさんから(骨嚢包の穴は塞がるのですか?)と
質問を受けましたので、銀座サロン松本正彦先生の本
『股関節痛は怖くない!』ーワニブックー、引用させていただきます。
☆骨にできる穴(骨嚢包)も修復されます
骨の中に穴があくことは、骨嚢包と呼ばれています。病院に
よっては「この穴がつぶれたら大変なことになるので、脚をかばって
歩きなさい」と言う医者がいます。穴がつぶれる何て言われたら、
怖くてもう脚に体重をかけられなくなるでしょう。その結果、筋肉は
痩せて骨も弱くなってしまうのです。
骨に穴があくことは事実です。しかし、その穴も自然治癒力で
除々に修復されます。私が勤務していた大学病院の先生は次の
ように説明していました。
「この穴のふちは、穴がつぶれないように頑丈になっているので、
つぶれることはありません」
骨の中にできた穴の中は、最初は黒く写ります。レントゲン写真で
黒く写るということは、骨密度が低下しているということです。しかし
レントゲン写真の経過を見ていると、黒かった骨の穴は除々に白く
なっていきます。白く写るのは、骨密度が高いということで、骨の中
にできた穴のふちが白くなったりするのは骨の修復なのです。人間
が持つ自然治癒力が正常に働いてくれた結果です。
骨に穴があいても、骨の修復力が解決してくれます。骨の穴に関し
ても、自然治癒力を信じ、怖がらないでいただきたいと思います。 骨頭にしろ、骨盤側にしろ、穴があいているということは、血液の
骨頭にしろ、骨盤側にしろ、穴があいているということは、血液の
循環が悪く、脚の痛みもあって、脚に体重をかけられなかったこと
もあって穴があいてしまった、と思います。私もあいていました。今、
塞がっている?はず?
骨がしっかりしていないと、いざ、もしも、という最終手段の
手術の時に、骨盤側の骨がガタガタだったため、人工の固定が難し
く手術に時間がかかった方や骨頭を切除して、ステム(人工骨頭)を
自分の骨にさす時に、自分の土台の骨にひびが入った方など、色々
と聞いています。
ですから、土台の骨を強くすることは、手術をする、しない、に
かかわらず重要です! 私も頑張っています!
骨が生まれ変わるのには、4ヶ月かかるそうです。股関節周辺の
血行をうながすための努力が必要です。具体的に何をすれば良い
のかは人それぞれだと思いますが、ブログにも色々書いています
ので参考になれば嬉しいです。
『変形性股関節症に負けないでね!』
母が亡くなって、直ぐ近く(同じマンションの301号と305号)の
兄と近いのに…ずっーと交流もなく、目が合っても挨拶もなく…
という状態から、少し挨拶程度になり、今は姪の赤ちゃんが
生まれたことにより、すっかり、行き来が再開しました。
昨日も母がそんな私達を見ていてくれ、喜んでくれたと、うれしい
気持ちになりました。
お墓の掃除は、炎天下(といっても朝の10時)の中、たった15分
で汗だくです。親戚と父方の祖父母のお墓と3家分。
主人、私、兄と3人で…
樹齢150年以上のいちょうの葉がお墓一面に…
しゃがんで、葉っぱを拾うのも一苦労!
やっぱり、脚の状態は進行した!?
しゃがんで、移動できなくなった…
いちいち、一枚拾っては、立って移動、また拾う。
腰をかがめては、腰も痛くなるし、痛いし。
なさけないー!
今、50代でこんな状態、70代になったら、お墓の掃除は
出来ない? お墓掃除代行の話も聞いたことがあったけれど。
まぁー今から心配してもしょうがないかー
今日は、朝から、ダビングをしています。
私の20歳からのバレエの作品。100本以上VHSのビデオテープ
です。それをDVDにダビングし直しています。
100本以上のダビングにえんえんかかりそうー
大量のごみが出そうです。
ビデオ→DVD、そして今はブルーレイの世界。
来年には、家のビデオデッキともさよならしなくちゃいけないし…
まだ、動くのに… もったいないー!
地デジ化の影響で、物入りだー!!!
おとといの朝の8時に朝帰りして(都内で男の後輩の美容師の卵と、
遊んでいたそうです)10時半に起こし仕事に行きました。
そんな不摂生をしているので今日もいくら起こしても…
夕方の7時に車で横浜へ出かけまだ戻りません。
少し前まで、不摂生な子どもの生活態度に、ただイライラして
怒り怒鳴っていましたが…
あきらめました。
息子には、息子の人生と考え方がある。と。
そして、息子の恋は、春が来て、夏になる前に、冬になりました。
明日は、1ヶ月ぶりの‘きらら'体操教室があります。
前に連絡が途切れていた、80代の方から電話をお盆の前に
頂きました。暫くぶりのお声もお元気でうれしかったー。
ただ、ご主人様は、施設に入られたようでその方は、デイサービ
スに行くと言ってらした。
「具合が悪くなり、救急車で運ばれ、一時は心配停止になって
家族親戚みな病室に来たのよ」と言われた。
大変な夏だったようでした。でも、気にかけて私にお電話を
下さった。きららへは、もう来れないかも知れないけれど…
嬉しかった!
明日は、この暑さの中、何人来て下さるか分からないけれど…
皆さんにお会いするのが、今から楽しみです。
仲間っていいですね!
世代を超えて、絆を感じました。
昨日は、(出版パーティー以来の)松本先生に施術をしてもらいまし
た。行き帰りの暑いこと暑い事‥‥7月18日のパーティーが、遠い昔
の出来事だったような感じがしています。私の身体の状態は?と、
施術を始める前に珍しく、悪い方の脚(私は左脚)をチェックします。
「悪くない。動きが良い」と自分では良いと思わないのですが…
――『股関節痛は怖くない!』――松本先生の本から引用します
★股関節が行っている6つの動作
股関節は球関節と呼ばれる形状の関節です。これは人体に可能
な範囲であらゆる方向に動かすことができます。ベアリングのよう
なものといった方がわかりやすいでしょうか。股関節では、屈曲・
伸展・外転・内転・外旋・内旋の動きが可能です。
ちなみに「旋」とは、身体の一部を軸として回す運動のことです。
外旋の場合は、動く場所の前面が外側に向かい、内旋の場合は、
動く場所の前面が内側に向うことをいいます。
私たちの日常生活では、無意識にこれら6つの運動が複雑に
組み合わされた動作をしているのです。
もともと個人差がありますが、一般的に股関節には73ページの
イラストでしめしたような動きの角度(範囲)があります。関節の動く
範囲を専門的には「関節可動域」といい、関節の動く範囲が狭く
なることを「関節可動域の制限」と呼んでいます。
 私はブログで絵が描けないので、正常股関節の関節可動域の
私はブログで絵が描けないので、正常股関節の関節可動域の角度を書きます。(まっすぐに立った状態から)
・伸展…後ろに脚を上げる動作で20゜
・屈曲…前にももを胸の方に寄せる動作で120゜
・外転…脚を横に上げて45゜
・内転…脚を内側に反対の脚より内に上げて入れた状態で20゜
・外旋…上に書いたように脚をひねるようにして、45°
・内旋…脚を内側にひねるように45°
変形性股関節症になると、痛みとともに股関節の関節可動域が
制限されることがあります。筋肉の短縮による筋肉の硬さから起き
てしまうのです。でも、骨と骨とがぶっかって股関節の動きが悪く
なっている方はほとんどいません。だから、初期のうちに筋肉を
ほぐして筋肉に柔軟性を持たせることがとても重要になってくるので
す。初期のうちに短縮して硬くなった筋肉は、病院では通常放って
おかれます。鎮痛剤の処方、そして筋力トレーニングをするようにと
指導されるのが一般的に診察ではないかと思われます。ところが
病院で指導する筋力トレーニングは、筋肉を収縮させる(筋線維が
短くなる)運動なのです。本来ならこの時期に、股関節周囲の筋肉を
ほぐすという治療を行うべきなのです。
関節が思うように動かなければ、筋力が十分に発揮できません。
また、可動域の悪くなった股関節を無理に動かそうとすると、逆に
筋肉を傷めてしまう可能性も出てきてしまうかもしれません。
ですから私は、股関節に関しては筋力をつけるよりも関節可動域
を広げる方が重要だと考えています。
 私の関節可動域、発表します。(これは、鏡に映った姿を見て自己
私の関節可動域、発表します。(これは、鏡に映った姿を見て自己評価しました。確か、富士温泉病院で初めにPTが計った。今度きち
んと聞いてみよう)
・屈曲‥右脚 正常、左脚 90゜
・伸展‥右脚 正常、左脚 正常
・外転‥右脚 正常、左脚 30゜
・内転‥右脚 正常、左脚 正常
・外旋‥右脚 正常、左脚 40°
・内旋‥右脚 正常、左脚 正常
私も、運動指導士として松本先生の可動域を広げる方が、筋力を
つけるよりも大切と考えています。まずは、自分の股関節可動域を
チェツクしてみましょう。そして、安心したり、嘆いて嫌になったりと感
情的になるのではなく、今の自分をしっかりと受け止めて、何をすれ
ばよいのか? ということを最重要課題にしてください。私の場合は、
ほぐしてほぐして(人頼み、松本先生だけでなく、自分でほぐすという
こと)ほぐしてから、筋力をつける無理のない運動をします。きららの
体操教室は、まさにそれを目標にしています!
今までは、仕事が不景気のため月の半分もなくて‥‥
ぶらぶらと好きなパチンコで楽しく遊んでいたのが‥‥
急に忙しくなり今月に入ってまだ3回しか休んでいません。
主人の仕事は(電気工事士)で、クーラーも入っていない部屋での
仕事ですので、ゆうに40℃の無風、サウナのような所での仕事です。
水分を半端じゃないくらい飲んでいるそうです。
水太り? のような腹になってます。。。
そんな主人が、貴重な休みの今日朝6時半から、大活躍で
洗濯(6㌔の洗濯機で4回)、お風呂場掃除、窓ガラス・網戸掃除、
フローリングのワックスがけ、をしてくれました。
ありがたい! 幸せ!
そんな主人に感謝しています。
先日、読んだ記事のご主人、最悪… みなさんのご主人はきっと
親切な方が多いと思います。でも、きっとこういう人多いと思います。
『怒る夫』 西田小夜子(作家)
チェロだけのコンサート「チェロざんまい」はすてきだった。
ずうたいは大きいけれど、控えめなチェロの音が糸子さんは好き
である。4人のチエロ奏者は彼女を魅了した。終わると夕方5時近か
ったが、まっすぐ家に帰りたくない。友達も同じで、ちょっとお茶を飲
んで行くことにした。ホールの喫茶室は満員だ。近くのレストランに
行きメニューをながめているうち、何となく「夕飯食べちゃおか」と
話が決まる。
糸子さんは夫のことがチラッと頭をかすめた。やさしい人だし定年
後は家事も手伝うが、ひまはあっても「めし作り」だけは絶対にやら
ない男だ。女房の料理が好き、というか、めしは女が作って当然と
信じている。
友だちの夫は、「弁当でもカップラーメンでも平気」な人でうらや
ましい。急いで食事を終え、自転車をすっ飛ばして帰宅した。夫の
怒りは予想をはるかに超えていた。
糸子さんは店から夫に電話したのに「めしまで食うとは聞いてい
ない。おれは腹ペコで待っていた。なぜ友だちに断れなかったんだ」
と、頭のてっぺんからゆげが上がっている。
いつもいつもいつも、出かけるときは夕飯の準備をしていく。結婚
以来40年以上続けてきた。今夜は予定が狂っただけである。夫は
どうだろう。夕飯を作り待っていたのに、食事してきたことが何度も
あるじゃないか。
汗まみれで夫のごはんをテーブルに並べているうち、糸子さんは
怒りと悲しみとあきらめの感情にうちひしがれていった。
 こういう方とは、まず一緒に一日も私はいられません。
こういう方とは、まず一緒に一日も私はいられません。バレエを引退するまでの私は、週5日は毎日忙しく、主人が子ども
の夕飯と世話をやいてくれたからこそ、安心してレッスンし、夜12時
に家に帰っておりましたから…
いまでも、脚の痛い痛くないにかかわらず、家事全般に渡って
やってくれます。 今日は夕飯もこれから作ってくれます。
へへへへ。最後はのろけになりました。
昨日、‘きらら'の相棒Sさんと神奈川県座間市の
「ひまわり畑」へ遊びに行きました。
一面の‘ひまわり'
一斉に太陽に向って伸びています。
目に飛び込んできます。
とっても、生きていてよかった~
と元気がでました。
田んぼの休耕地に農家の方が、植えています。
隣には、元気な稲が 頭を真っ直ぐにして、あおあおと
しています。
やっぱり、自然はすばらしい!
大切にしないといけませんね。
今日は、母の3回忌。
朝から、お経をあげました。 あげながら声がつまり、
涙が出ました。
私たちは、しっかりと生きています!
おかあさん、見ていてくださいね。
今日も、叔母はデイサービスに行けました。
昨年の今頃は、背中と腰の圧迫骨折のため、痛みがひどく、
入院もベット待ちで…私にとっては大変な夏でした。
一昨年は、亡き母も入院中で、いつ危なくなって病院から
電話が入ってもおかしくないような状態の中、叔母は認知症で
昼夜逆転… 叔母の隣の家の方から、はっきりとは言わないが
迷惑だから、なんとかして!ください。という電話が入り、私は、
二人介護に気が変にになりそうでした。
でも、今 叔母は、すっかり正気になり、元気に笑えるようになり
、日常生活の身だしなみにも注意ができるようになりました。
時間がかかりましたー。
今日は、この記事で辛かった二人介護とひどかった叔母の
状態を思い出しましたので、皆さんにも知ってもらいたい、と
思いご紹介します。
『夏の気掛かり』 ~把握できない生活リズム
柴田範子(NPO法人‘楽'理事長)
今年の夏は、自宅にいても熱中症になり、体調を崩すお年寄り
が少なくありません。私の自宅の近くでも、63歳の男性が亡くなり
ました。人との付き合いを嫌って2、3年。男性の両親の介護や
入院時には、近所の住民が多くかかわっただけに悔やまれます。
「ひつじ雲」の職員会議でも、一人暮らしをしている認知症のある
Aさん(79歳)について話し合いました。Aさんのマンションは、利用
者の中で「ひつじ雲」から最も遠くにあり、すぐには飛んでいけないの
です。現在要介護2で(うちの叔母と一緒)、自分でてきることも多く、
自宅では深夜に起きて、いろいろとしていることもあるようです。
職員から、朝訪問すると、前日冷蔵庫に用意した飲み物が空に
なっていると報告を受けました。夜間、のどが渇いて飲んでいるそう
です。寝る時にはエアコンも扇風機も止めます。A子さんの年代が持
つ価値観かもしれません。夕食の配達時間は午後4時前で、A子さん
は食事が届くとすぐに食べ、そのまま横になってしまいがちで、生活
のリズムにも課題があります。
会議では訪問回数を増やし、配食の配達時間を遅く出来ないか、
事業者と調整することにしました。でも、日中の訪問回数を増やした
としても、この暑さの中、夕方から翌日までの過ごし方が、細かく
把握できないことが気にかかります。
マンションの管理人さんがA子さんを気にかけてくれているので、
日が暮れる時間帯に職員が訪問して管理人さんに寝る前の巡回を
お願いできないか。気にかかることは、解決できるよう急いで進める
ことにしました。 なんて、気配り思いやりのある、事業所でしょうか!
なんて、気配り思いやりのある、事業所でしょうか!
うちから前に叔母が住んでいた所まで、車で15分、毎日ヘルパー
さんに1時間半入ってもらっても、結局心配で毎日、様子を見に
行きました。昼夜逆転、真夏にカーテン窓締め切り、エアコンも扇
風機もついてない。部屋がサウナのようでした。
もし、今年のような猛暑なら!と考えると恐ろしいです。
大分県国東市の吉広地域、(144世帯の集落で65歳以上の高齢
化率45%) 「黄色い旗運動」というのを知りました。
朝起きたら「黄色い旗」を玄関先に掲げ、夕方には家の中にしまう。
旗がかかっていないと、近隣の人が訪問して「どげんかしたかえ」と
安否を確認する。同様の運動は他の地域にもあるが、ここはお年寄
りの家に限らず全世帯が取り組んでいるそうです。一人暮らしに限る
と悪質な訪問販売の標的になるからと。一人暮らし女性の家の旗が
立っていなかったので近所の人が訪ねると「わざと立てなかった。
誰かに来て欲しくて、寂しくて」
都会で黄色い旗運動は、とても無理だと思われますが、
「寂しくて、誰かと話したい」 お年寄りの心は、都会ほど満ちている
かも?!
残暑お見舞い申し上げます。
今日の新聞で、猛残暑に注意! と書いてありました。
どうぞ、みなさまお体大切にご自愛下さい!
私は、お陰さまで夏バテしておりません。家族みな、元気に
しております。
夏バテで、食欲のない時に良いのでは、と思った記事が
ありましたので、ご紹介します。
指導:石原結實
(長寿地域として名高いグルジア共和国のコーカサス地方や
スイスのペンナー病院で自然療法を研究。伊豆に開設する
サナトリウムには、著名人など多くの人が訪れる。著書多数)
野菜の力で免疫力アップ
『人参ジュース健康法』
朝一杯の人参ジュースが、健康維持にとても役立つと言う。
数多くの患者に人参ジュース療法を施している、石原結實先生に
聞いた。
「現代人は、タンパク質や炭水化物、脂肪を摂り過ぎています。
その一方で、ビタミン、ミネラルが不足している。いわば栄養過剰の
栄養失調状態です」
おなかいっぱい食べることに問題あり。食べ過ぎは免疫力にとっ
てもマイナスだという。
「血液中に栄養分がありすぎると、免疫力はうまく働きません。
実は空腹時こそ免疫力が上がる時なんです」
そこで石原先生が勧めるのが人参ジュースだ。人参には生命に
とって必要なミネラル、ビタミンが豊富に含まれ、根菜なので、体を
温める作用もある。上手な飲み方は、人参ジュースを朝食代わりに
すること。これによって過食を防ぎながら、ミネラル、ビタミンを大量
に摂取し、かつ免疫力を高めることができる。朝食を軽くすると、
消化に使っていたエネルギーが排泄に回り、便秘やむくみの解消の
効果もあるという。
「昼食や夕食で減食するのは努力がいりますが、朝食を人参ジュ
ースにするのは楽ですし、いろいろな野菜をアレンジするのも楽しい
ですよ」
ジュースの栄養分は時間とともに失われるため、ジューサーを使
った搾りたてを飲むのがベスト。ミキサーは繊維分がジュース内に
残り、そこに栄養分が付着して吸収を妨げるので、ビタミン、ミネラル
を摂取するためにはジューサーがいいという。また皮と実の間に
動脈硬化を防ぐポリフェノールが多く含まれるため、たわしでよく洗っ
て皮はむかずに使用したい。
☆人参ジュースの作り方
①人参2本400gをたわしでよく洗い、皮はむかずに適当な大きさに
切る。
②リンゴ1個も同様に、たわしでよく洗い、皮はむかずに適当な大き
さに切る。
③ジューサーを使って人参とリンゴを生ジュースにして、朝食代わり
に飲む。冷える場合は、人肌程度に温めて。
●症状・体調に合わせプラスしたい野菜
・キャベツ→胃潰瘍・胃もたれに
・玉ねぎ→糖尿病
・生姜→冷え性
・セロリ→血栓症 家事が苦手な私は、もっぱら、(はずかしい…)こんな記事を書いて
家事が苦手な私は、もっぱら、(はずかしい…)こんな記事を書いて
も、自分では市販の人参ジュースを飲んでます。うちには、ジュー
サーがありません。
でも、試してみるのも…あり、だと思います。 へへへ…
「猛残暑に負けないでね!」
「戦死した軍人・軍属と空襲や原爆などで亡くなった民間の犠牲者
計310万人の冥福を祈り、平和への誓いを新たにする」
映画にもなった「回転」特攻隊員だった、哲学者の上山春平さんの
言葉「最大の愚考から、最大の教訓を学びとること、これが生き残
った特攻の世代に背負わされた課題なのかもしれません」
「戦争から教訓を学ぶ責任は、若い世代に引き継がれた」
―――新聞から―――
見当もつかない多くの犠牲がはらわれました・・・
でも、いまだに、戦争が無くなりません。
65年経って、今、なぜか色々なところで、負の部分が大きく影を
おとしています。
ー不明高齢者、100歳以上 281人確認できぬまま削除ー
無縁仏となって、誰にも知られず… なんでしょうか。
悲しく、暗い気持ちになりました。
「高野山教報」の記事に目に付きました。
『家族制度の崩壊』
昭和20年に始まる時代の激変に、それまで日本を支えていた
世代が戸惑い、自信を喪失していくのは、自然の成り行きだったと
いえるでしょう。まさに既成の秩序や価値観の大崩壊・大転換です。
戦争が終わり、戦地や海外の植民地からたくさんの人が引き揚げ
てきました。そして昭和22年(1947年)から昭和24年にかけ、赤ちゃ
んの出生率が急激に上昇します。これがいわゆる「団塊の世代」
ですが、生きてゆくのに精一杯で子どもの家庭教育どころではない
家庭が多かったのも、仕方がなかったことかもしれません。
この時期、従来の日本の「家族制度」も、過去の日本国家を支えた
悪の根源とされ、古来の道徳の規範であった「親孝行」などもっての
ほかと、破壊の標的にされました。
家族は、一人ひとりが独立した人権を持ち、親子といえども平等
だというのが、まさに正論とされていったのです。確かに、ただ威張
るだけの親にも家族はおとなしく服従し、親を大切にしなければなら
ないという「親孝行」なら、そんな理不尽なことはありません。だから、
それは一面、正論に違いありませんでした。
しかし、同時に勢いのおもむくところ、社会構成の最小単位である
家庭が見落としてはならない大切な役割までも、見失わせることに
なります。その当時「親と子は、友だちのような関係が理想的」と
いう、まことにおかしな考え方も流行しました。その結果、人間の
生き方や、社会の秩序を維持していくためのルールを、子どもに
しっかり伝えていくべき家庭が、その働きを十分に果し得なくなって
いったのです。もちろん一部ではありましょうが、学校も例外ではあ
りませんでした。生徒と先生も、友達のような関係が理想的というこ
とを真面目に言う者が少なくなかったのです。
その頃の話で、親と先生の会話を紹介した、雑誌の記事がありま
す。
「先生。うちの子はシツケが全くできていません。もっと学校で
教えて下さい」
「そうですか。ところでお宅のお子さん、算数の理解が不十分です。
うちでしっかりと教えてください」
もちろん、すべての大人や家庭がそうだったわけではありません。
「しっかりした家庭」が全く無くなってしまったわけではないのです。
ですが、社会の傾向がそうした方向へ大きく動いていったのは、否定
できない事実でありました。
(そして、親と先生のこうした会話は、今も続いています)
 今ある自分も、親の代、先々の代からの多くの人の歴史から成り
今ある自分も、親の代、先々の代からの多くの人の歴史から成り経っています。 戦争の愚考を忘れることなく…
唯一の核被爆国として、できることを…
しっかりと私たちの次の世代に教訓として、責任持って伝えていく
義務があると、大げさですが、思いました。
ですが、私のまわりはいたって静か。
どこへも出掛けないので、いつもの変わりない生活です。
今はお盆なので、今日は「高野山教報」から、記事をご紹介します。
『認め合い支え合う いのち』
辻 雅榮
「長男は、父親が何で死んだんか、まったく理解できていません。
だから許せない、と言っています。斎場できっとパニックになります。
どうしたらいいんでしょうか」と、働き盛りのご主人を亡くされた奥様
から電話があり、お葬式を依頼されました。檀家ではありませんが、
電話を切って、すぐに馳せ参じて枕経を唱えました。
奥様(喪主)の一番の心配事は、今年19歳になる長男S君の病気と
障害です。S君はは、生まれたときから糖尿病で、食前に血糖値を
計って注射を打ってからでないと食事ができません。それに高機能
自閉症という障害を持っています。養護学校を卒業した後、学童
からお世話になった病院で勤めています。
ところが、八ヶ月前突然、父がガンの告知を受けそれを知った
S君は、ショックで仕事に行けなくなり、不登校生を預かるボランテ
ィアさんのサポートを受けています。
お葬式の流れを説明した後「お父さんにお伝えしたいことは何か
ありませんか。それを通夜のとき、読んでみませんか」と、お尋ね
したところ「あ、それいいかも。S君は作文得意やし、書くよ。きっと」
三姉妹が賛同し、S君が父に送ることばを書いて、四人を代表して
S君がそれを読むことになりました。
お経が終われば、さあ、いよいよ出番です。四人が父の御霊前
に恭しく焼香をし、くるりと振り返って一礼します。
「お父さんに言い残したこと、いっぱいあります。今ここで言います。
お父さんは戦士です。八ヶ月よく闘いました。(略)今日、お父さんの
人生の学校の卒業式です。これからは仏さまの学校です。僕たちも
がんばります。お父さんこれから、僕たちをみといてください」
翌日、無事に本葬儀が終わりました。霊柩車で斎場へ向う途中
後部座席の三人(喪主・S君・三女)が父親のことをはなしています。
斎場に着き、棺を安置し読経、焼香、かまどの前に至ります。
火炉の扉が開き棺を中に入れ、火炉の扉が閉まったその瞬間。
「バンザーイ。バンザーイ。バンザーイ」S君は涙ながらに父の名を
呼び、万歳三唱を繰り返します。しばらくして、収骨室でお骨を壷に
収めます。「お父さん、こんなになっちゃった。でもあったかい」と
骨壷を抱いています。そのご慣例に従って法要しました。
翌朝、びっくりすることがおこりました。S君が職場に復帰し、また働
き始めました。なぜこれほどの心境の変化をもたらしたのでしょう。
高機能障害を持っているS君には、納得のゆかない急激な変化は
禁物です。パニックを起こします。しかし、みんなで経験を重ねながら
ゆっくり進んでいく仏教の儀礼は、とても相性がよかったようです。
まず、枕経で、大切な人が現実に亡くなってしまったということを
遺された者が実感する機会となりました。家族や親族が集まり、同僚
たちが仕事を休んで弔意を表しに来られた姿を見て、自分が人々と
とのつながりの中にいて、何かあれば援助や支援が得られることを
実感できました。決して自分は一人ではなかったのです。
メッセージを書いて読むということは、遺されたものが、逝ってしま
った人の人生を振り返ること。その人との関係を確認する作業になり
ました。これが遺された者が新たに歩みだすときの出発点をつくって
くれたのです。これらの働きは、いずれもお葬式が公的なものである
ことに由来します。死別は私的な体験ですが喪主が会葬者を集めて
行う葬儀は公的なものです。
人は認め合い支えあうことで、死別の悲しみを癒し、通過儀礼を
行うことで、満足や達成感が生まれ、孤独な状態からの健全な快復
をうながしていくのです。そのお手伝いをさせていただくのが私たち
僧侶の役目です。
 お葬式もこれからは、新しい儀礼として変化するようですが、彼の
お葬式もこれからは、新しい儀礼として変化するようですが、彼の心の深いところが、感じいりました。