臨床細胞学会の細胞診専門医の資格更新のお知らせが来た。
クレジットがぎりぎりでヒヤヒヤしていたのだが、無事更新完了。

病理医は病理医として取るべき資格が少なく、病理専門医と細胞診専門医くらいしか無い。
もちろん、臨床を経験している先生などで、内科や小児科の専門医をとってから病理に転科してきている先生も結構いて、それぞれの専門医資格を持っておられる方は多いが、どうやって資格を更新しているのだろう。
何でもそうだが、資格の更新というのは難しい。
更新の要件というのを必要最低限にしたところで、「え?そんなんでいいの?」という人がいたり、「それでもむり!」という人がいたり。
ところで、細胞診専門医というのは、私のような中年以上の世代の病理医にとっては悩ましい資格だ。私がいた教室なんかでも、細胞診専門医資格を持っている先生は先輩に一人いただけだったのが、あるときから、毎年一人か二人、受けるようになり、きがついたら、5、6人の先生が資格を取っており、そのうち、後輩が病理専門医をとったら次は細胞診、というようになり、相当数の病理医が細胞診専門医資格を持つようになっていた。
私なんぞ「うちの教室は細胞診とらないから」などとうそぶいていたのだが、今の病院に来てほかの病理学教室出身の先生と一緒に仕事をしていると、細胞診専門医資格をもっていないとどうも格好が悪い。もちろん、その先生(上司)は資格を持っていて、細胞診診断のサインアウトをしていて、私もまあ、一応するのだが、いかんせん、細胞診の勉強というのをきちんとやったことが無い。
結局は、ここのところがきつい。
日本の多くの病理医は血液と細胞はきちんと勉強したことがあまり無い(ハズだ)。ついでに言うと、法医解剖もできない。教育研修システムが無いというのことが最大の原因で、細胞診の勉強というのも大学病院ではあまりできない。
というようなわけで、細胞診ができない、というよりは細胞診の勉強をしたことがない、というのがコンプレックスになる。「細胞診てなに?」
ということで、一念発起、40近くになって、私も臨床細胞学会主催の勉強会に出て系統的に勉強した。これは、今でも良かったと思っていて、細胞診というものを曲がりなりにもちょっと勉強したおかげで、恐怖心は減った。
専門医資格をとればとったで、臨床細胞学会に出てクレジットを稼がないといけないのだが、これも勉強、仕方あるまい。
医師免許症と違い、専門医資格にはそれなりの内容が必要だ。
やっぱり、この間の福岡、出ておけば良かったか。
 にほんブログ村
にほんブログ村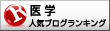
クレジットがぎりぎりでヒヤヒヤしていたのだが、無事更新完了。

病理医は病理医として取るべき資格が少なく、病理専門医と細胞診専門医くらいしか無い。
もちろん、臨床を経験している先生などで、内科や小児科の専門医をとってから病理に転科してきている先生も結構いて、それぞれの専門医資格を持っておられる方は多いが、どうやって資格を更新しているのだろう。
何でもそうだが、資格の更新というのは難しい。
更新の要件というのを必要最低限にしたところで、「え?そんなんでいいの?」という人がいたり、「それでもむり!」という人がいたり。
ところで、細胞診専門医というのは、私のような中年以上の世代の病理医にとっては悩ましい資格だ。私がいた教室なんかでも、細胞診専門医資格を持っている先生は先輩に一人いただけだったのが、あるときから、毎年一人か二人、受けるようになり、きがついたら、5、6人の先生が資格を取っており、そのうち、後輩が病理専門医をとったら次は細胞診、というようになり、相当数の病理医が細胞診専門医資格を持つようになっていた。
私なんぞ「うちの教室は細胞診とらないから」などとうそぶいていたのだが、今の病院に来てほかの病理学教室出身の先生と一緒に仕事をしていると、細胞診専門医資格をもっていないとどうも格好が悪い。もちろん、その先生(上司)は資格を持っていて、細胞診診断のサインアウトをしていて、私もまあ、一応するのだが、いかんせん、細胞診の勉強というのをきちんとやったことが無い。
結局は、ここのところがきつい。
日本の多くの病理医は血液と細胞はきちんと勉強したことがあまり無い(ハズだ)。ついでに言うと、法医解剖もできない。教育研修システムが無いというのことが最大の原因で、細胞診の勉強というのも大学病院ではあまりできない。
というようなわけで、細胞診ができない、というよりは細胞診の勉強をしたことがない、というのがコンプレックスになる。「細胞診てなに?」
ということで、一念発起、40近くになって、私も臨床細胞学会主催の勉強会に出て系統的に勉強した。これは、今でも良かったと思っていて、細胞診というものを曲がりなりにもちょっと勉強したおかげで、恐怖心は減った。
専門医資格をとればとったで、臨床細胞学会に出てクレジットを稼がないといけないのだが、これも勉強、仕方あるまい。
医師免許症と違い、専門医資格にはそれなりの内容が必要だ。
やっぱり、この間の福岡、出ておけば良かったか。










