残念ながら病気になってしまった場合、別な病気、再発にかかわらず、またかかりたいと思う病院とそうでない病院とがある。
自分に命を与えてくれるような医者、というのはいない。すなわち、名医というものは、数は少ないものの、少なくとも一人ではない、ということが明らかになっているので、かかりたい医者というのも取り替えが可能になってきている。
念のためいっておくと、その病気にかかった患者さんの数が多い疾患に関する名医はたくさんいるが、10万人に1人とかしかかからないような病気に精通した医者というのは少ないので、その医者が必ずしも名医でなくても、代わりがみつからない患者さんもいる。
さて、なぜそうなったかと言えば、医療技術があまねく世間に知れ渡り、少なくとも技術的に隠すことができなくなってきているからだ。あとは、経験さえ積めばある程度のレベルに達することはできる。
その経験を積むために、多くの若い医者は多くの患者さんが集まる病院で研修する。
病院側としても、もうけは別として、病院のレベルを上げるためには、多くの医者に来て欲しいし、そのためには多くの患者さんにも来て欲しい。要するに、経営努力が必要となる。
病院にとっての経営努力とは何か。一昔前なら、名門大学附属病院、名門病院といったようなところにかかって、教授とか教授級という偉い先生に盲目的に診てもらっていた。そういう病院でしか知られていない伝統技術、知識というものがあり、他所の病院の医者はそういったことを知らなかったわけだから、やむを得ない。
だが、いまや、そうではない。頑張っている医者、腕のいい医者というのは、どこにでもいる。病院間の技術格差が狭まりつつある。そういう状況になってくると、どこで差をつけるか、ということになる。
重要なのはもてなしの精神だろう。建物が立派で権威がたくさんいても、そこに行って不愉快になっては仕方が無い。
受付が不愉快、看護師がぶっきらぼう、採血で技師が不親切、レントゲンをとるときに恥ずかしい思いをした、掃除が行き届いていない・・・、そして医者が患者を馬鹿にしている。
そんなことが積み重なると、患者さんは簡単に病院を変えてしまう。
病院というところは誰も来たくないところである。だから、そこに働く職員は、愛想良く、明るく、来た人を元気にするようにおもてなししないといけない。
というようなことを考えていたら、何も、病院に限った話ではないということに気がついた。
たとえば、遊園地。先日、東京ディズニーランドが30周年をむかえた。30年前に初めて訪れたときは、働いている人(キャスト)たちの愛想の良さ、明るさに戸惑ったが、それこそが楽しさの元で、アトラクションなど二の次だった。
それまでの遊園地といえば、係員がめんどくさそうにアトラクションを動かし、客は恐縮して楽しませてもらっていた。ディズニーランドは、キャスト全員が、客を楽しませている。
医療技術(=アトラクション)に差がつきにくくなった今日、病院では医療従事者(=職員=キャスト)全員が患者さんに対して明るく、元気に接しないといけなくない。めんどくさそうに働いている、ネガティブな人のいる病院には誰も来たくない。そんな病院からは、患者さんは別のところに移ってしまうだろう。
なお、前提となる医療技術は高くて当然である。
 にほんブログ村
にほんブログ村
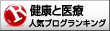 健康と医療 ブログランキングへ
健康と医療 ブログランキングへ
自分に命を与えてくれるような医者、というのはいない。すなわち、名医というものは、数は少ないものの、少なくとも一人ではない、ということが明らかになっているので、かかりたい医者というのも取り替えが可能になってきている。
念のためいっておくと、その病気にかかった患者さんの数が多い疾患に関する名医はたくさんいるが、10万人に1人とかしかかからないような病気に精通した医者というのは少ないので、その医者が必ずしも名医でなくても、代わりがみつからない患者さんもいる。
さて、なぜそうなったかと言えば、医療技術があまねく世間に知れ渡り、少なくとも技術的に隠すことができなくなってきているからだ。あとは、経験さえ積めばある程度のレベルに達することはできる。
その経験を積むために、多くの若い医者は多くの患者さんが集まる病院で研修する。
病院側としても、もうけは別として、病院のレベルを上げるためには、多くの医者に来て欲しいし、そのためには多くの患者さんにも来て欲しい。要するに、経営努力が必要となる。
病院にとっての経営努力とは何か。一昔前なら、名門大学附属病院、名門病院といったようなところにかかって、教授とか教授級という偉い先生に盲目的に診てもらっていた。そういう病院でしか知られていない伝統技術、知識というものがあり、他所の病院の医者はそういったことを知らなかったわけだから、やむを得ない。
だが、いまや、そうではない。頑張っている医者、腕のいい医者というのは、どこにでもいる。病院間の技術格差が狭まりつつある。そういう状況になってくると、どこで差をつけるか、ということになる。
重要なのはもてなしの精神だろう。建物が立派で権威がたくさんいても、そこに行って不愉快になっては仕方が無い。
受付が不愉快、看護師がぶっきらぼう、採血で技師が不親切、レントゲンをとるときに恥ずかしい思いをした、掃除が行き届いていない・・・、そして医者が患者を馬鹿にしている。
そんなことが積み重なると、患者さんは簡単に病院を変えてしまう。
病院というところは誰も来たくないところである。だから、そこに働く職員は、愛想良く、明るく、来た人を元気にするようにおもてなししないといけない。
というようなことを考えていたら、何も、病院に限った話ではないということに気がついた。
たとえば、遊園地。先日、東京ディズニーランドが30周年をむかえた。30年前に初めて訪れたときは、働いている人(キャスト)たちの愛想の良さ、明るさに戸惑ったが、それこそが楽しさの元で、アトラクションなど二の次だった。
それまでの遊園地といえば、係員がめんどくさそうにアトラクションを動かし、客は恐縮して楽しませてもらっていた。ディズニーランドは、キャスト全員が、客を楽しませている。
医療技術(=アトラクション)に差がつきにくくなった今日、病院では医療従事者(=職員=キャスト)全員が患者さんに対して明るく、元気に接しないといけなくない。めんどくさそうに働いている、ネガティブな人のいる病院には誰も来たくない。そんな病院からは、患者さんは別のところに移ってしまうだろう。
なお、前提となる医療技術は高くて当然である。














