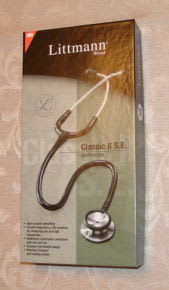8月23日の入院前最後の外来診察の時、入院のご案内という冊子を渡されました。
その中に、入院時の携帯品が書かれたページがあり、それにそって持ち物の準備を進めました。
とは言っても、大した量ではありません。
しかし、それに書かれていないものが、案外重要であったりします。
携帯電話、携帯オーディオ、本その他趣味のものなど、けっこう必需品かもしれないですね。
でも、自分のテリトリーはベッドとその周辺のごく狭い範囲しかありませんので(個室なら別の話です)、余りたくさんのものは持ち込めません。置くところがない・・・・
私は携帯電話、軽めの小説、1GBのウォークマン(小さい!!)、デジカメを持ち込みました。
11年前に、ヴォーリズ記念病院に2週間ほど入院したことがあるのですが、そのとき人間の本質に迫る重い小説を持ち込みました。
ところが読んでいくうちに手術した傷口が痛くなったので、その時の教訓から軽めのものにしました。
ウォークマンは、だいぶ曲の入替を行いました。
クラシック、ポップス、フォーク等そこそこバランスを取りました。
その他、妻が気づいたのがメモ帳でした。私は忘れていました(^^ゞ)
行き先を書いたり看護師さんや先生に言付けを頼んだり、いろいろと役に立ちます。
前回入院時、ベッドにいない患者さんを看護師さんが探してバタバタ走り回っているのを、よく見ました。
私もその1人だったかもしれないんですが、このままでは看護師さんに負担かけるなあと。
それで妻に電話して、メモ帳を持ってきてもらいました。
それに行き先をいろいろ書いて、ベッドを離れるときに行き先を書いたページを開いておくようにしたんです。
これが予想以上に看護師さんに好評で、笑顔で「いますねえ」などと、わざわざ覗いていく看護師さんもいらっしゃいました。
「豆パパさんのような患者さん初めて・・・・」
それきり私は忘れていたのですが、妻が思い出してくれました。
今回も役に立ちました。
日程がすべて決まったので健康保険限度額適用認定証の発行を申請すると、翌々日には認定証が届きました。これは用済み後返却しなければなりません。
診断書は上司経由で人事に提出しました。
これですべて手続きは完了しました。
余談ですが、最終出勤日は9月3日(金)でした。
前日の2日に上司が職場の社員全員に、私の入院のことをメールで回しました。それと他職場で特に連絡が必要な部署には上司に頼んで、入院メールを回してもらいました。
調整が必要な部署に関しては、2週間以上前から打ち合わせを済ませていました。
おかげで、金曜日は入れ替わり立ち替わり人がやってきて、事情を聞かれたり、励まされたり、アドバイスもらったりで、力をたくさんいただきました。
その中に、入院時の携帯品が書かれたページがあり、それにそって持ち物の準備を進めました。
とは言っても、大した量ではありません。
しかし、それに書かれていないものが、案外重要であったりします。
携帯電話、携帯オーディオ、本その他趣味のものなど、けっこう必需品かもしれないですね。
でも、自分のテリトリーはベッドとその周辺のごく狭い範囲しかありませんので(個室なら別の話です)、余りたくさんのものは持ち込めません。置くところがない・・・・
私は携帯電話、軽めの小説、1GBのウォークマン(小さい!!)、デジカメを持ち込みました。
11年前に、ヴォーリズ記念病院に2週間ほど入院したことがあるのですが、そのとき人間の本質に迫る重い小説を持ち込みました。
ところが読んでいくうちに手術した傷口が痛くなったので、その時の教訓から軽めのものにしました。
ウォークマンは、だいぶ曲の入替を行いました。
クラシック、ポップス、フォーク等そこそこバランスを取りました。
その他、妻が気づいたのがメモ帳でした。私は忘れていました(^^ゞ)
行き先を書いたり看護師さんや先生に言付けを頼んだり、いろいろと役に立ちます。
前回入院時、ベッドにいない患者さんを看護師さんが探してバタバタ走り回っているのを、よく見ました。
私もその1人だったかもしれないんですが、このままでは看護師さんに負担かけるなあと。
それで妻に電話して、メモ帳を持ってきてもらいました。
それに行き先をいろいろ書いて、ベッドを離れるときに行き先を書いたページを開いておくようにしたんです。
これが予想以上に看護師さんに好評で、笑顔で「いますねえ」などと、わざわざ覗いていく看護師さんもいらっしゃいました。
「豆パパさんのような患者さん初めて・・・・」
それきり私は忘れていたのですが、妻が思い出してくれました。
今回も役に立ちました。
日程がすべて決まったので健康保険限度額適用認定証の発行を申請すると、翌々日には認定証が届きました。これは用済み後返却しなければなりません。
診断書は上司経由で人事に提出しました。
これですべて手続きは完了しました。
余談ですが、最終出勤日は9月3日(金)でした。
前日の2日に上司が職場の社員全員に、私の入院のことをメールで回しました。それと他職場で特に連絡が必要な部署には上司に頼んで、入院メールを回してもらいました。
調整が必要な部署に関しては、2週間以上前から打ち合わせを済ませていました。
おかげで、金曜日は入れ替わり立ち替わり人がやってきて、事情を聞かれたり、励まされたり、アドバイスもらったりで、力をたくさんいただきました。